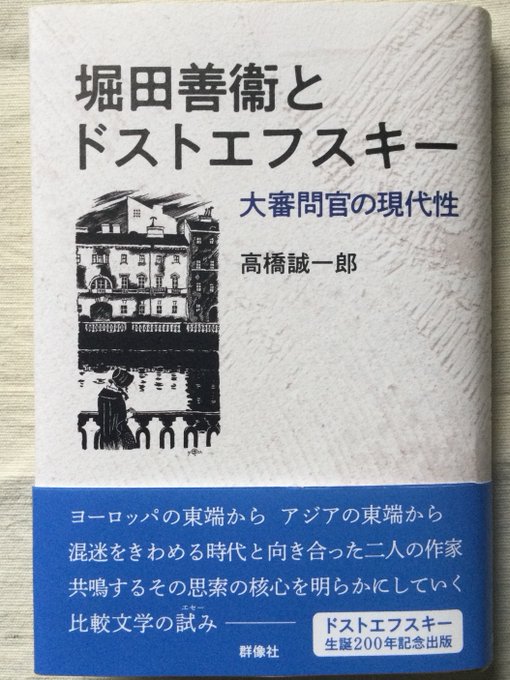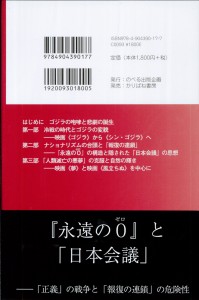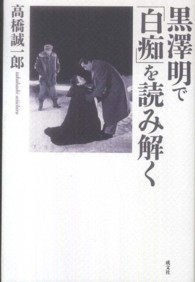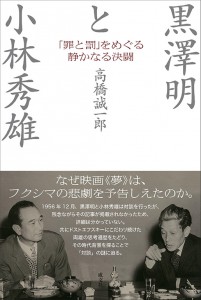(書影は、紀伊國屋書店のWEBより)
(書影は、紀伊國屋書店のWEBより)
はじめに 国際政治の混乱とユーラシア国際政治史
三宅正樹・明治大学名誉教授は前著『文明と時間』(東海大学出版会、2005年)で、国際政治学者ハンチントンの「文明の衝突?」(1993年)や大著『文明の衝突と世界秩序の再編成』と比較しながらトインビーの文明論を比較文明学の視点から再考察することにより、「攘夷主義」や「自国中心主義」の危険性を明らかにしていた*1。
しかし、ソ連崩壊後に唯一の超大国となったアメリカの大統領選挙で「アメリカ第一主義」を掲げるトランプ氏が当選し、地球温暖化対策の国際枠組みを定める「パリ協定」やユネスコからも米国が離脱すると発表しただけでなく、昨年の12月には「エルサレムをイスラエルの首都と認定する」と宣言し、さらに北朝鮮に対しても強硬な姿勢を続けていることで、世界情勢は再び大きく揺らいでいる。
このような状況において、外交文書や極東軍事裁判の供述調書などを詳細に分析するするとともに、「欧露中をまたぐユーラシアを俯瞰する視点」で描かれた三宅氏の『近代ユーラシア外交史論集』(千倉書房、2015年)も、緊迫した世界情勢や今後の日露関係を考える上でも重要な示唆に富んでいるといえよう。まず、目次を引用することで本書の全体像を示しておく。
第1章・ユーラシア国際政治史における帝国と民族/第2章・大正時代の日本――ユーラシア国際政治史の視点から/第3章・後藤新平の外交構想とユーラシア/第4章・世界経済危機から日本の国際連盟脱退まで/第5章・日独防共協定とその後/第6章・独ソ不可侵条約への道/第7章・日独伊三国同盟、日ソ中立条約と独ソ開戦/第8章・フルシチョフの経験した二つの戦争/第9章・ヤルタ密約をめぐる中ソ関係/第10章・スターリン批判から中ソ戦争へ/第11章・共産主義国家ソ連の崩壊
本書ではロシアを「引き裂かれた国家」と定義したハンチントンが注目しているロシアの「ユーラシア主義」とマッキンダーのハートランド理論との詳しい比較がなされている。亡命後にブルガリアのソフィア大学で教鞭をとっていた言語学者ニコライ・トルベツコイの「ユーラシア主義」は、広い視野を持っていた作家・司馬遼太郎の文明観とも近いと思われるので、その点にも注目しながら本書を紹介することにしたい。(以下、本書からの引用頁数は本文中のかっこ内にアラビア数字で示す)。
1.マッキンダーのハートランド理論と「ユーラシア主義」
著者によれば、地理学者でイギリス地政学の創始者でもあるマッキンダーは、日露戦争勃発の直前に行った演説で、世界の歴史をロシア側から見ることを提唱するとともに、ユーラシア大陸の中央の草原地帯こそが歴史の回転軸、ハートランドであると主張し、このハー卜ランドの中央に位置するロシア帝国とハー卜ランドの「内周の半月孤」の中に位置する、強力に武装したドイツ帝国が軍事同盟を結ぶことがあれば、それは英国及び世界全体の脅威になると警告していた(12-13)。
この視点から見ると重要なのが、結局挫折したものの1905年のドイツ皇帝ヴィルヘルム二世とロシア皇帝ニコライ二世との間でフィンランドのビヨルケで交わされた提携密約であり、それは1939年の独ソ不可侵条約ばかりでなく(13)、「日独接近のヒント」ともなっていた(125)。
さらに、ロシアの経済学者で地政学者のピョートル・サヴィツキーの思想が、「新たに人気を獲得していること」にハンチントンが注目していることに注意を促した著者は、中山治一が1944年に発表した論文「ロシア史の基本問題-ロシア史学史への一試論」で、「ユーラシア主義」の歴史学者ヴェルナツキーの見解を紹介するとともに、「中根練二によるサヴィツキーの『ロシア史の地政治学的覚書』の翻訳が、…中略…国立ハルビン学院『論叢』第三号に掲載されている」ことにも触れていたことを紹介している(19-25)。
著者によれば中山はこの著作で、ロシアの正統派史学とマルクス主義史学がともにヨーロッパ史の視野においてロシア史を構成しようとしていたのに対し、ヴェルナツキーがドイツとロシアの地理学者がロシアをまったく恣意的に「ヨーロッパ・ロシア」と「アジア・ロシア」に二分割してしまったと批判していたばかりでなく、「遊牧民族が文化的に劣っていると決めつけるのは大きな誤りであり、一二世紀から一三世紀にかけて、モンゴル民族が政治や社会の形態や組織に関して注目に値する進歩を遂げた事実に言及して」いたことを指摘している(23)。
ロシアにおいて「ユーラシア主義への関心の高まり」が見られるようになるのは、「グラースノスチ」(情報公開)を直接の契機にして1990年代であることに留意するならば、1944年にこのような論文が日本で発表されていたことは注目に値するだろう。
しかも、トルベツコイの『ヨーロッパと人類』の日本語訳が1926年には『西欧文明と人類の将来』と題して出版されていたことを紹介した浜由樹子氏は、満鉄の東亜経済調査局に勤務していた訳者の嶋野三郎がその「前書き」で、トルベツコイについてソフィア大学で歴史学を講じる老学者と権威付けしていたのは、「ユーラシア主義」が「『大東亜共栄圏』につながる発想を擁護しえる」を考えていたことを示していると記している*2。
そして、トルベツコイの生涯を詳しく紹介した浜氏は、1921年に亡命先のブルガリア・ソフィアで論文集『東方への旅立ち』をサヴィツキーなどとともに発刊することで「ユーラシア主義」を宣言したトルベツコイが、「ヨーロッパによる植民地支配に批判的であった」ばかりでなく、カフカス地域の言語と文化の研究をつうじて、「あらゆる民族と文化は、いずれも全て等しい価値を」持つという文化観を有しており、ウィーン大学に移った後では、「排他的ナショナリズム」に訴えるナチズムに対する批判を強めていたことをも明らかにしている*3。
このようなトルベツコイの文明観や先に見たヴェルナツキーのモンゴル観は、学生時代にモンゴル語を学び、学徒動員によって満州で兵役に就いていた作家の司馬遼太郎が後に、「文明的な行為」とされる「耕作」さえも、「草原」地帯では「砂漠」の発生につながることを比較文明論的な視野から指摘していたこととも重なっているように思える*4。
一方、マッキンダーのハートランド理論は、アメリカ・エール大学のニコラス・スパイクマンに影響を与えてリムランド論(日本・朝鮮半島など内周の半月孤の周辺地域をアメリカの提携地帯とすることにより独・露の拡大を防ぐことができるとする)を生み出し、それがまた冷戦初期における外交官ジョ-ジ・ケナンの「封じ込め」理論につながっていた(13)。
このことに注意を促した三宅氏は、ヴェルナツキーのいうユーラシアが、「マッキンダーがハートランドと呼んだ地域とほぼ一致して」ことも指摘して(21)、ユーラシア国際政治を学ぶことの意義を強調している。
2.司馬遼太郎の日露関係観とユーラシア外交史
第1次世界大戦の最中から諸帝国がつぎつぎと崩壊していく時期から始められている第2章では、1918年8月に日米が共同でシベリアに出兵するに到る流れが考察されている。
たとえば、「原敬日記」では「清帝国崩壊直後の中国についての言及が比較的少ないのにくらべて」、「ロシア帝国崩壊直後のロシアについては、しばしば詳細な記述が見られ、しかもこれらの記述はシベリア出兵論についての批判が大半を占めている」ことにも注意が促されている(43)。
日本ではシベリア出兵についてはあまり知られていないが、司馬は「執拗につづけられた」日本軍のシベリア出兵を、「前代未聞の涜武(とくぶ)といえる」と激しい言葉で批判していた*5。実際、連合国が1920年には相次いで撤兵したにもかかわらず、1922年まで単独で駐留を続行し、当初の約束に反してバイカル湖畔の都市イルクーツクまで占領したために、日本軍は連合国から領土的な野心を疑われることとなっていた。そのことを考慮するならば、シベリア出兵は、日ソ中立条約を破って満州に侵攻したソ連軍の行動などにも影響を及ぼしていると思える。
さらに、作家の司馬遼太郎は『翔ぶが如く』において、「日本に貴族をつくって維新を逆行せしめ、天皇を皇帝(ツァーリ)のごとく荘厳し、…中略…明治憲法を事実上破壊するにいたるのは、山県であった」と厳しく山県有朋を批判していた*6。本書でも元老山県有朋によって事実上の日露軍事同盟を意味する第四回日露協約が、第一次世界大戦のさなか、ロマノフ王朝崩壊のわずか九カ月前に締結されていたことが指摘されている(50)。
1933年に「相次いで国際連盟を脱退して孤立の道に進み出た日本とドイツは、やがて相互の提携を模索するように」なり、1936年には日独防共協定が結ばれることになったが、その時に提携を担当したドイツ駐在武官の大島浩にとって「日独接近のヒントとなった」のが、1905年にドイツ皇帝とロシア皇帝との間でフィンランドのビヨルケで交わされた提携密約であった(125)。
司馬遼太郎は1939年に満州国とモンゴル人民共和国の間で国境線をめぐる緊張が高まる中で、日本軍が起こしたノモンハン事件を厳しく批判しているが*7、三宅氏は同じ年の8月23日に独ソ不可侵条約を結んでいたドイツが2年後の9月に条約を破ってソ連への侵攻した理由を、ノモンハン事件にも言及しながら、1939年から40年にかけてソ連・フィンランド戦争でのソ連軍の苦戦が「ヒトラーを頂点とするドイツの上層部に、赤軍への誤った過小評価をもたらした」からだと説明している(253)。
一方、日独伊三国同盟がベルリンで調印されたのは1940年9月27日のことであったがその半年後に、松岡外相と会ったドイツ外相は独ソ戦争勃発の可能性を示唆するともに、その際には「日本の独ソ戦争への介入は必要ないと述べ、シンガポール攻撃を日独伊三国同盟の共通の目標に対する日本の最善の貢献である」と述べていた(203)。
一方、日ソ中立条約は1941年の4月13日にモスクワで調印されたが、この年の御前会議では「ソ連が崩壊した時にただちに介入してウラジオストックからバイカル湖までの、日本が渇望していた地域を占領できるようにしておくための軍事的準備は行う」ことが決定されていた(207)。
つまり、1945年の8月9日にソ連軍が日ソ中立条約を破って満州などに侵攻したことが強く批判されることが多いが、日本側が「中立を維持」していたのも、ソ連が強力な軍事力を保っていたために過ぎず、崩壊した際には条約を破る事が決められていたのである。このことは明らかになった事変や事件だけでなく、外交文書などをきちんと読み解くことの必要性を物語っていると思える。
おわりに
以上、「ユーラシア主義」について記されている第一章について考察し、多くの外交文書や極東軍事裁判の供述調書などをとおして帝政ロシアの崩壊からソ連の崩壊への流れが考察されている本書の第2章から第8章までをごく簡単に紹介した。
長編小説『坂の上の雲』を書き終えた後で、自分が数カ国語を学んだことが「よかったと思っています」と記した司馬は、「世界じゅうの事柄を、自分がすこしでもかじったコトバ(モンゴル語、中国語、ロシア語)の窓からみることができて、すこしは深く感ずることができるからです」と続けていた*8。
大国の「窓」を通して一つの価値をのみを学ぶだけでは、他の方向に向いた「窓」から見えるはずの多くの国々の文化や歴史の価値との出会いはなく、世界情勢の変化をきちんと認識することは難しいのである。
その意味で「日露独中の接近と抗争」ばかりでなく、英仏やアメリカなどの大国やモンゴル、フィンランドなどの動きにも注意を払って国際政治史が多角的に分析されている本書の意義はきわめて大きい。
日本の外交政策がアメリカのみを重視するようになって来たことが指摘されるようになってきている今こそ、日露関係に関心のある人だけでなく、世界史や政治に関心のある多くの方に本書を薦めたい。
――――――――――――――――――
注
1 高橋誠一郎「書評論文 三宅正樹著『文明と時間』」『文明研究』、第31号、2012年参照。リンク→三宅正樹著『文明と時間』(東海大学出版会、2005年)
2 浜由樹子『ユーラシア主義とは何か』成文社、2010年、236~242頁。
3 同上、75~77頁、121~123頁。なお、本書は序論と結論および次の各章から構成されている。第1章 ユーラシア主義をめぐる史料と研究史/第2章 N.S.トルベツコイのユーラシア主義/第3章 P.N.サヴィツキーのユーラシア主義/第4章 運動としてのユーラシア主義
4 高橋誠一郎「司馬遼太郎の文明観―-古代から未来への視野」(リンク→「司馬遼太郎の文明観―-古代から未来への視野」(レジュメ))、『文明の未来 いま、あらためて比較文明学の視点から』、東海大学出版部、2014年、268~282頁。
5 司馬遼太郎の山県有朋観と日露戦争観などについては、髙橋『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』(人文書館、2015年)参照。
6 司馬遼太郎「あとがき」『ロシアについて』文春文庫、1989年、256~257頁。
7 司馬遼太郎『モンゴル紀行』、朝日文庫、1978年、119~122頁。
8 司馬遼太郎「同期生からの依頼」『司馬遼太郎が語る日本』第5巻、朝日新聞社、1999年、87頁。
〔なお、執筆に際しては筒井清忠氏の書評「ソ連・フィンランド戦争の世界的重要性に気付かせる」『週刊読書人』(2016年1月1日)及び、「明治大学広報」(2016年2月1日)に掲載された外池力氏の書評も参考にした。〕
〔東海大学文明学会『文明研究』第36号(219ー224頁)より転載。転載に際しては、ホームページのリンク先も示した。〕