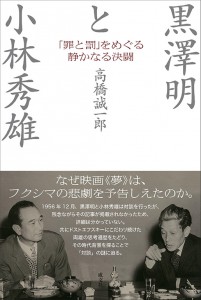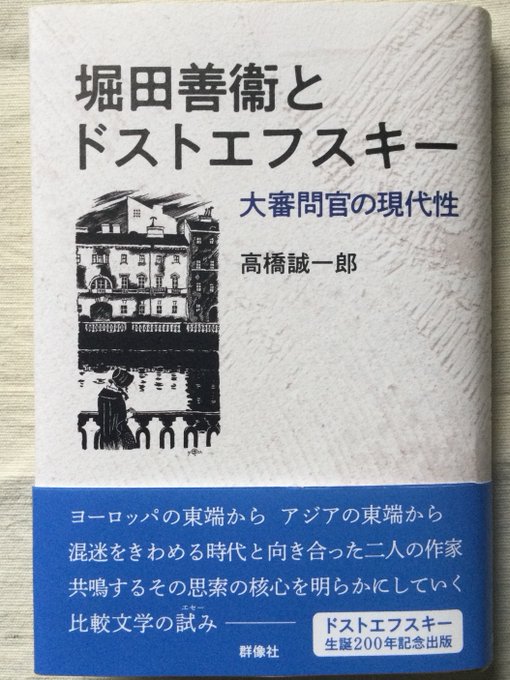一、ポベドノースツェフと「臣民の道徳」
二一世紀の初頭に起きた同時多発テロは世界を震撼させたが、国連の正式な承認を経ずに「テロ」に対する「新しい戦争」として始められたアフガンおよびイラク戦争の余波は、その終結が宣言された現在でも色濃く残っている。さらに、「グローバリゼーション」の強い圧力への反発からナショナリズムが世界中で広がりを見せている。
それはイスラム圏や中国などアメリカとは異なる文明を持つ国々や地域ばかりでなく、「テロ」に対する戦争や経済政策では「同盟国」アメリカとの密接な連帯を強調している日本でも、戦後の歴史認識や道徳的価値観の見直しが急速に進み、「憲法」の改正も視野に入ってきている。
このような最近の政治状況を考えるならば、近代西欧文明の政治・経済・道徳などに対する根本的な批判がなされている『カラマーゾフの兄弟』を頂点とするドストエフスキーの後期の作品が、若い世代にも読まれるなど再評価されているのは、ある意味で当然の流れだといえるだろう。
それゆえ、亀山郁夫氏の大作『ドストエフスキー ――父殺しの文学』(NHKブックス、2004、以下『父殺しの文学』と略し、括弧内に巻数を上下で、頁数をアラビア数字で本文中に示す)を読み始めたときには、二〇〇一年の同時多発テロという衝撃的な事件とアレクサンドル二世の暗殺を、「テロ」という視点から結びつけて論じるという着想のよさに感心し、時宜を得た出版であるだけにおそらく大きな反響を呼ぶだろうと感じた。
しかも、ドストエフスキーがメシチェルスキー公爵から破格の待遇で編集長を依頼された週刊誌『市民』について亀山氏は、「この雑誌は、ニコライ大公とその取り巻きたちが政治的拠点とする極右の機関紙」であり、「悪名高い保守派のポベドノースツェフ」も加わっていると説明していた(下・114)。
それゆえ、スターリンの研究者としても著名な亀山氏が『カラマーゾフの兄弟』など後期作品の問題に、「ロシアの検閲制度」の視点からどのように斬り込むかを期待しながら読み進んだが、ポベドノースツェフ(1827-1907)がドストエフスキーの作品に及ぼした影響についてはほとんどふれられていなかった。
しかも、亀山氏は「政治権力に対する二枚舌」と「ロシア語でいう『イソップ語』」とを同一視して述べている(上・141)。しかし、私見によれば、「政治権力への媚び」としての「二枚舌」が現れるのは、ポベドノースツェフと知り合った『悪霊』の頃からであり、政治権力に対する鋭い批判を隠した「イソップの言葉」とは区別されるべきであろう。
つまり、ドストエフスキーが辿り着いた最後の作品である『カラマーゾフの兄弟』の地点と皇帝の暗殺という事件から、「父殺し」を主題として作家の過去の作品をも分析するという亀山氏の方法は、「男女の関係」や「家族の問題」をとおして作者の意識や感情を深く掘り下げるためには適している。しかしその反面で、『貧しき人々』のジェーヴシキンを「ブイコフの模倣者」であり、「悪と欲望の側へとワルワーラを使嗾する存在」であると規定しているように、官僚制度の腐敗の問題などを「イソップの言葉」で批判した初期作品の意義を弱め、帝政ロシアが有した社会制度の問題を見えにくくしてしまう危険性があると思えるのである。
一方、チェコの哲人大統領と呼ばれたマサリク(1850-1937)は、『ロシヤとヨーロッパ――ロシアにおける精神潮流の研究』(全三巻、成文社、2002-2005、以下、巻数をローマ数字で頁数をアラビア数字で示す)において、ポベドノースツェフが、モスクワで民法と民事訴訟の教授になり皇太子の法学教師も務め、ドストエフスキーが亡くなる前年の一八八〇年から一九〇五年までは、ロシアの教育と宗教を統轄する宗務院の総裁を務めたことでロシアの宗教・教育・政治に大きな影響力を持ったことを具体的に示している。
実際、ニコライ一世の「暗黒の三〇年」と呼ばれた時代の政治手法を高く評価したポベドノースツェフは、アレクサンドル二世の暗殺後に即位した教え子でもある新皇帝と直談判して、父のアレクサンドル二世がその晩年に進めていた憲法制定などの穏健な改革案を廃棄させて、「専制護持」の詔書を出させていた。
そしてこのようなポベドノースツェフの宗教・教育政策は、日露戦争の敗色が濃くなる中で、厳しい格差にあえいでいたロシアの農民や労働者だけでなく、ロシア帝国の「臣民」として戦場にも駆り出されていたポーランドやフィンランドなどロシアに併合されていた属国の民衆や、ユダヤ人やコーカサスのイスラム教徒など少数民族の激しい怒りを呼び、一九〇五年の第一次ロシア革命へとつながったのである。
それゆえマサリクは、ロシア語ではポベドノースツェフという苗字が「勝利をもたらす者」という意味になるとしながらも、苗字から「ポ」の音を省くと「災いをもたらす者(ベドノースツェフ)」となり、さらに「ポベ」を省くと「密告者(ドノースツェフ)」という意味になることにも注意を向けて、「迷信的な宮廷において、幸福で推奨に値する名前」を持っていたポベドノースツェフが、皮肉にもロシア帝国を破滅へと導くことになったと記している(Ⅱ・187)。
このことは学生時代にブルガリアに二年間留学する機会を得ていた私には、よく理解できることであった。すなわち、一九六五年からは返還前の沖縄の基地が使用されて、アメリカ軍による北ベトナムに対する激しい爆撃が行われていたが、三年後の一九六八年には今度は社会主義を守るという名目でチェコへのソ連・東欧軍の侵攻が行われていた。
それゆえ、クリミア戦争や露土戦争でトルコ帝国と戦ったロシアは、ブルガリアではトルコからの解放者として見られていたが、東欧から来た留学生たちのソ連に対する視線はきわめて厳しかった。しかも、ロシア帝国でも属国とした東欧諸国や少数民族に対してロシア正教のみを正当とする宗教政策や、ロシア語を強要する言語政策が実行されていた。こうして東欧の視点から見ると、「スラヴ主義」の時期のドストエフスキーの作品は、このような大国ロシアの宗教・言語政策に無条件に迎合しているとの激しい反発を受けていることも知り、多面的な見方の必要性をも確認することとなったのである。
つまり、ドストエフスキーの後期作品を考察する際には、ポベドノースツェフの宗教・政治観や「ロシアの検閲制度」にも注意を払いつつ、これらの作品を分析する必要があるだろう。それゆえ、本稿では「西欧派」の時期に書かれた初期の作品を分析した拙著の到達点を確認しつつ、今後の日本におけるドストエフスキー研究にも大きな影響を及ぼしている亀山郁夫氏の『父殺しの文学』を批判的に考察することで、「スラヴ主義」の時期に書かれたドストエフスキーの小説の問題点に迫りたいと思う。
二、後期作品への扉としての『白夜』
近著『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』(成文社、2007)において私は、「祖国戦争」の頃に青春を過ごした父ミハイル(1789-1839)だけでなく、プーシキンやゴーゴリ、グリボエードフなど父親と同時代の知識人の作品に対するドストエフスキーの深い関心にも注意を払いながら、『貧しき人々』から『白夜』にいたる作品を考察した。
そのことで、「憲法」や言論の自由がなく「正教・専制・国民性」という三原則を遵守することが「臣民」に求められた「暗黒の三〇年」と呼ばれる時代に若きドストエフスキーが、厳しい検閲に抗しながら「西欧派」の視点から、生命を賭けて「イソップの言葉」によって、教育制度や格差社会の問題点に鋭く迫っていたことを明らかにしようとした。
実際、ドストエフスキーの生涯が黒船の来港に揺れ、「天誅」という名の「テロ」が横行した幕末から、士族や農民のさまざまな反乱の後にようやく「憲法」の制定に至った明治初期の日本の歴史と重なっていることを想起するならば、「文学」という手段でロシアの政治体制の問題点に鋭く迫り得ていた若きドストエフスキーの試みは果敢なものだったといえるだろう。
ただ、後期の哲学的で重たい長編小説ではなく、比較的短い作品が多い初期作品を論じた本書を出すのに、これほどの時間がかかったことに疑問を持たれる方もおられると思う。実は、ペトラシェフスキー・サークルの最左翼に位置したドゥーロフ・グループに属して活動していた頃にドストエフスキーが、なぜ『白夜』というようなロマンチックな作品を書いているのかが、私自身にとっては解けない謎として残っていたのである。
つまり、フランスで二月革命が起きた年に『白夜』は発表されているが、この時期にドストエフスキーは「四年間の外国生活の間に、彼は秘密結社の規約を十分検討し、積極的な闘争方法として、「イエズス会方式、文書宣伝方式、暴動」の三つの行動方式を提起していたスペシネフの影響下に入っていた。そしてベリチコフは、暴力的な革命を目指して秘密結社の規約を十分検討していたスペシネフの影響下にあったこのグループでは「農奴、分離教徒、兵隊など不満を抱くすべての者の間に思想宣伝」をするために活版印刷所が設立され、七人組が結成されたが、「ドストエフスキーはこの七人組の一人だった」とする研究者ドリーニンの考察を紹介しているのである(ベリチコフ著、中村健之介訳『ドストエフスキー裁判』北海道大学図書刊行会、1993、476-77、483)。
それゆえ、ロシアやソ連の「検閲制度」の問題にも詳しいはずの亀山氏が、『白夜』について「白いヴェールを払いとってしまえば」、「あられもない道化芝居に行き着くことは疑う余地もない」(上・113)と断定していることには強い疑問を持った。
その一方で亀山氏は、ドストエフスキーが単行本化された『悪霊』を「ネチャーエフ事件のような途方もない現象も、今日ほど奇怪な世の中になれば起こりうる、その可能性は十分にあるということを書いてみたいと思いました」という手紙とともに、皇太子とポベドノースツェフに献呈していることを紹介し、「政府中枢への接近は、みずからの思想的な転向と身の潔白を公に明かすためにも疎かにできない儀礼だった」と書いている(下・115)。
実際、『悪霊』の描写や心理描写がきわめて鋭いのは、ペトラシェフスキー事件の頃に自分は正しいことをしていると確信していたドストエフスキーが、いつの間にかロシアの体制転覆をももくろむ過激な秘密組織の一員に組み込まれていたことを知ったことで、このネチャーエフ事件という陰惨な事件を外からではなく、そのような事件を引き起こしていたかも知れないグループのかつての一員という視点から描いていたためでもあると思える。このような状況を踏まえて、私は近著で『白夜』で扱われているプーシキンの作品や、最も親しい友人であったプレシチェーエフへの献辞に注目することで、この作品が「イソップの言葉」で書かれた一種のプロパガンダ小説であり、「謎の下宿人」が実は「行動的な改革者」である可能性を示した。
このような私の仮説については、議論のあるところだろう。しかし、プレシチェーエフへの献辞が一八六五年版の『白夜』では省かれていることをも想起するならば、少なくとも『白夜』という作品と『悪霊』との強いつながりは無視できないだろう。このように見てくるとき、『白夜』を「ドストエフスキーの全作品を解く鍵」とまでは言うことはできなくとも、初期作品と後期作品とをつなぐ重要な作品と位置づけることは可能であると思える。
さらに、シベリア流刑後のいわゆる「大地主義(土壌主義)」の時期に書かかれた『死の家の記録』や『虐げられた人々』などの作品で、ドストエフスキーはかつての政治犯であるという自分のおかれた厳しい状況にもかかわらず、「イソップの言葉」で監獄制度や裁判制度の精一杯の批判を行っていた。実際、そのような記述はクリミア戦争敗戦後の「大改革」の時代という状況もあって効果を挙げてもいたのである(高橋『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』刀水書房、2002)。
こうして、この時期のドストエフスキーの思想は、「殺すなかれ」という視点から近代文明を批判しているという点では、保守的というよりも、『聖書』に記されたキリストの言葉に近いといえるのである(芦川進一『隕ちた「苦艾」の星:福沢諭吉とドストエフスキイ』河合出版、一九九七年参照)。
しかし、ドストエフスキー兄弟の総合雑誌『時代』が順調に売り上げを伸ばしていた時期に起きた一八六三年のポーランドの反乱は、ロシアにおける検閲制度の強化を呼んだ。こうして、民主主義的な傾向も強かった『時代』は廃刊に追い込まれ、新たに立ち上げた『世紀』は初めから、政府批判を封じられた形で創刊を許可されていたのである。
この意味で注目したいのは、ドストエフスキーが『罪と罰』において、ラスコーリニコフに自分が法律の専門誌に投稿して採用された「犯罪者の心理」をめぐる論文が、検閲のために雑誌が廃刊となったために、もう日の目を見ることはないと思いこませていたことである。これは一見、ささいなエピソードではあるが、当時のロシアの情勢を考慮するならば、ドストエフスキーはここで言論の自由がない国家では、暴力的な「テロ」が発生する危険性があることを示唆していたと思える。
そして、このような言論の自由を抹殺する「検閲」に対する批判的な視点は、文筆を生業とするドストエフスキーが生涯にわたって持ち続けた視点でもある。
三、「正義の戦争」の批判から賛美へ――クリミア戦争の考察と露土戦争
ドストエフスキーはクリミア戦争の敗戦後に描いた『罪と罰』(1866)において、自分をナポレオンのような「英雄」と見なすことによって、「正義」の名目で高利貸しの老婆の「殺人」を実行した青年を描くとともに、このような主人公の理論が「自己」(自国、自民族、自宗教)の「正義」に基づいて、「他者」への攻撃を「正義の戦争」として正当化する近代西欧の歴史観に基づくものであることも示唆していた。しかも、本編でスヴィドリガイロフ的な「弱肉強食の思想」や「自分の利益の追求」を正当化したルージン的な経済理論を厳しく批判したドストエフスキーは、さらにエピローグにおいては、『カラマーゾフの兄弟』において展開されるゾシマ長老の自然観にも通じるような近代西欧の「自然支配の思想」を批判しうるような視点も提示していた(高橋『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』刀水書房、2000)。
それゆえこの長編小説は、「自国の正義」を強調することで非人道的な原子爆弾や枯れ葉剤の投下をも正当化したアメリカ政府の政策に強い怒りを感じ、近代西欧文明の価値観に深い疑問を持つようになっていた私にとって、「戦争」という「野蛮な手段」を是認してきた歴史観を克服できるような方法と深みをドストエフスキーが持っていると感じて、ドストエフスキーの小説を熱中して読み始めることになる契機となったのである。
しかし、「大地主義」の頃の作品で「自己の正義」を武力で実行することの非を、きわめてキリストに近い視点から根源的に批判していたドストエフスキーの戦争観は、「スラヴ主義者」を自認するようになった露土戦争(1877-78)年の頃からがらりと変わり、戦争の必要性を唱え始める。そして、それは突然の変化ではなく、その遠因にはクリミア戦争(1853-56)とその考察があると思える。それゆえ、ここではドストエフスキーの作品分析からは少し遠ざかるが、クリミア戦争と露土戦争との関わりを簡単に見ておきたい。
クリミア戦争の発端については歴史家の倉持俊一が簡潔にまとめている。「戦争の直接の発端となったのは、フランス皇帝ナポレオン三世が、国内のカトリック勢力の歓心を買うために、聖地エルサレムにおけるカトリック教徒の特権をトルコに認めさせたことであった。トルコ領内におけるギリシア正教徒の保護者を自任していたロシア皇帝ニコライ一世は、そのために失われたギリシア正教徒の権利の回復を要求したが、トルコのスルタンはこれを拒否した」(「クリミア戦争」『世界大百科事典』平凡社)。
これに対してニコライ一世が、トルコ支配下のギリシア正教の同胞を助けることを唱えてバルカン半島に出兵したことで戦争が勃発することとなった。しかし、ロシアが五三年一一月の海戦でトルコ艦隊に大勝利をおさめると、トルコが敗北するのを恐れたイギリスとフランスは翌年三月参戦し力関係が逆転したのである。
ロシアが同じギリシア正教を国教とするバルカンの諸国を救おうとした時に、同じキリスト教国のイギリスやフランスがトルコの側にまわってロシアと戦ったことは、ロシアの知識人だけでなく、ロシアの大衆にも激しい怒りを呼び起こした。たとえば、スラヴ派のホミャコーフは一八五四年に書いた詩において「兄弟たちのために、不屈の戦いを戦え、/神の旗を頑丈な掌で支えよ。/剣で打ち破れーーそれは神の剣なり!」と書いている(高野雅之『ロシア思想史――メシアニズムの系譜』早稲田大学出版部、1989、182)。この時期にシベリアに流刑されていたドストエフスキーもまた、阿片戦争を行ったイギリスの行為を「われわれは虚飾なく野蛮と呼ぶ」と宣言するともに、さらに英仏などがクリミア戦争でロシアに宣戦を布告したことを、「暗愚な、罪深い、不名誉な仕業である!」とし、「神はわれらと共にあり! 進め! われらの偉業は神聖なり」と続けたのである。
これらの詩には、ヨーロッパ中心的な歴史観に対する反発が強く出ているといえるだろう。なぜならば、「十字軍はじつに近代ヨーロッパの英雄的事件」であると強調したフランスの歴史家ギゾーの記述が正しいとしたら、トルコの圧制に苦しむ同じキリスト教のスラヴ諸民族を救おうとするロシアの戦いもまた、そのような十字軍的な「正義の戦い」だったはずだからである。
しかし、クリミア戦争の最中に執筆され一八五六年に出版された『イギリス文明史』で、イギリスのような「文明国」では戦争という「野蛮な行為」は、「次第に使用されなくなっている」とした歴史家バックルは、しかし、「知性の発達とは無縁の民族においては、このような安定を実現することはできない」とした(Istoriya tsivilizatsii v Anglii, Spb.,1896,vol.1.,pp.75-78、ここでは一八九六年版によった)。そして、「歴史におけるこのような格好の例」としてクリミア戦争を取り上げ、この大戦争は「ヨーロッパで最も遅れた二つの国家」であるトルコとロシアの「衝突によってもたらされた」と結論していたのである。
ドストエフスキーなどロシアの知識人を激しくいらだたせたのは、こうした「客観性」のよそおいをこらした「西欧文明中心」史観であったといえるだろう。つまり、バックル的な文明観によって、西欧の肯定的な面のみが強調される時、「文明」の名前において「野蛮」を征伐する「正義の戦い」へと「自国民」を駆り立てることが可能になるのである。 それゆえ、ドストエフスキーは『地下室の手記』(1864)において主人公に、バックルによれば人間は「文明によって穏和になり、したがって残虐さを減じて戦争もしなくなる」などと説かれているが、実際にはナポレオン(一世、および三世)たちの戦争や南北戦争では「血は川をなして流れている」ではないかと鋭く問い質させて、彼の歴史観を鋭く批判させている(『ドストエフスキイ「地下室の手記」を読む』(リチャード・ピース著、池田和彦訳、高橋誠一郎編、のべる出版企画、2006)。
西欧文明のみを「進歩」とし、アジアを「停滞」と規定したヨーロッパの文明観に対して別な歴史観を対置したのが、ペトラシェフスキーの会でフーリエの思想についての講義をしていたダニレフスキーであった。すなわち、ダニレフスキーは『ロシアとヨーロッパ――スラヴ世界のゲルマン・ローマ世界にたいする文化的および政治的諸関係の概観』(1869)において、歴史を「国民国家」ではなく、より大きな「文化・歴史類型」によって分類した。
さらに、この書でクリミア戦争はロシアへの「報復の戦争」を望んだナポレオン三世によって引き起こされたものであると主張したダニレフスキーは、二月革命以後のハンガリー出兵の際にはオーストリアやプロシアなど西欧の諸国も関わっていたにもかかわらず、ロシアのみがその反動性を強く非難されたのは、ギリシア正教を受容したロシアを西欧列強が自分たちの同胞と見なしていないために、不公平な「二重基準」が用いられたためだとした(Danilevsky,Rossiya i Evropa,peterburg,1995)。
そして、カトリックなどとは異なるロシア正教を国教とするロシアが、弱肉強食を是とする西欧列強によって滅ぼされないためには、ロシアを盟主とする「全スラヴ同盟」を結成すべきだと強調したのである。
一方、ドストエフスキーも一八六八年には友人のストラーホフに宛てた手紙で、ダニレフスキーが「フーリエ主義者からロシア主義者」になったことを「まことに天晴れなことです」と書いていた。そして、クリミア戦争後にヘルツェゴヴィナ、ボスニア、ブルガリアなどで正教徒の反乱や戦争が相次いでおきると、ドストエフスキーは『作家の日記』において、「戦争という手段」を用いてでもバルカンのスラヴ諸民族を救うことが必要だと主張するようになるのである。
四、残された謎――『カラマーゾフの兄弟』におけるイワンの悪魔の形象
近著において私がもっとも重視したテーマの一つは、日本ではあまり知られていない外交官で作家のグリボエードフの『知恵の悲しみ』とドストエフスキーの諸作品との関わりであった。
たとえば、ペトラシェフスキー事件に連座して捕らえられたことで覚悟を決めたドストエフスキーはそれまでの「イソップの言葉」でではなく、「現在のような酷しい検閲のもとでは」、「諷刺文学や悲劇はもはや存在しえません」と率直に語り、「グリボエードフやフォンヴィージンのような作家、いやプーシキンでさえ存在できません」と自分が深く敬愛していた作家たちの名前とともにグリボエードフの名前も挙げているのである。
実際、グリボエードフ(1795-1829)が書いた戯曲『知恵の悲しみ』は、プーシキンはじめ多くの貴族の若者に愛読されており、デカブリストの乱が起きた際には彼も逮捕されるが、証拠不十分のために釈放された。有能な外交官でもあったグリボエードフが脚光を浴びたのは、第二次イラン・ロシア戦争(1826-28)後に行われた和平交渉で、ロシアに極めて有利なトルコマンチャイ条約を結び、東アルメニア、カフカスをイランがロシアに割譲させることに成功したためであった。こうして彼には勲章が贈られるとともに、五等官に任じられるが、トルコとの開戦が報じられ、全権公使として派遣されたグリボエードフはテヘランで暴徒に襲われ死亡した。
それゆえ私は、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』におけるイワンの悪魔が、グリボエードフをイメージして形成されているというロシアの研究者の指摘にも言及しながら、ドストエフスキーの全作品を理解する上では、プーシキンとともにロシアの民主化を望んだグリボエードフの『知恵の悲しみ』が重要な働きを担っていることを指摘した。しかし、その際にはなにゆえイワンの悪魔が、ドストエフスキー自身がメフィストフェレスと呼んだ秘密組織の組織者スペシネフではなく、かつて尊敬していたグリボエードフなのかについては深い分析を行っていなかった。ここではドストエフスキーとポベドノースツェフとの関係に注目することで、この問題をより深く掘り下げたい。
ユダヤ人の大富豪であるロスチャイルドのような金持ちになることを夢見ていた主人公のアルカージイを描いた長編小説『未成年』(1875)では、自分の父ヴェルシーロフが主役のチャーツキイを演じたグリボエードフの劇『知恵の悲しみ』を子供のときに見た時のアルカージイの感激を次のように語っている。「彼の足の指にも値しない愚かな連中が彼を嘲笑っている」が、「しかし彼のほうが――偉大な、偉大な人間なのだということが、わかりました」(工藤清一郎訳)。
このエピソードは、皇帝が絶対的な権力を持つロシアの現状を主役のチャーツキイに厳しく批判させていたグリボエードフの『知恵の悲しみ』を、ドストエフスキーが子供の頃からいかに愛読していたかを物語っているだろう。しかし、主人公のアルカージイに、チャーツキイと自分の父に対する尊敬の念を表明させてしていたドストエフスキーは、その後で父親のヴェルシーロフに西欧への幻滅をも語らせることで、ロシアを見捨てて外国へと逃げ出した知識人チャーツキイへの批判の色彩をも込めていたのである(高橋「ドストエフスキーとグリボエードフ(二)」、同人誌『人間の場から』第二三号、一九九一年)。
このことは『悪霊』や『未成年』における主人公の父親たちの形象が、グリボエードフの戯曲『知恵の悲しみ』の考察とも深く関わっている理由を示しているだろう。そして、『カラマーゾフの兄弟』では悪魔の形象の一つとしてグリボエードフが出てくることになるのである。すなわち、研究者のボーゲンはグリボエードフの経歴にも言及しながら、『カラマーゾフの兄弟』の中で悪魔がイワンに言う次の箇所に注目している。
「実はさっき、ここへ来る支度をしながら、僕は冗談のつもりで、コーカサスに勤務していた退役四等官の姿になって、燕尾服に獅子と太陽勲章でも下げてこようかと思ったんだけど、どうにもこわくなってやめたんだよ。だって、少なくとも北極星章かシリウス星章くらいつけずに、よくも獅子と太陽勲章なんぞ燕尾服につけられたもんだという、それだけの理由で、君に殴られかねないからね」(原卓也訳)。
ボーゲンによれば、ここで悪魔が北極星に言及しているのは、デカブリストたちが出していた文芸雑誌「北極星」のことと絡めているだけでなく、グルジアなどコーカサスと密接に結びついていたグリボエードフが初めてのペルシアへの旅でこの「獅子と太陽勲章」を受章していたためでもある(А・ボーゲン、「ドストエーフスキイとグリボエードフ、註への追加」、『ドストエフスキー、資料と研究、八』、ナウカ出版社)。
さらにボーゲンは、グリボエードフは五等官の位で亡くなっているが、退官する際には一つ官等を上げられるのが常であったから、無事に退役していたらグリボエードフも少なくとも四等官にはなっていた筈であると指摘して、ここで悪魔は生き延びたグリボエードフの姿をして現れようとしたのではないかと想定しているのである。
彼の仮説は、おそらく本質を言い当てているだろう。なぜならば、悪魔がイワンに「のべつ君は僕がばかだと言うね。しかし、正直のところ、君と知性を競おうなどという野心も、僕は持ち合わせていないんだ」と語っているように、賢さはイワンの自尊心に深く係わっていた。ボーゲンの説明を受け入れれば、悪魔はここで「ロシアでもっとも賢い人間の一人」グリボエードフの姿を借りて現れようとしたと語る事で、賢い人間を自認するイワンの自尊心を痛烈に皮肉っていたことになる。
そしてそれは、悪魔がなぜこの少し前で、『知恵の悲しみ』の登場人物の一人で秘密組織にも関わっていたレペチーロフの言葉を引用して、「昔この地上に、一人の思想家、哲学者がいて、『法律も、良心も、信仰も、ことごとく否定し』、何よりも、来世を否定したんだそうだ」と述べたかも明らかになるだろう。
しかし、グリボエードフは『知恵の悲しみ』の主人公であるチャーツキイをとおして、秘密結社によって社会を変えようとするレペチーロフの軽率さを批判していたのである。つまり、グリボエードフはペトラシェフスキー会のスペシネフや『悪霊』の主人公のモデルとなるネチャーエフのような人物の批判者だった。
それゆえ、たしかに知名度の点で大きな違いがあるので、読者に与えるインパクトの大きさを考えるならばある程度は理解できるにせよ、『カラマーゾフの兄弟』におけるイワンの悪魔がスペシネフではなく、深い尊敬の対象であったグリボエードフになぞらえられていることには、釈然としない思いが残っていたのである。
前著ではこの問題を詳しく分析する余裕はなかったが、この「謎」を解明するために重要なのは、ポベドノースツェフが「憲法を待望している」大臣たちを「犯罪者」と呼んでいたことに留意する必要があるだろう。すなわち、『カラマーゾフの兄弟』においてグリボエードフを暗示するような言葉を「悪魔」に語らせたときにドストエフスキーは、熱心な読者でもあったポベドノースツェフに「媚び」るために、かつてロシアに「憲法」を制定しようとしていたグリボエードフを悪魔に揶揄させるという「二枚舌」的な表現をしたと思える。
五、ドストエフスキーのユダヤ人観とポベドノースツェフの宗教観
イワンの悪魔の形象と同じような「見えざる検閲」と「二枚舌」的な表現の問題が、『カラマーゾフの兄弟』において、「ねえ、アリョーシャ、ユダヤ人は復活祭に子供を盗んで来て殺すんですってね、本当?」とリーザがアリョーシャに尋ねるシーンにも当てはまると思える。
すなわち、リーザは「わたし何かの本で、どこかのなんとかという裁判のことを読んだのよ。ひとりのユダヤ人が四つになる男の子をつかまえて、まず両手の指を残らず切り落として、それから釘で磔(はりつけ)にしたんですって…中略…子供が苦しみぬいて、うなりつづけている間じゅう、そのユダヤ人はそばに立って、見とれていたんですって」と語っているのである。
清水孝純氏はこれが一八七四年にグルジア娘が失踪して、死体となって発見された際に九人のユダヤ人が告発されたことから、「右翼の新聞雑誌が、血の神話(キリスト教徒の血をとる)のプロパガンダをひろめ」たこととかかわっているだろうという論考を紹介している。そして、これに対してアリョーシャが「知りませんね」と答えていることや、『カラマーゾフの兄弟』が「虚構」の上に成立する文学作品なので、このシーンを理由にドストエフスキーがユダヤ人に対する激しい差別意識を持っていたとすることはできないだろうと結論している(清水孝純『新たなる出発――「カラマーゾフの兄弟」を読むⅢ』九州大学出版会、2001、240)。
ただ、中村健之助氏はドストエフスキーが個人的には「ユダヤ人だからといって敵視する人ではない」としながらも、その一方で容易にロシアの「社会通念」やその時代のイデオロギーに「付和雷同する」傾向ももっていたので、ユダヤ人に対する誤解を広めるような文章を書くことはあると指摘している(中村健之助「ドストエフスキーとユダヤ人問題・覚え書き」『論集・ドストエフスキーと現代』、多賀出版、2001、472、487、以下「覚え書き」と略して、引用頁数のみを括弧内に示す)。
さらに、ユダヤ人・ジャーナリストから、厳しい反論の手紙を受け取った際にも、客観的な事実は無視して、「自分はロシアに住むユダヤ人が居住区その他の点で虐げられているとは思わない」し、「むかしからユダヤ人は金貸し業でナロードを思う存分だましてきた」などの「独善的」な反論をとうとうと書いていることに言及している(484)。このような点を確認した上で中村氏は、それは「ロシアのすることはすべて正しい」という激しい思いこみからくるもので、「開かれた議論ではなく、批判を受け入れない閉ざされた『信念』なのである」として、「非難される側としては非常に迷惑」なことだと書いている(487-88)。
しかし、中村氏も指摘しているように、「大地主義」の時代に書かれた『死の家の記録』ではユダヤ人が人間味を持って描かれていたことや、雑誌『時代』で「スラヴ主義の週刊誌『日(ヂェーニ)』の反ユダヤ主義に反発し、ユダヤ人にさまざまな抑圧的制約を加えることに反対する論陣を張って」いたことなどを考慮するならば、これらの記述をドストエフスキーの「信条」だけに帰することは難しいと思える(509)。
この意味で重要と思えるのが、宗務院の総裁となるポベドノースツェフの宗教的見解である。すなわち、「ロシア教会は絶対的真実を持っており、ロシア教会が絶対的真実である。それ故に、ロシア民族がこの真実を持ち、ロシア民族がこの真実であるのである」(Ⅱ・189)と見なしていたポベドノースツェフは、「国家はすべての宗派の中でただ一つの宗派を正しいものと認め、ただ一つの教会を支持し、それだけを優遇する。そして、他のすべての教会と宗派を劣等のものと見なす」としていた(Ⅱ・192)。
それゆえに、ロシア正教の異端である「旧教徒」(分離派)やロシア帝国内での少数者の宗教であったカトリックやユダヤ教に対する弾圧が強化されただけでなく、このような政策を批判した知識人は厳しく罰せられたのである。
たとえば、排他的な愛国主義を厳しく批判した哲学者のソロヴィヨフは公職から追放されていることを指摘した赤尾光春氏は、ポベドノースツェフと新皇帝との私信では、ソロヴィヨフが「狂人」と呼ばれていたことにも言及している(「帝政末期におけるロシア人作家のユダヤ人擁護活動」『ロシア語ロシア文学研究三九』、2007)。つまり、ニコライ一世の頃に雑誌でカトリック的な見解を堂々と発表したチャアダーエフは、公式に「狂人」と宣告されたが、ユダヤ人を養護したソロヴィヨフも同じように見られていたのである。
そしてそれは迫害されたプロテスタント系のドゥホボール教徒のために『復活』を書いて彼らの移住を助けるなどの活動をして、一九〇一年に正教会から破門されることになるトルストイの場合にも当てはまる。これらの事例は、『死の家の記録』では、真理を求めるためには罰されることも恐れない勇気を持つ者として好意的に描かれていた旧教徒が、『カラマーゾフの兄弟』ではロシアがフランスに占領された方がよかったと語る去勢派の若者スメルジャコフに焦点が当てられていることとも関わっているだろう。
つまり、これらの記述はロシア正教以外の宗教や異端とされた旧教徒に対して、自分が共感を持っていると権力者に思われることを、ドストエフスキーがいかに恐れたかを物語っているように思えるのである。これらのシーンを描きながら、ドストエフスキーが自分の作品の「愛読者」であるポベドノースツェフの反応を気にしていたことはたしかであろう。(ここではポベドノースツェフ宛のドストエフスキーの手紙などを紹介することで、具体的に論証する誌面的な余裕がないので、いずれ稿を改めて考察したい)。
マサリクはモノローグの形で書かれた『作家の日記』の最後の号(1881年1月)においてドストエフスキーが、皇帝はロシアという「民族的有機体において、自分の子供たちの父親であるという、公けに重んじられる古い家父長理論」を展開していると指摘している(Ⅲ・140)。事実、ドストエフスキーが亡くなる直前に皇太子アレクサンドルとの面会の機会をも与えていたポベドノースツェフは、ドストエフスキーの死後に発行されたこの号を、「この号の各頁がすばらしい」と絶賛して皇太子アレクサンドルに送っている。
さらに、歴史家の和田春樹氏によれば、ポベドノースツェフが「私には彼は大の友人」であるが、「彼の死はロシアにとって大きな損失です」との手紙を皇太子に書いて、遺族に対する援助へのとりなしを頼み、その結果、ドストエフスキー夫人には、将軍の年金額に等しい二〇〇〇ルーブルの年金を支給することが決定した(『テロルと改革――アレクサンドル二世暗殺前後』山川出版社、2005、195-6)。
こうして、比喩的に言うならば、一介の作家に過ぎなかったドストエフスキーは、ポベドノースツェフによって、国家のために英雄的な死を遂げた「軍神」的な位置を与えられたとのである。そして、アレクサンドル二世が暗殺された後では、ポベドノースツェフは新帝となったアレクサンドル三世に「専制を不動のものとして維持する」旨の詔書を出すように何度も働きかけて成功することになる。
六、皇帝暗殺の「謎」とアジアへの進出政策
「みずからの敵を恐怖に陥れるための政治の道具としてのテロリズム、その歴史はそう古いものではなく、たかだか百四十年の歴史をもつに過ぎません」と断じた亀山氏は「その悲劇的ともいうべき最初の銃声は、ロシアで鳴り響き、世界にその恐ろしい威力を知らしめたのでした」と続けている(下・166)。
しかし、よく知られているように、皇帝の暗殺はこれがはじめての事件ではなく、司馬遷が『史記』の「刺客列伝」で描いたように秦の始皇帝の暗殺を試みた荊軻(けいか)をはじめとして、絶対的な権力を握り批判を許さなかった皇帝暗殺の試みは、古代中国の時代からえんえんと続いていたのである。
一方、ドストエフスキーの死の謎をも視野に入れつつ、皇帝暗殺の謎に迫ったラジンスキーは、アレクサンドル二世が「憲法」を制定しようとしていたことから、「極端な保守勢力」にとっては、「あらゆる力を皇帝暗殺に集中するという『人民の意志』の考え方は、彼らにとって非常に都合のよいものだった」とした。そして、かつての第三部副長官で皇太子の親友のチェレーヴィン侍従将官が後に、「彼(アレクサンドル二世)が排除されたのはよいことと言いたい。もしそうしなければ、彼が己の自由主義でロシアをどんなにひどい状態に陥れていたか、わかったものではないからである」と語ったと記している(望月哲男、久野康彦訳『アレクサンドル二世暗殺』下巻、NHK出版、2007、336-8)。
こうして、「臣民の義務と良心に従って」、「ヨーロッパに存在している憲法は、あらゆる虚偽の道具であり、あらゆる陰謀の道具となっている」と語った激烈なポベドノースツェフの演説によって、「偉大な改革、すなわち、憲法にいたる道は終止符を打たれ」、「皇帝の広い背中の背後からロシアを支配し始めた」ポベドノースツェフによってもたらされたのは、「厳しい検閲から、国家による反ユダヤ主義にいたるまで、ありとあらゆる手を駆使した国粋主義的な陣営の大勝利」だったのである(『アレクサンドル二世暗殺』381-2)。
そしてマサリクも、「愛想の良い社交と魅力的な作法が賞讃」されていたポベドノースツェフが、「黒百人組」の指導者たちの同盟者だったばかりでなく、反革命的秘密結社である「神聖親兵」を組織して、「あらゆる手段を用いて――殺人によってでも――王冠の敵を根絶しようとした」と批判している(Ⅰ・341)。
このように見てくる時、『父殺しの文学』では皇帝暗殺という大事件にいたるまでのさまざまの事件については詳しく紹介されていながら、優遇された貴族階級の下で貧困にあえぐ民衆や、ロシア帝国を根底から揺るがした戦争によるポーランドやフィンランドなどの属国化と反乱などの記述はほとんどなく、皇帝暗殺の謎にも迫っていないことに気づく。
亀山郁夫氏の近著『大審問官スターリン』を論じた歴史家の塩川伸明氏は、そこには「個々の歴史的事実に関する明らかに間違った記述も少なくない」ことを指摘しながら、「歴史」と「神話」を組み合わすという亀山氏の語り口を「読者を惑わし兼ねない」という危惧の念を記している(『ロシア語ロシア文学研究・三九』)。
実は、亀山氏の『父殺しの文学』を読んだときの私の感想もほとんどそれに重なるもので、ドストエフスキーについての「新たな神話」が大胆な切り口で語られている本書は、ことに若い読者を「自国中心的な」古い歴史認識へと導いてしまう危険性を強く感じたのである。
たとえば、『死の家の記録』ではロシア政府に対抗して戦ったイスラム教徒が温かさをもって描かれていたが、『カラマーゾフの兄弟』では「妊婦の腹から胎児をえぐり出す」トルコ人や赤ん坊をあやした後でピストルで撃ち殺してしまうなどのブルガリアにおけるトルコ人の残虐がイワンによって語られている。これらのエピソードはドストエフスキーがこれらの病的な事柄からも目を背けずに描いているということだけではなく、イスラム教徒の残虐性を強調することで、ロシアが「正義の戦争」として行った露土戦争の正当性を、一般読者に主張しているという面も強くあると思える。
しかし、イスラム教徒に対する十字軍の実態については、日本ではあまり知られていないが、一九九四年にイギリスの国営放送であるBBCが「リチャード獅子心王はならず者であった」と題したドキュメンタリーで放映したように、「正義の戦争」とされてきたこの戦争が、実際には利権を確保するための嘘と欺瞞に満ちたものであり、それがジハード(聖戦)と呼ばれるイスラム教徒の激しい抵抗を生み出していたのである。
一方、『罪と罰』における「ナポレオン主義による金貸し老婆殺人をテロルとみるなら、その殺人のもつ意味は一気に歴史的な広がりを帯びるはず」と書いた亀山氏は(上・229)、「アレクサンドル二世はロシアのテロリストたちによって、今日でいう自爆テロに近いかたち」で暗殺されたと現代に引き寄せて記している(下・166)。
このような亀山氏の記述は、「スラヴ主義」の時期のドストエフスキーの歴史認識に重なるだけでなく、イラクを「ならず者国家」と規定して国連の正式決議を経ずに戦争に踏み切ったブッシュ政権のやり方や、さらには原爆などの近代兵器による悲惨さの認識の上に軍事力による紛争の解決を禁じた「憲法」の規定に反して、戦場に自衛隊を派遣していた日本政府の政策をも正当化することになると思えるのである。
一方、皇帝の暗殺を契機として始まったポグロムの第一の波(1881-1864)では、出稼ぎ農民や日雇い労働者などの貧しいロシア人がユダヤ人を襲撃したが、「政府当局はこれを静観していたばかりでなく、〈ユダヤ人=搾取者〉説に乗って事件を反ユダヤ人政策強化のために十二分に利用した」(原暉之、「ポグロム」『ロシアを知る事典』平凡社)。
先に見た赤尾氏は、もしドストエフスキーがこのことを知ったらどのように対応しただろうかという疑問を呈しているが、『カラマーゾフの兄弟』の続編をも大胆に想像した亀山氏は、ドストエフスキーと皇帝アレクサンドル二世の死が「神話的世界」の終わりであるかのごとくに、彼らの死後の直後に起きた重大な国策の変更やこの事件についてはまったく言及していない。
これに対して、ドストエフスキーが『作家の日記』の最終号で「我が国の将来の運命において、アジアこそ我々の主要な出口かもしれない」(Ⅲ・136)と記していたことに注意を促したマサリクは、皇太子ニコライが一八九〇年から翌年にかけて東アジアを旅行した時の公式の旅行記録者に、「アジアのすべての民族は、白きツァーリの支配を喜んで受け入れるだろう」とする汎アジア主義的な綱領を宣言させていたことに注意を促している(Ⅰ・133)。
しかも、「体制護持」の思想を詳しく分析した池庄司敬信氏によれば、ロシアの領土を拡張してさまざまな地域の「ロシア化」を進めるべきだと主張したスラヴ主義者のポゴージン(1800-1875)は、ロシアの皇帝を「ビルマ人、シナ人、日本人の王位」につけることで、これらの地域の民衆も幸せになると記していた(『ロシア体制変革と護持の思想史』中央大学出版部、526)。
実際、アジアへの進出を試みたアレクサンドル三世のもとで、一八九一年に始まったシベリア横断鉄道の建設は、一八九七年には一部区間をのぞきほとんどが完成することになる。そして、このようなロシア帝国の南下政策はマサリクが書いているように、「用心深い島国のエネルギー」を解き放ち、一九〇四年にはついに日露戦争が始まることになるのである。
この戦争が始まるとトルストイは平和を希求する宗教を信じるキリスト教徒と仏教徒のロシア人と日本人が戦場で戦うことの非を鋭く批判する論文を発表した。『アンナ・カレーニナ』において主人公に反戦的な言葉を語らせたトルストイを『作家の日記』で厳しく批判し、さらにコンスタンチノープルの領有も主張していたドストエフスキーが、もしこの年まで生存していたら、どのように反応しただろうか。
この意味で興味深いのは、「満州で敗北したのはロシアの兵士ではなく、ロシアの軍事行政、ロシアの参謀本部、ペテルブルグの宮廷とその外交、ロシアの官僚、一言で言えばポベドノースツェフの全体制だった」としたマサリクが、「ロシアは東アジアの地で、自らの内的な、最も内的な敵によって――日本人によってではなく――打ち負かされたのである」と結んでいたことである(Ⅰ・133-4)。
実は、このようなマサリクの結論は、日露の近代化の比較を通して日露戦争を詳細に分析した司馬遼太郎が、『坂の上の雲』の第六巻で「ロシア帝国は日本に負けたというよりみずからの悪体制にみずからが負けた」と記した考察とも重なる。そして司馬は、日本が日露戦争の勝利後にこのことをきちんと分析せずに、「憲法」の重要性をないがしろにして、軍人や政治家の横暴を防ぐような方策を取らなかったために、昭和初期の軍事国家へと突っ走ることになったことを明らかにしているのである(高橋『司馬遼太郎の平和観――「坂の上の雲」を読み直す』東海大学教育研究所、2005)。
このように見てくるとき、ファウストがメフィストフェレスとの契約によって永遠の若さを得たように、ドストエフスキーも権力者ポベドノースツェフに対する「二枚舌」を用いることにより、検閲の重みからある程度自由を得て、自分の才能を思う存分に活かして壮大なドラマを展開したといえるだろう。ことに「虚構」の上に成立するきわめてすぐれた文学作品である『カラマーゾフの兄弟』では「父親殺し」や「自殺」などの現代的な問題を鋭く描き出す一方で、ゾシマ長老の深い他者観や自然観を描くことで、読者に深い感動を与えた。
しかし、『カラマーゾフの兄弟』におけるグリボエードフを悪魔に揶揄させる表現やトルコ人の残虐さ記述などからは、熱心な読者でもあったポベドノースツェフに「媚び」るための「二枚舌」的な表現が感じられる。『作家の日記』の記述が作家の死後にポベドノースツェフたち保守的な政治家によって利用された可能性も否定できないだろう。
つまり、ドストエフスキーはスペシネフを自分のメフィストフェレスと見なしていたが、ドストエフスキー自身は認識することはできなかったが、彼の死後にも影響力を持ったポベドノースツェフもまたドストエフスキーのメフィストフェレスともいえる存在だったと思える。
「スラヴ主義」の時期に書かれた作品の「二枚舌」的な表現に注意を払わないで読むとき、私たちもまた「正教・専制・国民性」を「ロシアの伝統」として強調し、「憲法」の要求を「犯罪」と断じたポベドノースツェフ的な歴史・道徳観に引き込まれる危険性があると言わねばならないだろう。(『ドストエーフスキイ広場』17号、2008年)

〔本稿は2008年1月26日に代々木区民会館で行われた第184回例会での発表による。なお、再掲に際しては基本的な骨格はそのままにし、文末の「のである」の一部削除など文体上の修正を行った。〕