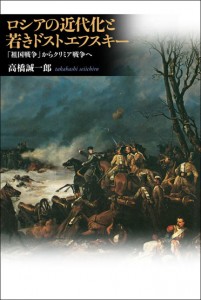拙稿では原爆パイロットをモデルとした堀田善衞の『#零から数えて』と『#審判』が『罪と罰』と『白痴』『悪霊』を踏まえて書かれていることを示し、
— 高橋誠一郎(絶望との対峙と克服『堀田善衞とドストエフスキー 大審問官の現代性』) (@stakaha5) November 24, 2021
『若き日の詩人たちの肖像』『ゴヤ』『路上の人』を「黙示録」を視野に入れて読み解くことで大審問官のテーマの現代性を明らかにしようとしました。 https://t.co/G27r1Na558 pic.twitter.com/V9qM7XY74r
高橋誠一郎 公式ホームページ
旧日本軍を批判しているように見えながら巧妙に読者を誘導して、「特攻」を美化する価値観へと導く『永遠の0』の危険な構造を分析する
映画《永遠の0(ゼロ)》を「神話の捏造」と厳しく批判した宮崎駿監督の
映画《紅の豚》の主人公 ポルコのセリフ「ファシストになるより豚の方がマシさ」
拙著の紹介が沖縄タイムズ、富山新聞、信濃毎日新聞、下野新聞、愛媛新聞に掲載
okinawatimes.co.jp/articles/-/881840…
「今年はドストエフスキー生誕200年。その文学の日本での受容を語る上で欠かせないのが堀田善衛である。終戦直前の東京大空襲と広島、長崎へ原爆投下という事態に出合って彼は、ドストエフスキーの現代的理解を深めていくからだ(…)」
〈新刊〉「堀田善衛とドストエフスキー」高橋誠一郎 著|文化|全国のニュース|富山新聞 (hokkoku.co.jp)
「堀田善衞の会」の例会で北陸にお伺いした際には、 生誕100年記念特別展「堀田善衞――世界の水平線を見つめて」が開かれた「高志の国(こしのくに)文学館」や「徳田秋聲記念館」など多くの文学館でお世話になりました。
拙著の紹介が12月19日の信濃毎日新聞、下野新聞、愛媛新聞にも掲載され、記事の後半では「黙示録的時代と向き合った2人の作家の共鳴の軌跡を追う」と、拙著の『審判』論が的確に紹介されていたことが判明しました。 (1月11日)
ドストエーフスキイの会、256回例会(報告者:国松夏紀氏)の延期のお知らせ
(再掲)下記の予定のところ、コロナビールス蔓延予防策の影響で、目下、延期、期日未定となりました。
以下にその要旨と「ドストエーフスキイの会」のホームページのアドレスを掲載します。
* *
下記の要領で例会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。
日 時:2020年3月28日(土)午後2時~5時
場 所:早稲田大学文学部戸山キャンパス31号館2階205室A
(最寄り駅は地下鉄東西線「早稲田」)
報告者:国松夏紀 氏
題 目: 『カラマーゾフの兄弟』における「寛容」を巡って
―― В. А. トゥニマーノフ氏追悼に寄せて ―
一般参加者歓迎・会場費無料
報告者紹介 : 国松夏紀(くにまつ なつき)氏
1947年久留米生まれ。早大露文・大学院、助手を経て桃山学院大学(名誉教授)。
[特別講演要旨]ドストエフスキー『悪霊』から削除された/入らなかった1章
“У Тихона”(「スタヴローギンの告白」)を巡って
(日本ロシア文学会関西支部会報2018/2019 №2)。
「昭和九年のドストエフスキー」に寄せて
(ロシア・ソヴェート文学研究会「むうざ」第32号2020年)。
(以下略、 2020年3月5日)
ドストエーフスキイの会、255回例会(報告者:杉里直人氏)のご案内
「第255回例会のご案内」を「ニュースレター」(No.156)より転載します。
* * *
第255回例会のご案内
下記の要領で例会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。
会場変更にご注意ください !
日 時:2020年1月25日(土)午後2時~5時
場 所:早稲田大学文学部戸山キャンパス31号館2階208教室
(最寄り駅は地下鉄東西線「早稲田」)
報告者:杉里直人 氏
題 目: 『カラマーゾフの兄弟』を翻訳して
会場費無料
報告者紹介:杉里直人(すぎさと なおと)
1956年生まれ。早稲田大学、明治大学、東京理科大学非常勤講師。2007年に旧マヤコフスキー学院の受講生とともに『カラマーゾフの兄弟』の輪読会を始め、2016年に読了。現在は新しい仲間も加わり、5年計画で『悪霊』を読んでいる。主要訳書:バフチン『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』(水声社、2007年)。
* * *
第255回例会報告要旨
『カラマーゾフの兄弟』を翻訳して
2020年1月に水声社より杉里訳『カラマーゾフの兄弟』が刊行される。1914年に二浦関造の手で初めて邦訳されてから106年、拙訳は16番目の日本語訳になる。
私は今回、第一に原文を一語一語、忠実に訳すこと、そのうえで平明な訳文の作成をめざした。とはいえ、『カラマーゾフ』は概して一文が長く、構文はねじくれていて、会話は高度のmodalityに富んでいるので、「原文に忠実」と「平明な訳文」の両立は容易ではない。難所にぶつかるたびに、そして無知や思いこみに起因する錯誤を回避するために、座右に置いた13の先行訳を参照した。拙訳には既訳に異を唱え、新しい解釈を提示する箇所がいくつかあるが、それは先人との時空を超えた対話を通してなされた。利用した8つの日本語訳のうち、語学的に正確で、周到に考えぬかれた原卓也の丹念な訳業、巧みな語り口、豊富な語彙、こなれた訳文という点で抜きんでた江川卓の仕事からは学ぶ点が多かった。5つの英・仏・独訳のうち、とくに2つの英訳(Pevear&VolokhonskyとMcDuff)は、日本語訳を批評的に対象化して、異なる見地から再検討し、代々の誤訳を洗い直すために有益だった。
翻訳作業では露和辞典に依存せず、常時複数の露々辞典を引くよう心がけた。主に利用したのは、ダーリ辞典(作家と同時代に編纂)、新アカデミー辞典(現在25巻まで既刊)、旧アカデミー17巻辞典、ウシャコフ辞典、ドストエフスキー語彙辞典、ミヘリソン表現辞典、19世紀刊行の方言辞典などである。ドストエフスキーを読む際、不可欠なのはダーリと新旧アカデミー辞典で、これらを徹底的に読みこめば、誤訳を確実に正すことができる。
拙訳のもう一つの特徴は詳細な注釈である(A5版190頁、1264項目)。140年前に異国で発表された古典作品を深く的確に理解するためには、目配りがよく偏りのない注釈が必須だ。ところが、従来の邦訳のうち、注釈の名に値するものを具備しているのは江川卓訳だけだった。これはナウカ版全集のヴェトロフスカヤによる画期的注釈(1976)に依拠しつつ、江川独自の研究を盛りこんだ労作である。これが成ったのは1979年で、その後40年が経過し、作品研究は長足の進歩をとげた。ヴェトロフスカヤは『カラマーゾフ』関連の単著や論文を集成し、2007年に600頁を超える大著としてまとめ、注釈部分(209頁)も最新の知見を反映させて大幅に増補・改訂した。拙訳の訳注ではヴェトロフスカヤ、江川のほかに、グロスマン(1958)、Terras(1981)の注釈も適宜利用した。
司法、教育などの社会制度、衣服、食事などの習俗、宗教儀礼、文化、自然といった、いわゆるレアリアについてはできるだけ具体的に解説した。ロシア人にとって自明で、注釈が不要な事柄でも、外国人読者にはなじみのない事象が数多くある。それらにはブロックハウス=エフロン百科を始めとする各種事典類を頼りに、独自の注釈を施した。聖書関連ではコンコーダンスをフルに利用した。新規の試みとして絵画などの視覚情報を別丁で掲載した。
『カラマーゾフ』は《引用の織物》と言ってよいほど、古今のテクストが引用され、原著に対する顕在的・潜在的な論争、パロディ、もじり、嘲笑に満ちている。この点も可能なかぎり原典にあたって調査し、作品の読解に益する場合には注釈を付した。従来日本では言語遊戯、新造語・古語・外来語の使用など言葉の芸術家としてのドストエフスキーに関心が向けられることは少なかったが、作家は最後の長編で細部の彫琢に腐心し、さまざまな意匠を凝らしている。注釈では真に驚嘆すべきこの側面にも照明を当てることをめざした。
一連の作業のために作成したノートは最終的に29冊になった。このノートがなければ、私は『カラマーゾフ』の翻訳などという身のほど知らずの蛮行を企てなかっただろう。本例会では、なるべく多くの具体例をあげながら報告する。いくつかの新発見についてもお伝えできればと思っている。
* * *
合評会の「傍聴記」や「事務局便り」などは、「ドストエーフスキイの会」のHP(http://www.ne.jp/asahi/dost/jds)でご確認ください。
ロシア帝国の教育制度と日本――『ロシアの近代化と若きドストエフスキー』から『「罪と罰」の受容と「立憲主義」の危機』へ
ニコライ一世治下の帝政ロシアでは、ロシアの貴族にも影響力をもち始めていた「自由・平等・友愛」という理念に対抗するために、「正教・専制・国民性」の「三位一体」を「ロシアの理念」として国民に徹底しようとした「ウヴァーロフの通達」が1833年に出されていました。
このような時代に青春を過ごした若きドストエフスキーは初期作品で、権力者の横暴を抑えるための「憲法」の意義や言論や出版の自由の必要性、さらには金持ちのみを優遇する「格差社会」の危険性などを、「イソップの言葉」で説いていました。
『貧しき人々』に始まるこれらの作品を分析することにより、日本における「憲法」や「教育」の問題を考察しようとした拙著『ロシアの近代化と若きドストエフスキー 「祖国戦争」からクリミア戦争へ』(成文社、2007年)の終章では、検閲の問題と芥川龍之介の自殺との関連にも注意を払いながら、『白夜』からの引用がある堀田善衞の『若き日の詩人たちの肖像』に注目することで、昭和初期の日本の状況とクリミア戦争直前の帝政ロシアの状況との類似性を明らかにしました。
たとえば、昭和一二年に文部省から発行された『国体の本義』では、大正デモクラシーを想定しながら、その後も「欧米文化輸入の勢いは依然として盛んで」、「今日我等の当面する如き思想上・社会上の混乱を惹起」したとして、これらの混乱を収めるべき原則として『教育勅語』の意義が強調されたのです。
さらに『国体の本義解説叢書』の一冊として文部省教学局が発行した『我が風土・国民性と文学』と題する小冊子では、「ロシアの理念を強調した「ウヴァーロフの通達」と同じように、「日本の国体」においては、「敬神・忠君・愛国の三精神が一になっている」ことを強調していました。
それゆえ、『ロシアの近代化と若きドストエフスキー』を書き上げた後では、芥川龍之介の自殺の問題も描かれている堀田善衞の『若き日の詩人たちの肖像』を詳しく考察することで、昭和初期に書いた「『罪と罰』についてⅠ」などの評論や『我が闘争』の書評で当時の若者や知識人に強い影響を与えていた小林秀雄のドストエフスキー論の問題点を明らかにしたいと考えました。
しかし、幕末だけでなく昭和初期に再び強い勢力を持つようになっていた平田篤胤の「復古神道」について理解が乏しかったために、その構想は先延ばししなければなりませんでした。
ようやく前著『「罪と罰」の受容と「立憲主義」の危機――北村透谷から島崎藤村へ』で、明治の文学者たちの視点で差別や法制度の問題、「弱肉強食の思想」と「超人思想」などの危険性を描いていた『罪と罰』の現代性に迫りました。さらに、『罪と罰』の人物体系や内容を詳しく研究することで長編小説『破戒』を書いただけでなく、『夜明け前』では平田篤胤没後の門人となって古代復帰を夢見た主人公の破滅にいたる過程を描いた島崎藤村の作品を分析することにより、明治政府の宗教政策や昭和初期の「復古神道」の問題をも考察することができました。
こうして、芥川龍之介の自殺と堀田善衞の『若き日の詩人たちの肖像』との関連を論じることのできる地点までようやく来ましたので、次の著書『堀田善衞と小林秀雄――「若き日の詩人たちの肖像」を読み解く』(仮題)ではこの問題を正面から論じることにします。
→*新刊 『堀田善衞とドストエフスキー 大審問官の現代性』(群像社、2021年)
そのためにも、徳富蘇峰の「教育改革」論の後で生じた事態を、芥川龍之介の自殺と堀田善衞の『若き日の詩人たちの肖像』との関連をとおして考察した箇所を、拙著『ロシアの近代化と若きドストエフスキー 「祖国戦争」からクリミア戦争へ』から、「主な研究」に転載することにより確認することにします。(引用に際してはわかりやすいように、一部改訂を行いました。)
→芥川龍之介の自殺と『若き日の詩人たちの肖像』――『ロシアの近代化と若きドストエフスキー』終章より
(2023/02/02、新刊 『堀田善衞とドストエフスキー』とツイターへのリンク先を追加)
ドストエーフスキイの会、254回例会(報告者:高柳聡子氏)のご案内
「第254回例会のご案内」を「ニュースレター」(No.155)より転載します。
* * *
第254回例会のご案内
下記の要領で例会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。
会場変更にご注意ください !
日 時:2019年11月16日(土)午後2時~5時
場 所:早稲田大学文学部戸山キャンパス32号館2階228教室
(最寄り駅は地下鉄丸ノ内線「早稲田」)
報告者:高柳 聡子 氏
題 目: タチヤーナ・ゴーリチェヴァの思想におけるドストエフスキイ
会場費無料
報告者紹介:高柳 聡子(たかやなぎ さとこ)
早稲田大学、東京外国語大学、専修大学非常勤講師。専門はロシア文学、おもに現代女性文学、フェミニズム史、女性誌研究など。著書に『ロシアの女性誌 時代を映す女たち』(群像社、2018年)、訳書に『集中治療室の手紙』(イリヤー・チラーキ著、群像社、2019年)他。
* * *
第254回例会報告要旨
タチヤーナ・ゴーリチェヴァの思想におけるドストエフスキイ
「ドストエフスキイは希望の作家である。このことは、希望のための場所が残されていないかのように見える現代では、とりわけ重要だ。20世紀は、いくつものユートピアが生まれ、その正体が暴かれるという百年だった。あらゆるイデオロギーが暴かれていった。現代の知識人たちは、不可能なものを求めるリスクを、もはや負おうとはしない」(タチヤーナ・ゴーリチェヴァ『聖なる狂気について 現代世界のキリスト教 О священном безумии. Христианство в современном мире』2015年、503頁)。
宗教哲学者タチヤーナ・ミハイロヴナ・ゴーリチェヴァТатьяна Михайловна Горичева(1947-)は、レニングラードに生まれ、ドイツ語の技術翻訳を学んだ後にレニングラード大学哲学科に進み、ドイツやフランスの現代思想をほぼ独学で学びました。1974年にモスクワで開催された世界ヘーゲル学会をきっかけに、晩年のハイデッガーと文通をしていたことでも知られています。
また、1960年代には、夫で詩人のヴィクトル・クリヴーリン(1944-2001)とともに、文学や宗教学のセミナールを開催し、サミズダートで雑誌『37』を発行、二人の住まいはレニングラードの非公式文化の中心のひとつとなっていました。ゴーリチェヴァの名は、この「第二の文化」と呼ばれる非公式芸術の担い手のひとりとして、そしてソ連時代唯一のフェミニズム運動のリーダーとして語られてきました。
彼女は、1979年に、詩人のユーリヤ・ヴォズネセンスカヤらと、やはりサミズダートでフェミニズム雑誌『女性とロシア』を、その後『マリア』を発行します。これは、ロシアの女性たちが、正教思想に基づき、工場労働ではなく、神が与えた女性の役割に生きることを主張するもので、ソ連社会で仕事と家庭の二重負担に疲弊した女性たちの労働からの解放と信仰の自由を求める民主化運動となりますが、ただちに逮捕され国外追放になりました。
追放を機に、ドイツやフランスで神学や哲学を学びながら思想を深め、ソ連崩壊後は、ペテルブルクとパリを拠点にして、執筆や世界各地でのロシア正教についてのレクチャーを精力的に行ってきました。最近は、環境問題、とりわけ、動物保護運動に力を入れています。
半世紀以上にわたって、さまざまな活動を行ってきたゴーリチェヴァの思想の基盤となっているのは一貫して、神の教えです。そして、正教とロシアをめぐる彼女の言説には、ドストエフスキイへの非常に力強い信頼を見ることができます。
ゴーリチェヴァが、とりわけ強い関心をもって着目するのは、ドストエフスキイの主人公たちの多くが、ユロージヴイか、あるいはユロージヴイ的な人物である点です。彼女は、ユロージヴイ的な人物をいくつかの種類に分けて考察していますが、そのなかでもっとも高い評価がくだされるのが、フョードル・カラマーゾフです。いったいなぜ彼が重要なのでしょうか?
さらに、おもに『地下室の手記』を取り上げながら、地下室(孤独・皮肉・苦悩)の人間のもつ聖性について指摘します。地下室の人が裸で叫ぶのは、「偽りの世界に対する偽りの庇護がない」からであり、これこそがユロージヴイの理想的な姿であると述べるのです。
こうした主張を展開する際、ルネ・ジラール(『ドストエフスキー:二重性から単一性へ』)やレフ・シェストフ(『悲劇の哲学 ドストエフスキーとニーチェ』)のドストエフスキイ論が引用され、共感が示されます。
ゴーリチェヴァのドストエフスキイ観は、全体的には新しいものとは言えませんが、フェミニズムやジェンダーの問題にまで言及している今現在の思想家が、ドストエフスキイを介して、伝統的なロシア思想につながっていることを証明できる興味深い事象となっているのです。
今回の発表では、今のところ日本ではまったく知られていないゴーリチェヴァのドストエフスキイ論をご紹介したいと思います。ゴーリチェヴァの思想を通してドストエフスキイの現代性を見いだし、同時に、ドストエフスキイを通して、精神的な人間を称揚するゴーリチェヴァが伝統的なロシア思想史の延長線上にいることを明らかにしたいと考えています。
* * *
合評会の「傍聴記」や「事務局便り」などは、「ドストエーフスキイの会」のHP(http://www.ne.jp/asahi/dost/jds)でご確認ください。
堀田善衞と武田泰淳の『審判』とドストエフスキーの『罪と罰』
はじめに
一昨日、原爆パイロットを主人公とした堀田善衞の二つの作品を考察した研究ノート「狂人にされた原爆パイロット――堀田善衛の『零から数えて』と『審判』をめぐって」を「主な研究」に転載しました*1。
ここでは堀田百合子氏の『ただの文士 父、堀田善衞のこと』や『堀田善衞・上海日記』、そして、木下豊房氏の「武田泰淳とドストエフスキー」にも目を配ることで、堀田善衞と武田泰淳の『審判』との関係を考察したいと思います。そのことによって、『若き日の詩人たちの肖像』に記されている『白痴』論の意味にも迫ることができるでしょう。
1、堀田善衞と「あさって会」
堀田善衞も属していた「あさって会」がどのような会だったかは年譜などからは分からなかったのですが、堀田百合子氏は『ただの文士 父、堀田善衞のこと』で、子供の頃に行われていた「埴谷家のダンスパーティーが、その後の『あさって会(埴谷雄高・椎名麟三・梅崎春生・野間宏・武田泰淳・中村真一郎・堀田善衞)』の集いにつながっていったのだと思います」と書いています。
さらに、彼女は「戦後派と呼ばれる作家たちのこの集まりは、家族ぐるみの付き合いでもあり、文学をタテ、ヨコ、ナナメに、それぞれが勝手にしゃべり、それぞれの栄養にして」いったのですと記しており、この会の雰囲気が伝わってきます*2。
ことに武田泰淳氏とその家族とは「夏の蓼科、角間温泉、湯田中温泉。父と武田先生、母と百合子夫人、私と花さん。遊んでいました。しゃべっていました」と書いた百合子氏は「父には見た目も、物言いも、かなり鋭角的なところがありますが、武田先生は違いました。何もかもがまーるいのです。時間の回り方が違うのかなと思えるようなまるさでした。人を包み込むような優しさが、子供の私には心地よかったことを覚えています」と続けています*3。
2、武田泰淳と堀田善衞の上海
このような堀田と武田の深い交友を考えるとき、武田泰淳の『審判』(1947)と堀田善衞の『審判』(1963)との関りの深さが浮かび上がってきます。
すなわち、ドストエフスキー研究者の木下豊房氏は、埴谷雄高が1971年のエッセイで、「同時代者である私達はまぎれもなく同一問題を負わざるをえなくなったドストエフスキイ族であることが明らかになった」とのべ、椎名麟三、武田泰淳、野間宏の名をあげながら、特に、武田の小説『風媒花』で展開される現代の殺人論が「ドストエフスキイの深い殺人論の延長線上」にあることを指摘していたことに注意を促していました*4。
さらに1946年に帰国した直後に書かれた「『審判』(1947・4)、『秘密』(1947・6)、『蝮のすえ』(1947・8)」と武田の作品とドストエフスキーの『罪と罰』との深い関連を木下氏は詳しく考察しているのです。
堀田善衞が『文芸』の1955年12月号に載せたエッセイ「武田泰淳」において、上海では堀田が詩だけを書いていたのに対し、武田は「詩を書きながら、しきりと『罪と罰』のような小説が書ければ本望だ、と云って、世の狂燥をよそにして、漢訳の聖書を一生懸命に耽読していた」と記していることは武田の『罪と罰』への関心の深さを物語っているでしょう*5。
そして、堀田が「そのときの姿勢が、いつまでも僕の眼底にのこっている」と続けていたことからは、武田泰淳と堀田善衞の二つの『審判』の関係の深さが伺えます。
しかも、1976年に発行された雑誌『海』の「武田泰淳追悼特集」に収められた開高健との対談では、上海ではまだドストエフスキーの文学を知らなかった武田に堀田がシェストフやミドルトン・マリなどの「さまざまのドストエフスキー論について武田先生に講義しました」とも語っているのです*6。
3、堀田善衞の原爆のテーマと武田泰淳
原爆パイロットを主人公とした堀田善衞の『審判』のテーマも武田との交友が深く絡んでいました。
すなわち、武田泰淳の葬儀で弔辞を読んだ堀田は、上海にいたときに「原爆の影響によって、我が国民全部が亡びるというデマ」がまことしやかに伝えられていたことから、武田が「『かつて東方に国ありき』という詩をお書きになったことを、私は忘れません」と語って、原爆のテーマと上海の記憶にも注意を促していたのです*7。
この言葉の意味は重いでしょう。なぜならば、1970年5月に毎日新聞夕刊に書いた記事で、宇宙飛行について書いたメイラーの『月にともる火』について「なぜいったいどこかで広島について、長崎についての言及と考察がなされなかったのか。それなしではアポロもヘッタクレもあるものか、と私は思う。それを欠いていることについて、ノーマンなどという奴はつまらぬ奴だ、と私は思う」と記しているのです*8。
しかも、1990年8月6日にNHK教育テレビで放映された「NHKセミナー 現代ジャーナル 作家が語る自作への旅」で 堀田善衞は自作『審判』の主人公についてこう語っていました*9。
「広島で二十数万人を一挙に殺したということについての、それが一体罪であるのか、あるいはただの戦時行為なのであるか、という判定がつかないわけですがそういう人物を選んだわけです。その人物の容貌、相貌を、私はフランスの画家ルオーの自画像を見ていて思いついたわけです。日本へ行けば、あるいは最終的に広島へ行けば、そこで何らかの解決、あるいは審判というものを受けられるのではなかろうか。再生のための、もう一度生きるための道というものが、日本にあるのではなかろうか。そういうことを考えたわけなんです。」
この文章を紹介した堀田百合子氏は、『掘田善衛全集5』 の「著者あとがき」で堀田が武田泰淳に触れながら記していた文章も引用しています。
「筆者自身としても、この作品について何かを言うことは、現在でもある苦痛の感を伴うものがあった。(略)/なお、同じく『審判』と題された、故武田泰淳氏の傑作が別にあることを、付記しておきたい。『審判』という命題は、戦争を通過して来た戦後世代にとっては、避けては通れないものである」
こうして、木下氏の考察をも考慮するならば、原爆パイロットを主人公とした堀田善衞の『零から数えて』と『審判』は、武田のこれらの作品を踏まえた上で書かれているといっても過言ではないでしょう。
4、小林秀雄のドストエフスキー観の見直し
注目したいのは、『堀田善衞 上海日記』の冒頭に記されている1945年8月6日の記述で堀田善衞が、「頃日(注:けいじつ、この頃の意)ド〔ドストエフスキー〕氏の「白痴」を読みたしと思ふことしきり」と書いていることです。同じ年の10月13日の日記では、創元社から刊行された小林秀雄の『小説1』『小説2』とともに小林秀雄が1943年の9月に『文学界』で論じていたゼークトの『軍人の思想』を買い求めたと記されていることに注目するならば、この時期に堀田が『白痴』を通して小林秀雄の思想の見直しをしていることが感じられます*10。
なぜならば、小林秀雄は「天皇機関説」事件が起きる前年の1934年に書いた『白痴』論で、「ムイシュキンはスイスから還つたのではない、シベリヤから還つたのである」と解釈していましたが、堀田善衞はこの時期を描いた『若き日の詩人たちの肖像』で、「たとえ小説の中でも羽根をつけて飛んで来るわけには行かないから、天使は、(……)外国、すなわち外界から汽車にでも乗せて入って来ざるをえないのだ」と書いているからです*11。
これらの記述から堀田が『白痴』を通して小林秀雄の思想の見直しをしていると断ずることは強引のように見えるかもしれませんが、先ほど見た『堀田善衞 上海日記』に収められている開高健との対談での終わりの方で堀田は、こう語っていました*12。
「ぼくはほんの一年九カ月ぐらい上海にいただけですが、ものの考え方も感覚もひじょうに変ったと思うんですね。帰ってきて『批評』の同人会へ出ても、かれらが喋っていることがぜんぜん解りませんでね。(……)隣りに小林秀雄さんがいて、『堀田君、君は随分おとなしい人だね』と言ったけれども、おとなしいんじゃなくて、何言っているのか全然解らないんですよ。」
この言葉からは上海から戻った時に、堀田善衞が昭和の『文学界』や『日本浪曼派』の、「日本回帰」のイデオロギーから完全に解き放されていたと考えることができるでしょう。
こうして武田泰淳との関係も踏まえて、堀田善衞の自伝的な長編小説『若き日の詩人たちの肖像』の前に書かれた『零から数えて』と『審判』を読むと、いっそう興味と理解が深まると思われます。
注
*1 「狂人にされた原爆パイロット――堀田善衛の『零から数えて』と『審判』をめぐって」『世界文学』(127号)、2018年7月、101~107頁。→ホームページ 「狂人にされた原爆パイロット――堀田善衞の『零から数えて』と『審判』をめぐって」
*2 堀田百合子『ただの文士 父、堀田善衞のこと』岩波書店、2018年、22頁。
*3 同上、92頁
*4 木下豊房「武田泰淳とドストエフスキー」、(初出:「ドストエーフスキイ広場」№15.2006)
*5『堀田善衞全集』、第16巻、25頁。
*6 堀田善衞・開高健「対談 上海時代」、紅野謙介編『堀田善衞 上海日記――滬上天下(こじょうてんか)一九四五』集英社、2008年、394頁。
*7 堀田百合子、前掲書、94頁より引用。
*8『堀田善衞全集』、第14巻、309~310頁。
*9 堀田百合子、前掲書、45~46頁より引用。
*10 紅野謙介編『堀田善衞上海日記』、集英社、2008年、13頁、32頁。
*11 高橋誠一郎、「堀田善衞の『白痴』観――『若き日の詩人たちの肖像』をめぐって」『ドストエーフスキイ広場』第28号、2019年、121~127頁。→ホームページhttp://www.stakaha.com/?p=8515。なお、堀田善衞の『審判』とドストエフスキーの『悪霊』やセルバンテスの『ドン・キホーテ』との関連については、別の機会に譲ることにする。
*12 紅野謙介編『堀田善衞上海日記』、415~416頁。
「狂人にされた原爆パイロット――堀田善衛の『零から数えて』と『審判』をめぐって」を「主な研究」に転載
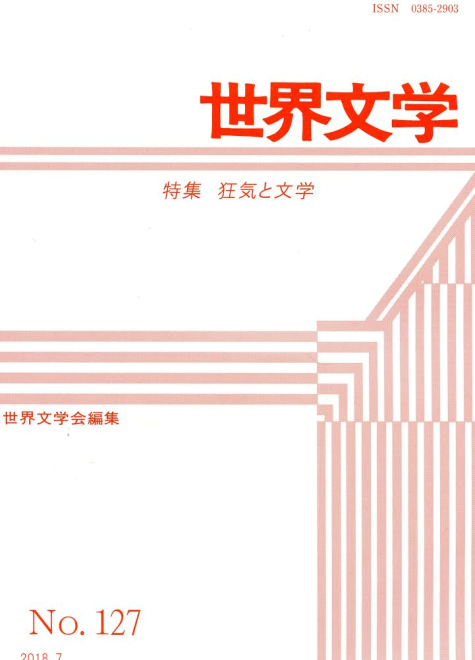
原爆パイロットを主人公とした堀田善衞(1918―1998年)の二つの作品については、「狂気と文学」が特集された『世界文学』(127号)に寄稿した研究ノートで、ドストエフスキーの『白痴』や『罪と罰』との関連で予備的な考察をしました。
その研究ノート「狂人にされた原爆パイロット――堀田善衛の『零から数えて』と『審判』をめぐって」を「主な研究」に転載します。
→狂人にされた原爆パイロット――堀田善衞の『零から数えて』と『審判』をめぐって
ただ、その際には堀田善衞と武田泰淳(1912年―1976年)の二つの『審判』との関係については言及できませんでしたので、それについては別稿で考察することにします。
→堀田善衞と武田泰淳の『審判』とドストエフスキーの『罪と罰』
「ドストエーフスキイのプーシキン観ーー共生の思想を求めて」を「主な研究」に転載
『ドストエーフスキイ広場』の創刊号に掲載された拙論「ドストエーフスキイのプーシキン観」についてのお問い合わせを頂きました。
その内容はすでにその後に執筆した拙著に組み込んでいると思っていましまたが、調べて見るとまだ完全な形では収録されていないことが分かりました。
1991年の古い論考ですが、『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』(刀水書房、初版1996年、新版2000年)から、『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』(成文社、2007年)を経て、近著『「罪と罰」の受容と「立憲主義」の危機――北村透谷から島崎藤村へ』に至る一連の拙著につながる私の問題意識が色濃く出ている論考です。
それゆえ、人名表記などはそのままの形で、ホームページの「主な研究」に転載することにしました(→ドストエーフスキイのプーシキン観――共生の思想を求めて)
以下に、この論考の「目次」を掲載しておきます。
* *
序章 「ねずみ」たちについて
第一章 社会正義を求めて ーーペトラシェーフスキイ事件まで
第一節 『貧しき人々』と『駅長』
第二節 「ネワ河の幻影」と『青銅の騎士』
第三節 「警告するもの」としての良心
第二章 殺すことについての考察 ーー良心の問題をめぐって
第一節 「良心」の「自己流の解釈」
第二節 『地下生活者の手記』と『その一発』
第三節 『罪と罰』と『スペードの女王』