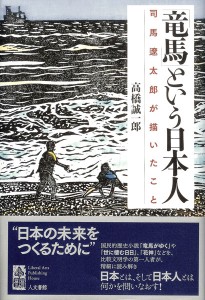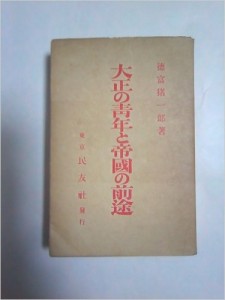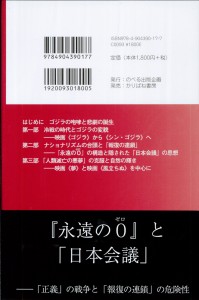「神国思想は明治になってからもなお脈々と生き続けて熊本で神風連(じんぷうれん)の騒ぎをおこし国定国史教科書の史観となり、…中略…その狂信的な流れは昭和になって、昭和維新を信ずる妄想グループにひきつがれ、ついに大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」(司馬遼太郎『竜馬がゆく』文春文庫、第3巻「勝海舟」より)。
* * *
安倍氏が国会で「わが党においては結党以来、強行採決をしようと考えたことはない」と答弁していたにもかかわらず、昨日、またも安倍政権によりTPP法案の強行採決が行われました。
このニュース報道を受けて、早速、「国民の健康も不安も無視する安倍政権の戦前的な価値観」とのコメントをツイッターに載せたのに続いて、下記の文章とその理由を説明した文を掲載しました。
「農業や医薬、ISDS条項など、国民の生命や安全を犠牲にしてTPPの国会成立を急ぐ安倍政権と自公両党。責任者の甘利元大臣の証言がなく、資料が黒塗りでは議論にならないのは明白。安倍氏に仕える自公の議員の姿は、律令制度の頃の官僚に似ている」。
〈なぜならば、明治維新で成立した薩長藩閥政府が理想視していたのは、律令時代の太政官制度でしたが、司馬氏の言葉を借りれば律令制度の頃の「公地公民」という用語の「公」とは「公家(くげ)」という概念に即したものであり、その制度も「京の公家(天皇とその血族官僚)が、『公田』に『公民』を縛りつけ、収穫を国衙経由で京へ送らせることによって成立していた」からです(司馬遼太郎、「潟のみち」より〉。
残念ながら、司馬氏の文明史家ともいえる広い視野は「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」などの論客による「褒め殺し」とも呼べるような一方的な解釈によって、いちじるしく矮小化され歪められてしまいました。
そのような解釈の顕著な例が、明治7年の台湾出兵や明治10年の西南戦争などで巨万の富を得て、三菱財閥を創業した政商・岩崎弥太郎を「語り手」としたNHKの《龍馬伝》(2010)でしょう。
安倍氏や「日本会議」などの論客からの強い要請によって放映されたと思われるこの大河ドラマは《龍馬伝》という題名に反して、「むしろ旗」を掲げて「尊王攘夷」というイデオロギーを叫んでいた幕末の宗教的な人々を情念的に美しく描いていたのです。
一方、司馬氏は『竜馬がゆく』の「勝海舟」の章で坂本竜馬についてこう記していました。
「たしかにこの宗教的攘夷論は幕末を動かしたエネルギーではあったが、しかし、ここに奇妙なことがある。/攘夷論者のなかには、そういう宗教色をもたない一群があった。長州の桂小五郎、薩摩の大久保一蔵(利通)、西郷吉之助、そして坂本竜馬である。」
そして、『竜馬がゆく』では当時の日本や世界の政治状況にもふれながら、勝海舟と出会った後の竜馬の視野の広がりと「文明論者」とも呼べるような思想の深まりが描かれていたのです。
それゆえ、ここでは拙著『「竜馬」という日本人――司馬遼太郎が描いたこと』(人文書館、2009年)より、「公地公民」制などについて考察した「”開墾百姓の子孫”」と題した第2節の一部(120~121頁)を引用することで、司馬氏の農政観の一端を記しておきます。
* * *
”古き世を打ち破る”
竜馬と庄屋の息子である中岡慎太郎との出会いを描いたこのシーンは、商才が強調されることの多い坂本竜馬の農民観を推測する上でも重要だろう。
すなわち竜馬が商人的な「利」の視点を持っていたことはよく知られているが、司馬は武士が「その家系を誇示する」時代にあって、竜馬に自分は「長岡藩才谷村の開墾百姓の子孫じゃ。土地をふやし金をふやし、郷士の株を買った。働き者の子孫よ」とも語らせているのである(四・「片袖」)。
ここで竜馬が自分を「開墾百姓の子孫」と認識していることの意味はきわめて重いと思われる。なぜならば、「公地公民」という用語の「公とは明治以後の西洋輸入の概念の社会ということではなく、『公家(くげ)』という概念に即した公」であったことを明らかにした司馬が、鎌倉幕府成立の歴史的な意義を高く評価しているからである(「潟のみち」『信州佐久平みち、潟のみちほか』)*12。
すなわち、司馬によれば「公地公民」とは、「具体的には京の公家(天皇とその血族官僚)が、『公田』に『公民』を縛りつけ、収穫を国衙経由で京へ送らせることによって成立していた制度」だったのである。そして、このような境遇をきらい「関東などに流れて原野をひらき、農場主になった」者たちが、「自分たちの土地所有の権利を安定」させるために頼朝を押し立てて成立させたのが鎌倉幕府だったのである。
しかも『箱根の坂』(一九八二~三)ではさらに、「諸国を管理するのに守護や地頭を置いた」鎌倉幕府や室町幕府について、「個々の農民からいえば、かれが隷属している地頭との間のタテ関係しか持てなかった」と記した司馬は、主人公の北条早雲に「日本の支配層は支配層のためにのみ互いに争うのみで、農民(たみ)のために思った政治をなした者は一人もおりませぬ」とも語らせている(中・「富士が嶺」)*13。
それゆえ、司馬は応仁・文明の乱(一四六七~七七)によって、世が乱れ、農民(たみ)が苦しむのを見た早雲に、「わしは、坂を越えて小田原」に入り、「古き世を打ち破る」と語らせていた。そして、「単に坂といえば箱根峠のことである」と続けた司馬は、「年貢は、十(とお)のうち四」という低い税率の「伊豆方式」を発した早雲が、守護や地頭などの「中間搾取機構を廃した」ことの意義を強調したのである(下・「坂を越ゆ」)。
こうして、「農業経営の知識」が深く、「十二郷の百姓どもの百姓頭になり、この地を駿河では格別な地にしたい」と思った北条早雲が、「民政主義をかかげて」室町体制を打ちやぶったことを、「日本の社会史にとって」は、「革命とよんでもいい」と高く評価した司馬は、「江戸期に善政をしいたといわれる大名でも、小田原における北条氏にはおよばないという評価がある」と続けていた(下・「あとがき」)。
このような大地とのつながりを重視する農民的な視点は、商才にも富んでいた竜馬が、なぜ武力討幕の機運が高まった際に、武器を調達することで大儲けをすることができる絶好の機会である戦争を忌避して、「時勢」に逆らうことが自分の生命を脅かすことになることを知りつつも、幕府が自ら政権を朝廷に返上する「大政奉還」という和平案を提出したかのを理解するうえでも重要だろう。
* * *
なお、『箱根の坂』における農政問題に対する認識の深まりは、日露戦争をクライマックスとする長編小説『坂の上の雲』を書く中で、ロシアのコサックと日本の鎌倉武士とを比較しながら、専制国家・ロシアにおける「農奴制」の問題を考察した結果だと思えます。
上からの近代化を強行に推し進めた帝政ロシアは「富国強兵」には成功し、皇帝と一部の貴族は莫大な富を得ました。しかし、特権化した貴族や近代化のために増大した人頭税のために、人口の大部分を占め、それまでは自立していた農民は、権利を奪われ生活が貧しくなって「農奴」と呼ばれるような存在へと落ちぶれ、逃亡した農民の一部はコサックとなったのです。
それゆえ、『坂の上の雲』を書き終えた後で、司馬遼太郎氏は「私は、当時のロシア農民の場からロシア革命を大きく評価するものです」と書き、「帝政末期のロシアは、農奴にとってとても住めた国ではなかったのです」と続けていたのです(「ロシアの特異性について」『ロシアについてーー北方の原形』文春文庫)。
(2016年11月7日、青い字の箇所を追加)