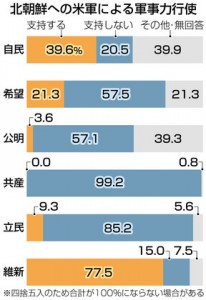(書影は「KINOKUNIYA WEB STORE」より)
(書影は「KINOKUNIYA WEB STORE」より)
序に代えて フーコーとドストエフスキー
私がフーコーを強く意識するようになったのは、『講座比較文明』第1巻の『比較文明学の理論と方法』に掲載された中川氏の「ヨーロッパ近代への危機意識の深化(2)――ニーチェとフーコー」を読んだときであった*1。
この論文の題名に(2)という番号が付いているのは、ドストエフスキーを中心にロシア思想史の流れを概観した私の論文「ドストエーフスキイの西欧文明観」が「ヨーロッパ近代への危機意識の深化」の(1)として置かれていたからである。
ただ、なぜ「ドストエフスキー」から「フーコー」なのか、私には当初その流れがよく理解できなかったが、フーコーは最初の著作『狂気の歴史』の冒頭でパスカルとドストエフスキーに触れてこう書いていた。
「パスカルによると、『人間が狂気じみているのは必然的であるので、狂気じみていないことも、別種の狂気の傾向からいうと、やはり狂気じみていることになるだろう』。またドストエフスキーには『作家の日記』のなかに、『隣人を監禁してみても、人間は自分がちゃんと良識をもっているという確信をもてない』という文章がある」。
そして、「非理性が理性の恥辱、その表向きの恥辱であることをやめるためには」、パスカルから2世紀後の「ドストエフスキーとニーチェまで」待たねばならないと第5章で記したフーコーは、「キリストは万人の目に自分が狂人――自らの托身によって、人間の失墜のあらゆる惨めさをたどる狂人――に見えることをも欲したのである」とも書いていた*2。
この文章を目にしたときに私は、若きドストエフスキーが兄ミハイルへの手紙で「私にはプランがあります。それは狂人になることです」と記していたことを思い出した。ドストエフスキーが「哲学に反対することは、それ自体哲学することです」とも書いていたことを想起するならば、フーコーの記述は検閲がきわめて厳しく「言論の自由」がほとんどなかった「暗黒の30年」と呼ばれる時代に青春を過ごしたドストエフスキーの小説の方法をも説明しているように思われる*3。
それゆえ、『狂気の歴史』を読んだ後では、この論文集の「総論」で「ヨーロッパ文明が唯一の文明と想定されるにいたった」19世紀の学的〈近代〉パラダイムを超える「新しい知の形成」の必要性を強調していた比較文明学会理事(当時)の神川正彦氏が、近代的な知の根源に迫ろうとしていたドストエフスキーとフーコーの作品の考察をも組み込むことで、「比較文明学という学的パラダイムの構築」を企画していたことに気づいた*4。
この論文集に掲載された「トインビーのルネサンス論をめぐる再検討」などを含む三宅正樹・明治大学名誉教授の『文明と時間』(東海大学出版会、2005年)についてはこの学会誌に書く機会を得た*5。今回はミシェル・フーコーの最初の著作『狂気の歴史』(1961年)から最晩年の『自己への配慮』(1984年)に至るまでの著作までが詳しく論じられている中川氏の『ミシェル・フーコーの思想的軌跡』が出版された。この著作からも強い知的刺激を受けたので、この機会に本書の内容をなるべく忠実に紹介しながら、比較文明学的な視点からドストエフスキーの作品にもふれつつフーコーの意義を考えてみたい。
1,フーコーの著作と「他者の思想」
「はじめに」でフーコーについて「哲学と歴史(そしてしばしば心理学や文学)を軸とした幅広い人文諸科学の領域において、実に多様な思想を展開した思想家であった」と記した著者は、彼の行った知的活動を次のように簡単に紹介している。
「精神医学、司法、監獄、言説(ディスクール)、権力、知、生-権力(バイオ・パワー)、性(セクシュアリテ)」など、「多様なテーマ・領域を貫く形で」、「『権力』と『知』の間の濃密な結びつき(すなわち『権力-知』」)の分析およびそれに対する批判的な論述を行った」。
その後で著者は本書の方法について、「フーコーのテクストを丹念に追いながら、彼が諸著作・諸論文において展開した『権力-知』についてのさまざまな批判的分析を、可能な限り一貫したやり方で」行うと明確に記している。
本書は以下の章から構成されている。
第1章 『狂気の歴史』と思考の可能性 ――フーコー・デリダ論争をめぐって
第2章 『言葉と物』における他者の思考について
第3章 『知の考古学』における言表/言説の実定性について
第4章 『知への意志』から『快楽の活用』へ――フーコーの「自己の倫理」の問題系と「権力-知」批判
第5章 ローマ帝政期における自己への配慮と批判的知の問題――古代倫理をめぐるミシェル・フーコーの比較研究について
第6章 ミシェル・フーコーの批判理論――いわゆる規範的問題をめぐって
第7章 ミシェル・フーコーの比較文明論――境界からの批判的思考の可能性について
『狂気の歴史』(正式な題名は『古典主義時代における狂気の歴史』)を扱った第1章では、この書でフーコーが「西洋近代理性が、非理性的存在(ここでは狂気)を自分自身にとって根本的な『他者』として同定し、それを分離・排除することで自らのアイデンティティーを確定してゆく有様を叙述」していることを明らかにしている。
そして、フーコーとデリダの論争を中心に考察しながら、「狂気」の問題は、「理解不可能な他者を前にして、思考がいったい何をなしえるのか、また何をなすべきか(あるいは何をなすべきでないか)という、倫理的問題に帰着する」とした著者は、フーコーが「デカルト的省察を西洋近代文明における理性の思考の代表であるとして、それ以外の思考の可能性を認め、また他者的要素の思考の内部への方途を模索しようとするのである」と書いている。
このような指摘は齋藤博・元東海大学文明学会会長が、「我思う、ゆえに我あり」を哲学の第一原理としたデカルト以降、近代西欧哲学では「世界観としての自我論的なパラダイム」が定着する中で、「他者」が「廃棄」されてしまったので、共存の問題を考える「文明理論の構築には、他者論の展開が不可欠の基礎作業である」と記していたことを想起させる*6。
著者にはすでに「他者」を主題とした共著があるが、フーコーの著作をとおして他者論の問題を深く考察したこの著書は、「文明理論の構築」を求めた重たい要請に答えるものでもあるといえるだろう*7。
本稿における私の関心は、フーコーの後期の著作『監視と処罰』(1975年)とドストエフスキーの『死の家の記録』との関係を中心に分析することで、「権力-知」と「他者」の問題がどのように深められているかを考察することにある。この意味で注目したいのは、「前期フーコーの方法論とされる『考古学』が、いかに後期フーコーの権力論の下地を形作り、準備するものであったのか」についても著者が詳しく検討していることである
フーコーの主著の一つとされる『言葉と物』(1966年)を論じた第2章では、古典主義時代(17・18世紀)の「表象作用によって人間に獲得された世界という記号群」が何よりも「同一性と差異性の原理に従って」、「『表』の形をした体系のうちに分配」され、「この時代の三つの大きな学問」である「一般文法」「博物学」「富の分析」もそれぞれの体系を完成することを目指していたと指摘している。
前期最後の著作として位置づけられる『知の考古学』(1969年)を論じた第3章では、この時期にフーコーが、「一貫した特徴・型・形式を抽出することの可能な独自のシステムを持つひとかたまりの総体、つまり社会や文化や文明といった、時間空間的に限定された大きな歴史的単位を分析するという基本姿勢をとっている」ことに注意を促した著者は、『知の考古学』が「各時代の支配的な知を構成する言表/言説の出現と、それにかかわる規則性の分析に主たる関心を払うこの時期のフーコーの、いわば理論的な総括となっている」と指摘している。
それとともに注目したいのは、第2章で「古典主義的な世界認識にあっては、たとえば博物学などに典型的に見られるように『自然のうちには連続性がある』と考えられなければならない」と分析していたフーコーが、第3章では「一九世紀の思考を規定している」「歴史的・時間的連続性」を指摘しているとし、「連続性の原理を基盤とする『同一者の思考』に対して、フーコーがひとつのアンチ・テーゼとしてこの『非連続性』の観点を提出しようとしていること」に著者が注意を促していることである。
2,「権力-知」の分析と「監視社会」の考察
論文「ニーチェ、系譜学、歴史」(1971年)には「フーコーの思想において中心的な役割を持つ『他者』『知』『批判』という三つの大きな概念を有機的に結びつける核心がある」と指摘した著者は、後期の方法論たる「系譜学」が、「ものごとの今現在の価値づけや意味づけを批判的に動揺・解体させようと試みるもの」であり、「『系譜学』は現在を批判するために、まさしく歴史を用いるのである」と記している。
そのような方法で書かれたのが1975年の『監視と処罰』であり、前期の諸著作にあっては「言表/言説の編制とそれを支配する規則性の分析にウエイトが置かれていた」ために、「具体的な社会的諸制度との関わりへの視点が比較的希薄であったが」、この著作は「一七世紀以来の近代西欧を全面的に覆う規律-訓練型権力システムの出現について」考察している。
では、『監視と処罰』においてはこの問題がどのように描かれているのだろうか。フーコーはロシアのエカテリーナⅡ世(在位1762~96)が、1767年に発布した『訓令』(ナカース)には死刑や体罰の廃止を強く求めたベッカリーアの『犯罪と刑罰』(1764年)の思想やモンテスキューなどの思想が盛り込まれ、実際にはあまり機能しなかったものの、理念的には法哲学の最新の成果が取り入れられていたことを指摘している*8。
この記述からは作家ドストエフスキーを生んだロシア帝国の法制度に対するフーコーの強い関心がうかがえるので、ドストエフスキーの場合と比較しながら具体的に見ていきたい。
農奴制の廃止や言論の自由などを求めたために1848年のペトラシェフスキー事件で逮捕され、死刑の宣告を受けた後に減刑されてシベリアの監獄に流刑になったドストエフスキーは『死の家の記録』において、肺病で死んでいく病人ですら足枷を外されなかったことに注意を促して、「足枷は――恥辱をあたえる一つの罰なのである。恥辱と苦痛、肉体と精神に加えられる罰なのである」と記している*9。
一方、監獄の考察をとおして鋭く「権力-知」の問題に迫ったフーコーも、囚人たちが足枷につながれて移送されることについて、「鉄鎖の一群の大がかりな光景(=見世物)は、身体刑の公開の古い伝統につながっていた」と指摘している*10。
興味深いのはドストエフスキーが「病院」が、「民衆をおびやかしているいちばん大きな理由」として、「ドイツ式の病院規則、病気のあいだじゅう見知らぬ人に取巻かれていなければならぬこと、食事のきびしい制限、衛生兵や医師のがんこなきびしさについての噂、死体の切開や解剖の話など」を挙げていることである。
ドストエフスキーは「病院」と題したこの章で、笞刑を行うことに慣れた刑吏の心理を分析して、「他者」の存在に対して、「もっとも残酷な方法で侮辱する権力と完全な可能性を一度経験した者は、もはや自分の意志とはかかわりなく感情を自制する力を失ってしまうのである」と指摘し、「暴虐は習慣である」と断言していた。
ドストエフスキーはさらに「刑吏の特性の芽は現代の人々のほとんどが持っている」と書き、「わたしが言いたいのは、どんなりっぱな人間でも習慣によって鈍化されると、野獣におとらぬまでに暴虐になれるものだということである。血と権力は人を酔わせる」と書き、「どんな工場主でも、どんな事業経営者でも、自分の労働者はときには家族ぐるみすっかり自分の思いどおりになるのだと考えて、一種のうずくような満足をおぼえるに相違ないのである」と続けている。ここには「権力」の危険性が鋭く指摘されているといえよう*11。
厳しい刑罰のことが詳しく描写されるこれらの章が「病院」と題され、病院や医師の考察がなされているのは一見奇妙に思われる。しかし、フーコーは近代における病院の役割が軍隊に続いて大きかったとし次のように記している。「病院、ついで学校、もっと後に工場は、単に規律・訓練によって《秩序化される》にとどまらなかったのであり、規律・訓練のおかげで、それらは、客体化のあらゆる機構がそこでは服従強制の道具という価値をもちうる、しかもそこでは権力のあらゆる増大が存在可能な知識を生み出す、そうした装置になった」*12。
このように見てくると、ドストエフスキーの監獄観とフーコーの監獄観がきわめて似ていることに気づくが、類似の一因は若い頃に「空想社会主義者」のフーリエから強い影響を受けていたドストエフスキーが、たとえ理想社会に見えようともプライヴァシーさえも完全に管理されるような社会の問題点を、シベリア流刑後に『地下室の手記』で鋭く指摘することになるためだろう*13。ベンサムを「治安本位の社会のいわばフーリエ」であると呼んだフーコーも、フーリエの提唱した理想社会の住居である「ファランステール(共同体住居)」を「〈一望監視施設〉の形式」をとっているようだとも記している*14。
フーコーの記述によって功利主義者のベンサムが考案した監獄の新しい建築様式「一望監視施設」を一瞥しておこう。それは「中心に塔を配して、塔には円周上にそれを取巻く建物の内側に面して大きい窓」をいくつも持ち、周囲の「円環状の建物」は、「独房に区分け」されており、「中央の塔のなかに監視人を一名配置して、各独房内には狂人なり病者なり受刑者なり労働者なり生徒なりをひとりずつ閉じ込めるだけで十分」な施設なのである。
つまり、フーコーの言葉を借りれば、「一望監視施設」は「見る=見られるという一対の事態を切離す機械仕掛であって、その円周状の建物の内部では人は完全に見られるが、けっして見るわけにはいかず、中央部の塔のなかからは人はいっさいを見るが、けっして見られはしないのである」*15。
こうして、技術が発展した近代においては「監視」の面でも、「権力を持つ」「少数者に、さらには唯一の者に、大多数の者の姿を即座に見させる」ことを可能としたことを指摘したフーコーは、ナポレオンを「過去の王権の簒奪者であると同時に新しい国家の組織者である君主」と位置づけ、ナポレオンこそが「統治権の君主的で祭式本位な行使」と「際限のない規律・訓練」との「接合点に位置する」と規定している*16。
この意味で注目したいのはドストエフスキーが長編小説『罪と罰』で、自分をナポレオンのような「英雄」であると見なし、「悪人」と決めつけた高利貸しの老婆の殺害を行った若き主人公の行動と苦悩をとおして、「自己」の絶対化の問題点をえぐり出していたことである。
『監視と処罰』では言及されていないが、権力者の元にすべての情報が集まるような仕組みの危険性は、核戦争後で3つの超大国によって分割統治されるようになった世界が描かれているジョージ・オーウェルの長編小説『1984年』(1949年)ですでに描かれていた。ことに「テレスクリーン」という双方向のテレビによって市民のほとんどの活動が監視されているという状況は、全体主義的な国家のみならず、現代の監視管理社会の問題をも先取りしていたといえよう。
ロシア文学との関わりで興味深いのは、革命後の1920年から21年にザミャーチンが書いた長編小説『われら』ではどんな個人的な会話も記録されることで個性を全く奪われるという未来の全体主義国家をすでに詳しく描いており、1924年に英訳されたこの作品は1949年に刊行されたオーウェルの小説にも影響を与えていたことである。
ザミャーチンが「この小説は人類をおびやかしている二重の危険――機械の異常に発達した力と国家の異常に発達した力――に対する警告である」と語っていたことを紹介した訳者の川端香男里氏は、「自然を圧殺する科学技術、産業文明、組織化される統治技術など」に向けられたザミャーチンの視野は、『カラマーゾフの兄弟』における「大審問官伝説」や『悪霊』のシガリョフの言葉とも深く関わっていると記している*17。
著者はフーコーがヨーロッパ社会を「監視文明」と呼んでいたことを紹介しているが、現代の世界ではインターネットの普及により情報の量は格段に増える一方で、米国家安全保障局による世界各国首脳の通話の盗聴が明るみに出るなど、「敵対国」だけでなく「友好国」相互でも「監視」が進んでいる。
その意味でも「監獄」の詳しい分析を通して「権力」と「他者」の問題に迫った『監視と処罰』の意義は大きいといえるだろう。
3,「自己への配慮」とフーコーの比較文明論的な視野
フーコーが死ぬ直前に発行された『快楽の活用』と『自己への配慮』が出版されると、「多くの失望」の声があがったと著者は記している。たしかに『監視と処罰』の後で、急に古代のギリシアやローマの倫理をめぐる比較研究という幾分古めかしいテーマを示されると腰が引ける感じがしていた。
しかし、「古代ギリシアにおける自己の倫理と『権力-知』の問題――ミシェル・フーコーの古代研究について」という題名で行われた第91回比較文明学会の例会での講演を聴いて驚いたのは、それが現代にも通じるきわめて新鮮な切り口であったことである*18。
本書でも著者は「フーコーはあくまでも考古学者として、古典古代という古層を発掘し、それをありのままに復元している」という批判に対して、「古典古代の自己・主体の倫理に関する」研究も、「あくまでも系譜学、しかも出来事が力の場で繰り広げられるダイナミックなあり様を分析しようとする批判的な系譜学の試みとして、受け取る必要がある」と主張している。
著者によれば、「中世キリスト教の修道的倫理とその自己認識を一貫して『自己放棄』を目指したもの」であると指摘したフーコーは、「ギリシア的自己認識」についても、その本質は「記憶や想起に基礎を置いて行われる『神的な要素としての自己の認知』である」と指摘していた。
一方、フーコーが例に挙げている「ローマ的な自己認識」は、「自己の不適正な言動や誤った行為に対して注意深く警戒・審査・査察の視線を注ぎ、絶えず試練のふるいにかけるような知の形式」であり、それは「自己に向けられた強力な『批判』的な視線であると言ってよい」と著者は記している。
興味深いのはセネカなどのストア哲学を好んだロシアの作家チェーホフが、友人の俳優にマルクス・アウレリウスの『自省録』を勧めて次のように語っていたことである。
「あなたが読みたがっておられるマルクス・アウレリウスを送ります。空欄に鉛筆で書き込みがありますが、気にしないでお読みください。続けて全部、お読みください――なぜなら全部、同じように素敵ですから。」
このことを記したロシア文学者の佐藤清郎氏は、19世紀末のロシアではセネカなどのストア哲学が、「多くの知識人の間でかなり広く読まれていたそうです」とも記している*19。
ストア派のセネカの著書『心の平静について』にも言及した著者は、「フーコーがしばしばローマ期の自己への配慮と医学・医術との類比に注目している」ことを指摘しているが、世紀末の混乱の時期を生きた作家のチェーホフが医師でもあったことを思い起こすと彼の言葉は「古典古代の自己・主体の倫理に関する」フーコーの哲学を考える上でも含蓄の深い言葉だと思える。
なぜならば、2001年の「同時多発テロ」を「新しい戦争」の勃発ととらえて「報復の権利」の行使としてアフガンへの空爆を行ったブッシュ政権は「悪の枢軸国」と名付けたイラクとの戦争にも踏み切っていたからである。しかし、「大量破壊兵器」が見つからなかったために、この戦争には「大義」がなかったことが明白になった*20。こうして、圧倒的な軍事力の差からアフガンのタリバン政権やイラクのフセイン政権は簡単に打倒されたが、それが中東情勢やアフガンの混乱、さらには「イスラム国」の問題とも直結しているように見える。
『比較文明学の理論と方法』に載せた論文で私は若い頃にフーリエの思想から強い影響を受けていたダニレフスキーがクリミア戦争(1853~56)によって激しく西欧文明に幻滅した後では、『ロシアとヨーロッパ――スラヴ世界のゲルマン・ローマ世界にたいする文化的政治的諸関係の概観』(1869)で、攻撃的な西欧から仕掛けられる戦争で亡ぼされないために「全スラヴ同盟」を作ることの必要性を説き、ドストエフスキーも『悪霊』や『作家の日記』を書いていた頃にはこのような考えから強い影響を受けていることを示唆した*21。
後期のドストエフスキーとダニレフスキーの文明論の問題点についてはいずれ稿を改めて考察することにしたいが、ここでは権力の奪取の方法を想定していなかったために批判されたフーリエの思想を、若きドストエフスキーが「悪意ある攻撃によってではなく、人類愛によって人を鼓舞する」と説明していたことを指摘しておきたい*22。
「権力-知」の問題をとおして他者の「理解可能性」を模索したフーコーの著作が、「思考のうちに『他者』を取り込んだ形で、『他者』とともに成立する新しい主体性の形式を目指そうとするものである」と著者は記している。最近はドストエフスキーの文学を「父殺しの文学」とスキャンダラスに捉えるような傾向も見られるが、ドストエフスキーは最後の長編小説『カラマーゾフの兄弟』で、「他者」を殺すことや自然との関わりの問題を哲学的な深さで展開していたのである。
「フーコーの一連の批判的な歴史分析の仕事は、具体的には西欧文明の『権力-知』をめぐる合理性の歴史を扱い、権力や力に貫かれた西欧文明の来歴を明らかにし、その実際の姿をあらためて認識すること」であったとした著者は、「自己の歴史こそが唯一の正当性を持つとの考えの否定は、自己とは異なる他者の歴史の存在、自己とは異なる別のあり方の再認識に私たちを導いてくれるのである」と続けている。
このようなフーコーの「他者」の認識は、比較文明学の創始者といわれるトインビーの見方にも通じるであろう。世界戦争を引き起こすにいたった近代西欧の「自国」中心の歴史観がはらむ危険性を深く認識したトインビーは、『フランス文明史』を書いたギゾーや『イギリス文明史』を書いたバックルが唱えた歴史観を大著『歴史の研究』において「自己中心の迷妄」と厳しく批判したのである*23。
「比較」という方法の重要性にも注意を喚起した著者は、「フーコーは力のシステムたる文明の現実/裏面を単に顕わにし、分析するだけではない。彼の仕事は、そうした文明の力のシステムを批判し、かつそれを変容させようとする強い動機に裏打ちされている」と書き、次のように結んでいる。
「過去と未来を同時に見据えようとするフーコーの『〈文明〉の批判理論』は、それ自体、そうした力の可能性のひとつを明らかにしてくれるものなのである」。
本書の書評で加藤泰氏は、フーコーが最初の著作で明らかにしたことは〈「狂気」をまえにした「理性」にとってのみならず、人類が「深い多元性」(コノリー)をもつ存在である限り根源的な意義をもつ〉と指摘するとともに、「フーコーを『文明』についての批判理論として明晰に理解する試みはこれまでほとんどなされたことはないのではないか」と結んで本書の意義を高く評価している*24。
博士論文をもとにした著作なので多少難解な点は残るが、哲学や歴史の研究者のみならず、文学や比較文明学をめざす若手の研究者にもぜひ読んでもらいたい書物である。
注
*1 中川久嗣「ヨーロッパ近代への危機意識の深化(2)――ニーチェとフーコー」、伊東俊太郎・梅棹忠夫・江上波夫監修『講座比較文明』第1巻、神川正彦・川窪啓資編『比較文明学の理論と方法』、朝倉書店、1999年、64~79頁。
*2 フーコー、田村俶訳『狂気の歴史――古典主義時代における』、新潮社、1975年、177~178頁。
*3 高橋『ロシアの近代化と若きドストエフスキー』、成文社、2007年、66~67頁。
*4 神川正彦「比較文明学という学的パラダイムの構築のために」、前掲書、『講座比較文明』第1巻、1~13頁。
*5 高橋、書評「三宅正樹著『文明と時間』」、『文明研究』、第31号、2012年。
*6 齋藤博「他者のトポロジー」、『文明』、第39号、1983年、20頁
*7 中川久嗣・石浜弘道・浅見聡『他者の風景──自己から関係世界へ』、批評社、1990年。
*8 フーコー、田村俶訳『監獄の誕生――監視と処罰』、新潮社、1977年、121頁。
*9 ドストエフスキー、工藤精一郎訳『死の家の記録』、『ドストエフスキー全集』第5巻、新潮社、1979年参照。
*10 フーコー、田村俶訳、前掲訳書『監獄の誕生――監視と処罰』、262頁。
*11 高橋『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』、刀水書房、2002年、第3章〈権力と強制の批判――『死の家の記録』と「非凡人の思想」〉参照。
*12 フーコー『監獄の誕生――監視と処罰』、引用は桜井哲夫『「近代」の意味――制度としての学校・工場』、NHKブックス、1984年、90頁より。
*13 リチャード・ピース、池田和彦訳『ドストエフスキイ 『地下室の手記』を読む』、のべる出版、2006年、102~128頁。
*14 フーコー、田村俶訳、前掲訳書『監獄の誕生――監視と処罰』、224頁。
*15 同上、202~204頁。
*16 同上、217~218頁。
*17 川端香男里「解説」、ザミャーチン、川端香男里訳『われら』、岩波文庫、1992年、357~371頁。
*18 2011年7月に東海大学高輪校舎で行われた第91回比較文明学会の研究例会については、比較文明学会HPの「研究例会」の頁を参照。
*19 佐藤清郎『わが心のチェーホフ』、以文社、2014年、「チェーホフとストア哲学」参照。
*20 戦争によって問題を解決しようとすることの危険性については、日本価値観変動研究センターの季刊誌「クォータリーリサーチレポート」に連載した8編の論考を再構成した拙論「戦争と文学 ――自己と他者の認識に向けて」『日本ペンクラブ電子文藝館』、2005年参照。
*21 髙橋「ドストエーフスキイの西欧文明観」、前掲書『比較文明学の理論と方法』、58~59頁。
*22 若きドストエフスキーとフーリエ主義との関係については、ベリチコフ編、中村健之介訳『ドストエフスキー裁判』北海道大学図書刊行会、1993年参照。
*23 トインビー、長谷川松治訳『歴史の研究Ⅰ』、社会思想社、1967年、75~76頁。
*24 加藤泰「書評」、『比較文明』第30号、2014年、255頁。
(『文明研究』第33号、東海大学文明学会、2014年、77~81頁)。
(2018年1月20日、書影を追加)