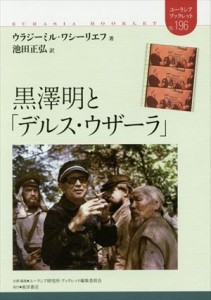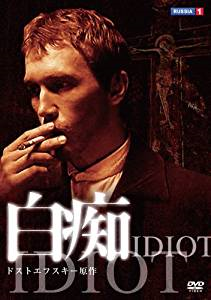リンク→「映画・演劇評」のページ構成
はじめに
かねてからタルコフスキー(一九三二~一九八六年)の映画には関心を持っており、映画《惑星ソラリス》は授業でも紹介していたが、なかなか詳しく調べる暇がなくそのままになっていた。それゆえ、タルコフスキー監督に関する多くの文献をとおして両者が会った年月を確認し、両監督の映画の深い関わりを明らかにした堀伸雄氏の「黒澤明とアンドレイ・タルコフスキー ~『七人の侍』に始まる魂の共鳴」(『黒澤明研究会誌』(第三二号)からは強い知的刺激を受けた。
さらに『ドストエーフスキイ広場』(第二四号)に掲載された「ドストエフスキーへの執念が育んだ〈絆〉― 黒澤明とアンドレイ・タルコフスキー」を読んだことで、ドストエフスキーの研究者ではない堀氏が長編小説『白痴』に示している深い理解の原因の一つが、黒澤明監督だけでなくドストエフスーをも深く尊敬していたタルコフスキー映画の理解にあることに気づいた。
それゆえ、本稿では堀氏の論文にも言及しながら映画《惑星ソラリス》を中心に考察することで、黒澤明とタルコフスキーのドストエフスキー観とその意義に迫ってみたい。
一、 黒澤監督と映画《惑星ソラリス》
「『惑星ソラリス』を中心に、物質性と精神性について」と題する論文でタルコフスキーは、「文芸作品の映画化」という側面から黒澤映画《白痴》などに次のように言及していた。
〈文芸作品の映画化は、映画監督が作品から離れて、なにか新しいものを作り出したときにのみ成功するのだと、私は信じています。(中略)最良の映画化とは、原作とは別の新しい何かなのです。シェイクスピアとドストエフスキーの最良の映画は、黒澤の『蜘蛛巣城』(マクベス)と『白痴』です。しかし黒澤はきわめて多くのものを破壊しました。全く新しいものを創造するために、舞台を現代に移しさえしています。例えば、ドストエフスキーの小説を逐語的に言いかえたり、図解したりしようとする映画監督よりも黒澤は、ドストエフスキーに近いことがわかるのです。文芸作品の映画化自体は、純粋の意味では、意味がないと思います〉*1。
ここでタルコフスキーは主人公を日本人とし、登場人物の数を減らして筋にも変更を加えつつも、長編小説『白痴』の本質を描いた黒澤映画の創作方法を見事に指摘しているといえるだろう。
しかし、ポーランドの作家スタニスワフ・レムのSF小説『ソラリス』を原作とした映画《惑星ソラリス》は、一九七二年にカンヌ国際映画祭審査員特別賞などを受賞したものの原作者からは酷評された。
その理由を原作者のレムは次のように語っている。「タルコフスキーは私の原作にないものを持ち込んだのです。つまり、主人公の家族をまるごと、母親やらなにやら全部登場させた。それから、まるでロシアの殉教者伝を思わせるような伝統的なシンボルなどが、彼の映画では大きな役割を果していたんですが、それが私には気に入らなかった」*2。
実際、レムの原作『ソラリス』では、ようやく、地球からの緊張に満ちた飛行を終えて宇宙ステーション「プロメテウス」に到着した心理学者のクリス・ケルヴィンが耳にしたのは、「単語の一つ一つが、鋭く飼い猫の鳴き声のような音で区切られていた」機械的な音声による案内であり、「控え目に言っても、奇妙なことだ。誰か新しい訪問者が到着した。しかもほかならぬ地球から来たのだ、とあれば、生きている者は誰でも発着場に駆けつけるのが普通ではないか」と感じたと描かれている*3。
さらに、主人公が宇宙ステーションで最初に出会ったサイバネティックス学者のスナウトは、クリスの到着に取り乱して「ギバリャンはどこだ?」という質問に答えないばかりか、天体生物学者のサルトリウス以外の誰かを見かけても「何もするな」という奇妙な警告を発するというきわめて緊迫した状況で始まる。
こうして、レムのSF小説では「知性を持つ巨大な存在」である「ソラリスの海」と人間との意志疎通の試みが大きなテーマであり、クリスは「ソラリスの海」によって主人公の記憶の中から実体化して送り出された「自殺した妻」ハリーとも出会うことになる。
一方、澄んだ水の流れとそこに揺らめく藻、そして草の情景から始まる映画《惑星ソラリス》では、原作にはない地球上での風景や家族とのやりとりが描かれており、それに対応するようなシーンで終わる。
それゆえ、訳者の沼野充義氏は「愛を超えて」と題した『ソラリス』の解説で、「(タルコフスキーの映画では――引用者注)シンボルは母から、母なるロシア、大地(地球)へつながっていき、映画は小説とは根本的に違うイデオロギー的意味を担うにいたる」と説明している*4。
たしかに原作と映画から受ける印象はかなり異なり、自分の原作にロシアの家族の物語を挿入された原作者レムの不満は理解できる。しかし、映画《惑星ソラリス》のテーマは、ロシア文学者でもある沼野氏の解釈のように、ロシア的な特殊なものに収斂されるのだろうか。むしろこの映画はドストエフスキー作品のように、きわめて深く個人の内面を描きつつ、普遍的なテーマをめざしているのではないのだろうか。
この意味で注目したいのは、映画《デルス・ウザーラ》の撮影のために当時のソ連に滞在していた黒澤監督が、一九七三年にタルコフスキーとともに映画《惑星ソラリス》を観たあとで、導入部の地球の自然描写の巧みさの中に、科学の進歩は人間を一体、どこへ連れていってしまうのかという根源的な恐ろしさを表現していると評価し、他の監督には見られない並はずれた感性に大いなる将来性を感じたと述べていたことである*5。
このような理解の背景にあるのは、この映画が提起している文明論的な課題の重視であろう。かつてソラリスで奇妙な体験をした宇宙飛行士のアンリ・バートンは、主人公のクリスが「ソラリスの海」の謎を解くために「非常手段として海に放射線を当ててみるか…」と語ると、たとえ研究にしても「手段を選ばぬやり方には反対だ。道徳性に立脚した研究でなければ…」と語り、「不道徳でも目的は遂げられます。ヒロシマのように」と主人公のクリスが反論するとバートンが「君は何を言うんだ。おかしいぞ」と激怒する場面が描かれているのである*6。
黒澤映画《デルス・ウザーラ》の冒頭の場面でも、沿海州を調査した隊長アルセーニエフが、探検隊のガイドをしてくれた森に詳しいデルスの墓を一九一〇年に訪れるが、開発によって工事が進み、その埋葬地さえも分からなくなっているというシーンが描かれている*7。
黒澤監督は記者会見でこの映画の理念についてこう語っていた。「人間は自然に対して好き勝手をしている。しかし、本当に自然を怒らせてしまったら、とんでもないことになる。…中略…環境汚染は海面だけでなく、海底にも及んでいる。今地球が危機に瀕している。今人類には環境を守ることが課題となったのだ。科学をそのために使わなければ自然は滅び、それとともに人間も滅びる。『デルス・ウザーラ』は二〇世紀初めの話だが、私の思いはそこにある」*8。
このような黒澤明の発言には『作家の日記』において、「森林がどんどん伐採されて影をひそめるおかげで、ロシアの気候はまるっきり別なものになろうとしています、水分を保持するところがなくなり、どこにも風をふせいでくれるものはありません」と木々が気候に与える影響について書き記していたドストエフスキーからの影響も見ることが可能だろう。
残念ながら日本では小林秀雄の解釈以降、ドストエフスキーの作品における骨太の文明論的な構造は軽視されるような傾向が今も続いている。しかし、ドストエフスキーは若い頃参加していたサークルの指導者であり、後に「ロシア植物学の父」と呼ばれるようになるアンドレイ・ベケートフとの交友を続けていた。そのベケートフは一八六〇年に「自然界の調和」という論文で、「勝者と敗者以外に何もない世界」を描き出していた社会ダーウィニストたちを批判するとともに、「自然界の調和は普遍的必然性の法則の表明」であると主張していた*9。『罪と罰』で「自然支配の思想」や「弱肉強食の思想」など近代西欧文明の問題点に鋭く切り込んだドストエフスキーには、このような文明論的な視野があるといえるだろう。
さて、映画はその後宇宙ステーション「プロメテウス」で物理学者ギバリャンが謎の自殺を遂げ、残った二人の科学者も何者かに怯えていることを描いた後で、クリスの前に数年前に自殺した妻ハリーが現われるという場面が描かれる。
この妻について映画《惑星ソラリス》では、旅立つ前に主人公のクリスが過去の思い出となる書類やかつての妻の写真を燃やすという地上のシーンで何回か示唆されていたが、妻の自殺に良心の呵責を覚えていたクリスは、「ソラリスの海」によって彼の記憶を物質化して送られた「妻のハリー」と出会うことにより、自分の内面を直視することになる。
それゆえ、映画《惑星ソラリス》の何度も現れる「妻」のシーンから、『罪と罰』の主人公・ラスコーリニコフが「高利貸しの老婆」を殺す前後に見るさまざまな「悪夢」を連想した私は、冒頭の藻のシーンからもラスコーリニコフが殺害の前に「花に見とれ」つつも、その意味を理解できずに立ち去ったという文章を思い浮かべたのである*10。
さらに、『罪と罰』の若き主人公は、酔っ払った少女をつけ回す中年の男を見つけて、警官を呼ぼうとしたあとで、数学の確率論を思い出し、今救ってもどうせ同じような結果になると考えてあきらめる一方で、今、すぐ大金が必要だとして「高利貸しの老婆」殺しを実行していた。
作品を読んでいない方には関係が分かりにくいかもしれないが、研究のためならば「非常手段として海に放射線を当ててみるか」と提案していた映画《惑星ソラリス》の主人公・クリスの考え方は、殺人を犯す前の『罪と罰』の主人公・ラスコーリニコフの思考法ときわめて似ているのである。
そのようなクリスに対して研究の続行を主張しつつも、「海を破壊すること」につながるような方法を拒絶していた宇宙飛行士のバートンは、それ以上の会話は無意味と考えて説得をあきらめるが、車で帰宅するバートンが高速道路で次々とトンネルを通過しながら考え込むシーンはきわめて印象的であり、映画《夢》の第四話「トンネル」のイメージとも重なる。バートンを「幻覚」を見た者のようにみなしてその主張を軽視していたクリスは、ソラリスでバートンの見た「幻覚」の意味を理解することになる。
このように見てくるとき、映画《惑星ソラリス》は『罪と罰』からの影響が非常に強いのではないかと思えるが、実際、堀氏の記述によれば「タルコフスキーの妹のマリーナと結婚した映画監督のアレクサンドル・ガルドン」も、「タルコフスキーの中には、常にドストエフスキーがおり、彼の作品には研究し、学び、考え、苦悩する芸術家ドストエフスキーが形を変えて現れる、つまり、タルコフスキーを通じてドストエフスキーが表現されている」と語っていたのである*11。
二、映画《惑星ソラリス》と『おかしな男の夢』、そして『白痴』
映画《惑星ソラリス》を初めて観た時に『罪と罰』とともに思い浮かべたドストエフスキー作品は、夢の中で他の惑星に行くというSF的な短編小説『おかしな男の夢』であった。この短編については、映画《夢》で実現されなかった「数学の不得意だった学生の私が、天使に導かれて地球から脱出しまた帰還して影と合体」するという話が描かれていたエピソード「飛ぶ」との関連で三井庄二氏の論文「現実と非日常の時空を超えた往還」(『会誌』第三〇号)にも言及しながら拙著でも簡単に触れていた*12。
三井氏は前号の論文の第九章で、タルコフスキーの映画『僕の村は戦場だった』における「イワン少年の見る叙情的な夢のシーン」にも言及している*13。一方、「まったく夢の中では、おれの理性にまったく理解しがたいことが起こるのである」と記された『おかしな男の夢』でも、夢の中で自殺した主人公は墓に埋葬された後で、広大な宇宙を旅して、地球と同じような星に着くのである*14。
そこはエデンの園のような理想郷で、主人公は彼らが「樹々と言葉をかわしていたと言っても、たぶん、あながちおれの誤りではあるまい!」と感じたばかりでなく*15、「なにかもっと積極的な手段によって、空の星と接触を保って」おり、「彼らは自然を讃え、大地を、海を、森を讃えた」とさえ確信したのである。
しかし、少し先を急ぎすぎたようなので、少し後戻りして主人公が自殺をしようとする動機などを確認しておく。
大作『罪と罰』の前に書かれた『地下室の手記』は、「わたしは病的な人間だ……わたしは意地悪な人間だ」という印象的な言葉で始まっていたが、『おかしな男の夢』も「おれはおかしな男だ。やつらはみんないまおれのことを気違いだと言っている。もしおれがやつらにとって、昔のままのおかしな男でないとすれば、それはつまり格が上がったというものである」という特徴的な言葉で始まっている。
こうして主人公の「自意識」や「自尊心」の問題に注意を促したドストエフスキーは、「この世界が存在しようとしまいと、あるいは、どこにもなにもないにしても、おれにとってはどっちみち同じことだ」と感じた主人公が、「素晴らしいピストルを買い込んで、その日のうちに弾丸(たま)をこめておいた」と記したあとで、ある少女と出会った夜のことを描いているのである。
ピストルを買い込んでから二ヶ月間も引き出しにしまい込んでいた主人公は、ある晩、暗い夜空を見上げて一つの星を見つめながら今晩こそ自殺を決行しようと考える。しかし、そんなときに「頭をスカーフで包み、薄い服を一枚身につけているだけで、全身ぐしょ濡れになっていた」八歳ぐらいの少女が、「おかあちゃん! おかあちゃん!」と必死に叫びながら、「おれの肘をつかんだのだった」。
「母親を助けるなにかの手だてを見つけるために、彼女は駆け出してきたものに相違ない」と理解しつつも、怒鳴りつけて追い払ってしまった主人公は、又借りをしている部屋に戻るとピストルを取り出してテーブルに置いた後で、安楽椅子に腰をかけたままで思いがけず眠ってしまう。
ドストエフスキーはその後で夢の中で「エメラルドのような輝きを放っている小さな星」に向かって飛び続けた主人公がその星を見つめながら「自分が見棄ててきた、なつかしい古巣の地球に対する、どうにも抑えがたい感激的な愛情」にとらわれたと書き、「あのとき自分が侮辱を与えた哀れな女の子の面影が、ちらりと目の前にひらめいた」と描いている。
この記述は惑星ソラリスで「なつかしい古巣の地球」で自殺させた妻に対する記憶にさいなまれるようになるクリスの良心の呵責をも説明しているように思える。
さらに、理想的な時代から戦争に明け暮れるようになるまでの人類の歴史を夢の中で主人公に体験させたドストエフスキーは、夢から覚めた主人公が「おれはこれから出かけて行って、たゆみなく、絶えず説きつづけるつもりだ」と決意し、「なによりも肝心なのは――自分を愛するように他人をも愛せよということで、これがいちばん大切なことなのだ」と思ったと描いている。
そして、「ところでおれは例の小さな女の子を探し出した……。さあ出発だ! それではいよいよ出かけるとしよう!」とこの短編は結ばれているのである。
「他者との関係」を失い「自殺」するというテーマは、『悪霊』などで中心的なテーマとしてたびたび描かれているが、この描写から私が連想したのは、長編小説『白痴』で主人公ムィシキンの敵対者となる重要な登場人物のイッポリートのことであった。
自殺し損なったイッポリートは悪意に駆られてさまざまなことを企み、それが悲劇を生むことになるのだが、ドストエフスキーはこの長編小説で別な可能性も示唆していたのである。
映画《白痴》ではこのイッポリートのエピソードは全く描かれていないが、拙著ではこの人物を主人公としながら、その可能性を閉ざすことなく描いたのが映画《白痴》(一九五一年)の翌年に公開された映画《生きる》であるという考えを記した。
先に挙げた論文「ドストエフスキーへの執念が育んだ〈絆〉」で堀伸雄氏も同じような見解を記していたが*16、それはおそらくタルコフスキーに関する主要な邦訳文献を読み込み、考察した結果だと思われる。
ロシア文学者の井桁貞義氏は第一回国際タルコフスキー・シンポジウムの挨拶で、「私にとって残念なことは、タルコフスキーがドストエフスキーの『白痴』を映画化するプランを、ついに実現できなかったこと」と述べていた*17。このことを紹介した堀氏は、「タルコフスキーの思想遍歴と監督生活の日常については、彼が遺した貴重な二つの書籍から読み取ることができる。ひとつは、彼の人生観・芸術観・映画観などを俯瞰的に叙述した『映像のポエジア』であり、他方は、彼自らが『殉教録』と名付けた日記である」と紹介している。さらに、タルコフスキーが一九七〇年四月三〇日の日記で、「ドストエフスキーは、私が映画で作ってみたいと思っていることのすべての核になるかもしれない」と書かれていることに注意を促した堀氏は、映画《惑星ソラリス》の後もタルコフスキーがいかに『白痴』の映画化に向けて終始、執念を燃やし続けていたかを文献をとおして明らかにしている*18。
残念ながら、タルコフスキーは『白痴』の映画化には成功しなかったが、ドストエフスキーが強い関心を持っていた詩人プーシキンの『ボリス・ゴドゥノフ』をオペラ化したムソルグスキーのオペラ《ボリス・ゴドゥノフ》の演出に携わっていた*19。
僭称者のテーマに強い関心を持ったドストエフスキーは、長編小説『悪霊』にこの問題を組み込んでいるが、プーシキンは歴史上の実在の人物をモデルとして権力者の「良心の呵責」の問題を描いたこの作品で、権力の獲得を目指したラスコーリニコフの先駆者とも呼ぶべき若き修道僧グリゴーリーに、彼が見た次のような夢について語らせていた*20。
「わたしは急な梯子をつたわって、塔に登った夢を見ました、モスクワが蟻塚のように見えました、下の広場では人民がひしめき、わたしを指さして笑うのです、わたしは恥ずかしくも恐ろしくもなりました。そして、まっさかさまに落ちると見て、ハッと目がさめました」。
その話を聞いた同室の老僧ピーメンは、それは若者の見る夢だとして、年代記を書いていたこともあり、イワン雷帝の幼い息子ドミトリーがゴドゥノフによって暗殺されたことを伝えた。その時、ピーメンはグリゴーリーの夢に強い権力へのあこがれを読み取り、その戒めとしてゴドゥノフのことを語ったと思われる。
しかし、皇子ドミトリーが生きていれば自分と同じ年齢になることを知ったグリゴーリーは僧院を出奔してリトアニアに逃げ、カトリック教徒のポーランド貴族の娘と結婚して改宗し、自分こそが生き残った皇子ドミトリーであると僭称して、ポーランド軍を率いてロシアに攻め込むことになるのである*21。
オペラ《ボリス・ゴドゥノフ》の演出に際して、皇帝(ツァーリ)となることを受け入れたゴドゥノフが、民衆の中にいた少年を見てはっとする場面を描いていたタルコフスキーは、修道院の「場」では、グリゴーリーとピーメンとの会話の背後で皇子ドミトリーが暗殺される場面を演じさせていた。それは偽ドミトリーとしてツァーリの座につき一時は権力を有するが、ほどなく亡ぶことになるグリゴーリーの将来をも示唆していたといえるだろう。しかもタルコフスキーはこのオペラの終幕ではモスクワに攻め込もうという偽ドミトリーの呼びかけに幻惑されて従う民衆を見た聖愚者にロシアの危機を語らせていた。
私自身としては、ゴドゥノフの子供達たちが自殺したと知らされ僭称者が皇帝になったことを祝うように強要された民衆が、「黙して答えず」と結ばれていた原作の方がその後の歴史を暗示して引き締まっていると感じている。しかし、このオペラの結末のシーンからはタルコフスキーが、「殺すなかれ」という理念を唱えていた長編小説『白痴』の主人公ムィシキンの悲劇を強く意識していたことは確実だと思われる。なぜならば、自分の恩人がカトリックに改宗していたということを知らされ、激しい衝撃を受けたこともあり主人公が元の「白痴」に戻ってしまうこの長編小説の結末も、ロシアの精神的な危機が強く示唆されているからである*22。
最後にもう一度映画《惑星ソラリス》に戻るが、「無重力になった宇宙ステーション内の図書館で抱き合って宙に漂うクリスとハリー」のシーンの直前に「少年時代の主人公が乗っていたと思われるブランコが雪に覆われた丘の上でかすかに揺れるショットがある」。そのことに注意を促したロシア文学者の相沢直樹氏は、そこに黒澤映画《生きる》との関連を見て、そのシーンは「クロサワへのオマージュだったかも知れない」と書いている*23。
黒澤監督がタルコフスキーと一緒に試写室で『惑星ソラリス』を観た後にウォッカで乾杯し、一緒に『七人の侍』だけでなく『生きる』のテーマなどを歌ったという、黒澤和子さんからの証言も踏まえた堀氏の興味深い記述にも留意するならば*24、そのシーンは実際に「クロサワへのオマージュだった」可能性が高いと思われる。
追記:
ブログに記したように、考察に際しては「ドストエーフスキイの会」第215回例会で「ドストエーフスキイとラスプーチン ――中編小説『火事』のラストシーンの解釈」という題で発表された大木昭男氏の考察からも強い示唆を受けています。
ドストエフスキーが1864年に書いたメモで、人類の発展を「1,族長制の時代、2,過渡期的状態の文明の時代、3,最終段階のキリスト教の時代」の三段階に分類していたことを指摘した大木氏は、『火事』とドストエフスキーの『おかしな男の夢』の構造を比較することで、その共通のテーマが「己自らの如く他を愛せよ」という認識と「新しい生」への出発ということにあると語っていたのです。
この指摘は長編小説『白痴』の映画化にも強い関心をもっていたタルコフスキーのドストエフスキー観を理解するうえでも重要でしょう。
注
*1 月刊「イメージフォーラムNO80追補・増補版」七七頁。鴻英良訳による。引用は『会誌』第三二号に掲載の堀伸雄論文より)。
*2 スタニスワフ・レム、沼野充義訳『ソラリス』国書刊行会、二〇〇四年、三六〇頁。
*3 同右、八頁。
*4 同右、沼野充義「愛を超えて」(訳者解説)、三六〇頁。
*5 堀伸雄、前掲論文「黒澤明とアンドレイ・タルコフスキー」、九七頁。
*6 DVD《惑星ソラリス》、アイ・ヴィ・シー、二〇〇二年。
*7 DVD《デルス・ウザーラ》、オデッサ・エンタテインメント、二〇一三年。
*8 ウラジーミル・ワシーリエフ、池田正弘訳『黒澤明と「デルス・ウザーラ」』東洋書店、六~七頁。
*9 トーデス、垂水雄二訳『ロシアの博物学者たち』、工作社、一九九二年、一〇一頁。
*10 高橋『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』、二〇〇〇年、一九九頁。
*11 堀伸雄、前掲論文「黒澤明とアンドレイ・タルコフスキー」、一一五頁。
*12 高橋『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』成文社、二〇一四年、二〇一頁。
*13 三井庄二「『七人の侍』に見る伝統文化と歴史観」(『会誌』第三二号)。平和時の叙情的な映像と戦時の過酷な日々が対比されている『僕の村は戦場だった』の夢からは、『戦争と平和』において突撃のシーンの前に見るペーチャの夢も連想される。
*14 小沼文彦訳『おかしな男の夢――幻想的な物語』、『ドストエフスキー全集』第一三巻、一九八〇年、筑摩書房。以下もこの訳からの引用による。
*15 前掲書『「罪と罰」を読む(新版)』では、この記述に注意を促しつつ、ソーニャという存在との類似性を指摘した。
*16 堀伸雄、前掲論文「ドストエフスキーへの執念が育んだ〈絆〉」、三二頁。
*17 堀伸雄、前掲論文「黒澤明とアンドレイ・タルコフスキー」、一一四~一一五頁。
*18 堀伸雄、前掲論文「ドストエフスキーへの執念が育んだ〈絆〉」、四一頁。
*19 都築政昭氏の『プーシキンの恋 自由と愛と憂国の詩人』(近代文芸社、二〇一四年)では、波乱に満ちたプーシキンの生涯だけでなく、主要な作品も詳しく紹介されている。『ボリス・ゴドゥノフ』については一八三頁から一九四頁参照。
*20 プーシキン、佐々木彰訳『ボリス・ゴドゥノフ』(『世界文学体系』第二六巻)、筑摩書房、一九六二年、二〇九頁。
*21 DVD『ボリス・ゴドゥノフ』(『DVDオペラ・コレクション』)、デアゴスティーニ・ジャパン、二〇一一年。
*22 高橋『黒澤明で「白痴」を読み解く』、成文社、二〇一一年、二三四~二五二頁。
*23 相沢直樹『甦る「ゴンドラの唄」 「いのち短し、恋せよ、少女」の誕生と変容』、新曜社、二〇一二年、三一二頁。
*24 堀伸雄、前掲論文「黒澤明とアンドレイ・タルコフスキー」、九六頁。