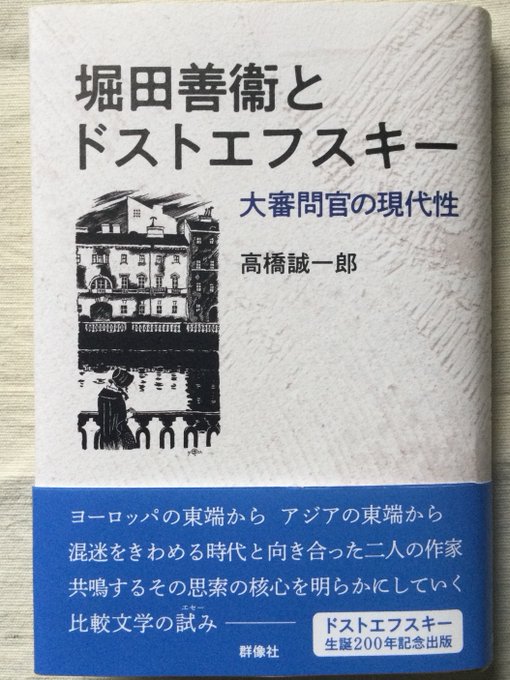
はじめに
群像社から2021年10月に発行した拙著の書評が掲載された『世界文学』№135が届きました。
評者の平山令二氏(中央大学法学部名誉教授)は、ドイツ文学の研究者で近著に『ユダヤ人を救ったドイツ人―「静かな英雄たち」』(鴎出版、2021年)があります。
ドストエフスキー文学や堀田善衞作品にも造詣が深い評者は、拙著の全体像を正確に紹介したあとで、「(本書の発行が)本年2月に突然始まったロシア軍のウクライナ侵略以前」にもかかわらず「重要な問題点の提起が見られる」とし、プーチンによるウクライナ侵攻と満州事変以降の日本との比較も戦争とプロパガンダという視点から試みています。
拙著ではこの問題を扱うことができなかったのを残念に感じていたので、評者にはこの場を借りて感謝の意を表します。著者と編集委員会からの了解を得ましたので、一つの誤植を訂正したうえで、以下に書評の全文を転載します。
『堀田善衞とドストエフスキー 一大審問官の現代性-』を読む
昨年2021年はドストエフスキー生誕200周年にあたる。本書はそれを記念して出版された比較文学の研究書である。ところで堀田善衞とドストエフスキーという取り合わせを見て、意外に思う人と当然と思う人に分かれるのではなかろうか。私は前者だった。
ドストエフスキーの日本の戦後派作家への影響を考えると、すぐに思い浮かぶのは埴谷雄高、椎名麟三、武田泰淳、野間宏といった第一次戦後派の面々であろう。革命運動、弾圧、転向という彼らの体験はドストエフスキーへの強い関心につながる。彼らの下の世代にあたる堀田善衞はいかなる抵抗も不可能に見える時代に青春期を送った。世代経験が違うのである。また、堀田の晩年の大作は『ゴヤ』であり、モンテーニュについても書いている。多彩な才能を発揮した堀田であるが、ドストエフスキーとの関わりが仕事の中心にあるとは思えない。
しかしながら、本書は堀田の仕事の最初から最後まで、ドストエフスキーが一貫して重要な刺激を与えたことを明らかにしている。本書により、堀田の仕事に対するドストエフスキーの影響の全体像が初めて明らかになり、あらたな視角から堀田文学の全体像も同時に明らかにされた。
1
本書は全7章からなり、序章と終章を除く5つの章は、堀田の作品とドストエフスキーの作品を具体的に対照させて、そこに共通する両作家の問題意識や手法を論じている。
冒頭に置かれた「はじめに 堀田善衞のドストエフスキー観」は、本書全体を貫く構想を明らかにしている。堀田は1918年に富山県伏木町の北前船の廻船問屋に生まれている。首都から離れた地方の小さな町というイメージがあるが、日本海を通じて日本各地、さらには世界にもつながる開かれた風土であった。堀田文学の日本にとどまらない世界へ開かれた開放性は、このような育ちに関係するだろう。
堀田が中学に入学した年には、満州事変が勃発して重苦しい日々となった。受験のために上京した1936年には2.26事件が起きた。昭和初期の暗い時代に堀田が没頭したのがドストエフスキーの作品群であった。堀田はラジオから流れてきたゲッベルスのドイツ語による野蛮な演説を聞いて、政治学科からフランス文学科に転入を決意し、卒業論文では、『白痴』のムイシュキンとランボーの比較を取り上げる。
堀田のドストエフスキー観は終戦間際の2つの体験によりきわめて現代的な深まりを示す。3月10日の東京大空襲を体験してから24日の上海出発までの短期間、集中的に『方丈記』を読み、鴨長明の記述する京の大火災が東京大空襲につながるものであることに気づいた。その後、上海で堀田は、広島、長崎への原爆投下のニュースを知り、『ヨハネの黙示録』の終末論的なビジョンとの暗合に震える思いがした。
堀田が上海で知り合った武田泰淳は帰国後、中国で犯した殺人の罪と向き合うために現地に残る兵士を主人公とした『罪と罰』を思わせる短編『審判』を書いた。武田の問題意識は、中国の知識人の視点から南京虐殺を描いた堀田の長編小説『時間』につながっている。
長編小説『零から数えて』と長編小説『審判』では、アメリカ人の原爆投下機のパイロットの苦悩を通して「黙示録」的な規模の悲劇が描写され、核戦争の勃発が全人類の滅亡につながる恐怖が示されている。『審判』はドストエフスキーの『白痴』の鋭い心理分析や複雑な人間関係を研究した上で描かれている。『審判』が発表された1963年のアンケートへの回答で、「現代のあらゆるものは、萌芽としてドストエフスキーにある。たとえば、原子爆弾は現代の大審間宮であるかもしれない」と堀田は書いている。晩年の大著『ゴヤ』で、堀田は国民軍が動員されたナポレオン戦争や「スペイン戦争における異端審問」の問題を文明論的な視点から深く考察している。
2
本書の出版は2021年10月なので、当然ながら本年2月に突然始まったロシア軍のウクライナ侵略以前である。しかしながら、本書にはウクライナ侵略にも関係する重要な問題点の提起が見られる。本書は、単に堀田善衞とドストエフスキーを比較文学的視点から考察しただけの研究書ではない。思想弾圧、民族差別、プロパガンダ、核戦争といった現在の課題に直結する問題を扱っている。すなわち、堀田やドストエフスキーを偉大な古典と解釈して終わるのではなく、彼らの作品が今も生命力を持っていて、現在の難問に対する回答、少なくとも対処の視角を示しているという問題提起を行っている。したがって、本書にウクライナ侵略を考える視角も現れ、しかもそれが日本の今と無縁でないことがわかるのである。
そこでこれからは、ウクライナ侵略という蛮行、悲劇を踏まえて、戦争とプロパガンダの問題に焦点を当て本書の視角を検証してみたい。
ウクライナ侵略は、20年以上にわたり独裁体制を着々と構築してきたプーチンが最後に到達した恣意的な強権支配の「総決算」である。なぜ、21世紀にもなって、それこそ封建時代の王たちが恣意的に戦争を始めたように、このような不法な侵略が行われるのか。しかもプーチンが行ったクリミア略奪などの局地戦争の形ではなく、ウクライナという国家全体を纂奪するという全面戦争である。
その秘密はプーチンが国家情報機関KGB出身であったことにある。プーチンは情報をつかむものが冷戦、そして熱い戦争にも勝利すると体験して、国内での権力維持にも情報の一元的支配の重要性を感じたのである。今回、プーチンはロシア国内で完全な情報統制を行い、国民に「戦争」ではなく「特別軍事作戦」を行っているだけだとプロパガンダをしている。これに反旗を翻したのが国営テレビのオフシャンニコワさんである。プーチンの手法はゲッベルスのナチス宣伝省、さらには「戦争」の代わりに「事変」を多用した軍国日本の情報統制につながる。
このような偽情報に毎日、毎時間さらされることで国民は支配者の言い分を真に受けるようになる。そのひとりの例が『若き日の詩人たちの肖像』に登場する「アリョーシャ」という仇名の若者である。ドストエフスキーと太宰治を信奉する文学青年である「アリョーシャ」は日本軍の敗色が濃厚になるにつれ、プロパガンダに全身染められて、ついには「キリストが天皇陛下なんだ。つまり天皇陛下がキリストをも含んでいるんだ」とまで言い始める。
国家プロパガンダの影響を受けやすいのは純真な青年層のように思えるが、他方、知識と経験のある知識人にも、プロパガンダに影響を受け、自らもプロパガンダを発信するハブのような役割を果たす人物がいる。本書では、プロパガンダに一貫して批判的な若き堀田と対照的な人物として、小林秀雄が取り上げられている。
小林の戦時中の自らの言動に対する発言として知られるのは、1946年の「近代文学」誌における座談会「小林秀雄を囲んで」であり、戦時中の言動を批判された際、小林は「自分は黙って事変に処した、利口なやつはたんと後悔すればいい」と語ったとされる。戦争犯罪に加担したという批判に、このように「毅然とした反論」をしたことで、小林は戦後の批評の世界で教祖的な地位を占め、「大学の入試問題」にも頻出するようになった。しかし、座談会に出席していた埴谷雄高は小林の「発言」はあとで付け加えたものであると証言している。また、小林の弟子筋の大岡昇平は、小林は「黙って事変に処してはいない」と皮肉っている。小林はこのように自らの戦中の言動を巧妙に隠蔽し、戦後批評における地位を確保した。プロパガンダのハブとしての役割を見事に隠しおおせたのである。
小林は、真珠湾攻撃の航空写真から受けた印象を当時のエッセイ「戦争と平和」で書いている。「空は美しく晴れ、眼の下には広々と海が輝いていた。漁船が行く、藍色の海の面に白い水脈を曳いて。さうだ、漁船の代わりに魚雷が走れば、あれは雷跡だ、といふ事になるのだ。海水は同じ様に運動し、同じ様に美しく見えるであろう。」真珠湾攻撃も空から俯瞰すると戦場の阿鼻叫喚は消えて、美的な光景しか残らない。これに対して、堀田の『若き日の詩人たちの肖像』では、特攻潜航艇での真珠湾特別攻撃で海の藻屑と消えた兵士たちについて、「親御さんたちゃ、切ないぞいね」と同情するお婆さんの言葉が語られる。人間の視点からの発言である。小林秀雄は『我が闘争』に関して「彼(ヒトラー)は、彼のいわゆる主観的に考える能力のどん底まで行く。そしてそこに、具体的な問題に関しては決して誤たぬ本能とも言うべき直覚をしっかり掴んでいる」と書いている。小林の逆説とレトリックに満ちた言説は、ヒトラーの犯罪を薄める役割をする。しかも、この文章もあとで抹消してしまう巧妙さである。
南京虐殺を中国人知識人の目で描いた『時間』では、知識人は日本をこう批判する。「彼等は(中略)孤独に堪えずして他国に押し込み、押し込むことによって孤立する。(中略)全世界の征服と、全世界からの逃亡とは、彼等にとって同義語ではなかろうか。孤立、破滅、そこに一種の美観にも似たものがあるらしい、それがわたしにはわかる。」また、柳条溝鉄路爆破事件について知り合いの日本軍大尉の認識を批判する。「驚くべきことに、彼はあの事件が日軍が自ら手を下して爆破したものであることを知らない。中国軍がやったのだ、と思い込んでいる。日本人以外の、全世界の人々が知っていることを、彼は知らない。」この「彼」に、戦争ではない「特別軍事作戦」だというプーチンのプロパガンダを信じるロシアの兵士や市民も重なるだろう。彼らにとっては、世界中がウクライナ侵略でロシアを批判して孤立したとしても、それはむしろプーチンの正しさの証明であり、世界が欧米のプロパガンダに汚染されている証拠と解釈されてしまう。
願わくば、この書評が掲載される時期までにウクライナの人々に平和が訪れ、ロシアの人々がプーチンのプロパガンダの呪縛から解放されますように。本書もそのような願いを目覚めさせる強い働きをしている。
(『世界文学』№135、115~117頁)