はじめに――堀田善衞と小林秀雄のヒトラー観と堀田善衞
小林秀雄の短い書評「ヒットラアの『我が闘争』」が朝日新聞に掲載されたのは1940年9月12日のことであったが、それから間もない9月27日には日独伊三国同盟が締結された。
小林秀雄は後に雑誌『文藝春秋』(1960年5月号)に掲載した「ヒットラーと悪魔」でこの記事についてこう書いている。
「ヒットラーの『マイン・カンプ』が紹介されたのはもう二十年も前だ。私は強い印象を受けて、早速短評を書いた事がある。今でも、その時言いたかった言葉は覚えている。」
しかし、掲載された書評と小林秀雄の記憶とを比較すると、かなり大きな違いがあることがわかる。それについてはすでに別稿で記した。
→小林秀雄のヒトラー観(1)――書評『我が闘争』と「ヒットラーと悪魔」をめぐって
この問題について堀田善衛はなにも記していないようだが、重苦しい昭和初期の日々を若き詩人たちとの交友をとおして克明に描き出している『若き日の詩人たちの肖像』(1968年)では、何度もナチスの宣伝相ゲッベルスの演説などについて何度も言及されている。
ことにこの長編小説の終わり近くで作者はは登場人物に、「神仏習合って言うけど、古神道がキリスト教と習合し、いまどきの論文書きどもは、国学とナチズムの習合なんかをやってんだから話しにもなんにもなりゃせんよ」と厳しく「国学とナチズムの習合」を批判させているのである。
以下、本稿では『若き日の詩人たちの肖像』の記述をとおして、小林秀雄のヒトラー観に対する堀田善衛の批判を検証する。
1、『若き日の詩人たちの肖像』の構造とナチズムの考察
この長編小説の主人公は、大学受験のために上京した翌日に日本文化を重んじて物質より精神を重視する皇道派の影響を受けた陸軍青年将校たちが「昭和維新、尊皇斬奸」をスローガンにしたに遭遇する。
この長編小説で注目したいのは、2.26事件だけでなく幕末から明治初期と同じように「昭和維新、尊皇斬奸」が叫ばれるようになっていたこの時期の雰囲気が詳しく描かれていることである。
たとえば、この事件の前年に起きた統制派の中心人物・永田鉄山陸軍省軍務局長が殺害された相沢事件や、1934(昭和9)年に『ファッシズム批判』を出版していた河合栄治郎・東京帝国大学教授の「二・二六事件の批判」(帝国大学新聞)や軍国主義と「国体明徴」運動を批判して伏字ばかりの文章となっていた『中央公論』の巻頭論文も詳しく紹介されている。
こうして、第一部の終わり近くでは主人公の「生涯にとってある区分けとなる影響を及ぼす筈の、一つの事件」が起きる。ラジオから流れてきたナチスの宣伝相ゲッベルスの演説から「明らかにある種の脅迫」を感じた主人公は、続いて流れてきた「フランスのただの流行歌(シャンソン)」に「異様な感銘」を受け、「異様なことに、いますぐ何かをしなければならぬ」と思って背広を着て外に出るのである。
その後で作者は、「空には秋の星々がガンガンガラガラに輝いていた」のを見た若者が、「星を見上げて、つい近頃に読んだある小説の書き出しのところを思い出しながら、坂を下りて行った」と書き、題辞でも引用していた『白夜』の冒頭の文章「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた(後略)」を引用して、「小説は、二十七歳のときのドストエフスキーが書いたものの、その書き出しのところであった」と説明している。
『白夜』を発表したドストエフスキーがこの後でペトラシェフスキー事件で逮捕され、偽りの死刑宣告を受けた後でシベリアに送られていたことや、それまで主人公を「少年」と記していた作者がここで「若者」と呼び変えている。こうして、ゲッベルスの演説から「異様な衝撃」を受けた若者は、それまで学んでいたドイツ語を捨てて新たにフランス語の勉強を始めて、昭和15年秋に法学部政治学科から仏文科に転科することになる。
しかも、そこでは仏文科の先輩である白柳君との会話をとおして、日本では「商工省の通達があって、洋書の輸入は禁止された」ことをが、「一九三五年にパリで行われた国際作家会議の記録によると、ドイツの作家代表は匿名は無論のこと、顔に覆面までをかぶって出て来るというひどい政治の有様」になっていたことも記されている。
実は1933年1月にナチスが政権を握った後では「非ドイツ的な魂」に対する抗議運動が行われ、『人権宣言論』などを書いていたユダヤ人の公法学者イェリネックの本も焚書の対象とされた。「天皇機関説」事件でやり玉に挙げられた美濃部達吉は、その『人権宣言論』を1906年に訳出しており、一方、ゲッベルスは焚書に際して扇動的な演説をしていた。
一方、日本は2・26事件が起きた1936年の11月に日独防共協定が結び、主人公が「赤紙」で召集された1940年の9月には日独伊三国同盟を結ぶことになるのである。


 (ナチス・ドイツの焚書)
(ナチス・ドイツの焚書)

 (書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)
(書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより) 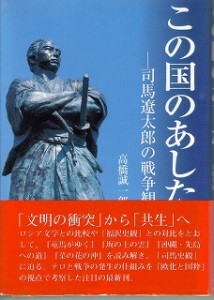
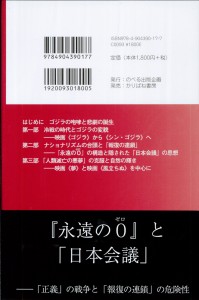


 (「ウィキペディア」より)
(「ウィキペディア」より)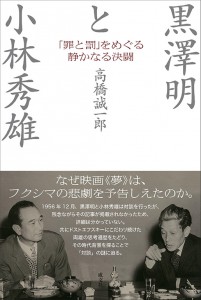
 写真の出典は奈良県立図書情報館。
写真の出典は奈良県立図書情報館。



