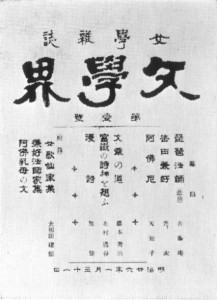一葉の研究者である和田芳恵氏は、樋口一葉の婚約者だった渋谷三郎の兄で郵便局長だった渋谷仙二郎の家に、石阪昌孝を最高指導者とする自由民権運動の結社の事務所が置かれていたことを指摘しています(「樋口一葉 明治女流文学入門」『日本現代文学全集』第10巻)。
和田氏は一葉と渋谷三郎が会ったのが、大阪事件のあった明治18年で、この頃に三郎が自由民権運動から離脱していたことにもふれています。北村透谷の研究者には、よく知られていることと思われますが、一葉の経歴と透谷には、石阪昌孝という接点があったのです。
まだ奈津と結婚をするという覚悟の出来ていなかった三郎は、その後去っていったのですが、和田氏は顕真術者・久佐賀義孝に面会した後で一葉が記した激しい言葉に、「はじめて知ったころの、自由党の壮士渋谷三郎」との関わりを見ています。
* * *
樋口一葉が小説「十三夜」で描いたお関と『罪と罰』のドゥーニャとの簡単な比較は、「絆とアイデンティティ」という教養科目で用いた教科書『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』で行っていました。ここではそこでの考察を踏まえてもう少し掘り下げてみたいと思います。
研究者の菅聡子氏は「『十三夜』の闇」と題した章の冒頭で、こう記しています。
「『にごりえ』のお力が制度外の女性であったのに対して、『十三夜』で一葉が描いたのは、まさしく制度内の女--斎藤家の娘、原田の妻、太郎の母--としてのお関の姿であった」、「制度内の、あるいは家庭の中の女性にとって、〈娘・妻・母〉という制度内の役割以外の生は存在しないのだろうか」(『樋口一葉 われは女なりけるものを』NHK出版)。
正月の羽子板の羽が奏任官の原田の車に落ちるという偶然の出会いで原田勇に見初められ、身分の不釣り合いを超えて原田家に嫁いだお関は、初めの頃はちやほやされていたのですが、息子の太郎を出産した後は、教育のないことなどをさげすまれて、辛い毎日を送るようになっていたのです。
離婚を決意して戻ってきた娘の訴えを聞いた父親は、「お前が口に出さんとて親も察しる弟も察しる」と慰めるのですが、離縁という選択肢はほとんどありませんでした。このことについいて菅氏はこう説明しています。
「お関の父・斎藤主計(かずえ)は没落した士族であるらしい。その斎藤家の復興の望みが託されているのは、次期家長である亥之助(いのすけ)である。昼は勤めに出、夜は夜学に通う亥之助の、将来の立身出世がかなうか否かに斎藤家の将来もかかっているのだ。この彼の将来にとって、『奏任官』原田の力は絶大である」。
こうして一葉は「十三夜」で、勉強熱心な弟・亥之助や置いてきた幼い一人息子の太郎のことを持ち出されて説得され、「私の身体は今夜をはじめに勇のもの」と再び戻る決心をしたお関の苦悩を描き出していたのです。
このような「十三夜」の内容を詳しく知るとき、『罪と罰』で描かれているラスコーリニコフの妹・ドゥーニャの重い決心の理由もよく理解できるでしょう。
『罪と罰』で描かれることになる事件の発端は、ラスコーリニコフが母親からの手紙で、ドゥーニャが近くペテルブルクに事務所を開く予定の弁護士ルージンと婚約したことを知ったことにありました。
兄に送金するために「家庭教師として住みこむとき、百ルーブリというお金を前借り」していたドゥーニャは、雇用者のスヴィドリガイロフから言い寄られても、「この借金の片がつくまでは、勤めをやめるわけに」いかなかったのです。最初は、夫が誘惑されたと思い込んだ妻のマルファは悪い噂を広めたのですが、後にドゥーニャの潔白を知って、年配とはいえ立身出世していた自分の遠縁のルージンを結婚相手として紹介したのです。
ドゥーニャが婚約に至るまでのこのようないきさつを手紙で詳しく記した母のプリヘーリヤは、息子にやがてルージンの「共同経営者にもなれるのじゃないか、おまけにちょうどお前が法学部に籍を置いていることでもあるしと、将来の設計まで作っています」と書き、ドゥーニャについて「あの子が、おまえをかぎりもなく、自分自身よりも愛していることを知ってください」と書いた後で、「おまえは私たちにとってすべてです」と続けていました。
ここで注目したいのは、「十三夜」のお関の夫・原田が「明治憲法下の高等官の一種で、高等官三等から八等に相当する職とされていた」奏任官(そうにんかん)であったと記されていることです。弁護士のルージンも七等文官であると記されていますが、ロシアの官等制度のもとでは八等官になると世襲貴族になれたので、日本の制度に当てはめれば奏任官と呼べるような地位だったのです。
長編小説『罪と罰』の構成の見事さは、マルメラードフの家族の悲劇をきちんと具体的に描くことで、家族を養うために売春婦に身を落としたソーニャの苦悩をとおして、兄の立身出世のために中年の弁護士ルージンとの愛のない結婚を決意したラスコーリニコフの妹ドゥーニャの苦悩をも浮かび上がらせているにあると思います。
小説「にごりえ」でお力におぼれて長屋住いの土方の手伝いに落ちぶれた源七だけでなく、「自ら道楽者」と名乗る裕福な上客・結城朝之助も描いていた樋口一葉は、「十三夜」でも原田家に戻る途中のお関と「小綺麗な煙草屋の一人息子」であったが、おちぶれて「もっとも下層の職業の一つとされた」人力車夫に落ちぶれていた高坂録之助との出会いも描くことで、小説の世界に広がりを与えていたのです。