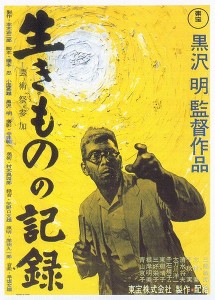一、映画『十三階段への道』とアイヒマンの裁判
雑誌『文藝春秋』(1960年5月)に掲載された「ヒットラーと悪魔」の冒頭で小林秀雄は、「『十三階段への道』(ニュールンベルク裁判)という実写映画が評判を呼んでいるので、機会があったので見た」と記し、実写映画という性質に注意を促しながら、「観客は画面に感情を移し入れる事が出来ない。破壊と死とは命ある共感を拒絶していた。殺人工場で焼き殺された幾百万の人間の骨の山を、誰に正視する事が出来たであろうか。カメラが代ってその役目を果たしたようである」と書いた。
実際、NHKの佐々木敏全による日本版「解説」によれば、この映画は「裁判の記録映画」であるばかりでなく、「各被告の陳述にあわせ一九三三年から四五年までの十二年間、ナチ・ドイツの侵攻、第二次世界大戦、そしてドイツを降伏に導いた恐ろしい背景を、その大部分が未公開の撮影および録音記録によって」描き出したドラマチック・ドキュメンタリーであった。
→ニュールンベルグの戦犯 13階段への道 – CROSS OF IRON
一方、カメラの役目を強調して「御蔭で、カメラと化した私達の眼は、悪夢のような光景から離れる事が出来ない」と続けた小林は、「私達は事実を見ていたわけではない。が、これは夢ではない、事実である、と語る強烈な精神の裡には、たしかにいたようである」と続けていた。
「事実」をも「悪夢」に帰着させているかのように見えるこの文章を読みながら思い出したのは、小林秀雄が1934年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」において、「殺人はラスコオリニコフの悪夢の一とかけらに過ぎぬ」と書き、「罪の意識も罰の意識も遂に彼には現れぬ」と解釈していたことであった(髙橋『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』参照)。
注意を払いたいのは、「何百万という人間、ユダヤ人、ポーランド人、ジプシーなどの、みな殺し計画」を実行し、敗戦後にはブラジルに潜んでいたアイヒマンがこの映画が公開されたのと同じ年の5月に逮捕されたことが5月25日に発表され、翌年の1961年には裁判にかけられたことである。 
(アイヒマン裁判、写真は「ウィキペディア」より)
映画『十三階段への道』を見ていた小林秀雄は、この裁判をどのように見ていたのだろうか。ちなみに、1962年8月には、アイヒマンの裁判についても言及されている『ヒロシマわが罪と罰――原爆パイロットの苦悩の手紙』(G・アンデルス、C・イーザリー著、篠原正瑛訳、筑摩書房)が日本でも発行されたが、管見によれば、小林秀雄はこの著書に言及した書評や評論も書いていないように見える。→「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(4)――良心の問題と「アイヒマン裁判」
 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)
二、「ヒットラーと悪魔」とその時代
改めて「ヒットラーと悪魔」を読み直して驚いたのは、おそらく不本意ながら敗戦後の文壇事情を考慮して省かざるを得なかったヒトラーの「決して誤たぬ本能とも言ふべき直覚」や「感傷性の全くない政治の技術」が、ドストエフスキー論にも言及することで政治的な色彩を薄めながらも、『我が闘争』からの抜き書きともいえるような詳しさで紹介されていたことである(太字は引用者)。
最初はそのことに戸惑いを覚えたが、この文章が掲載されたこの当時の政治状況を年表で確認したときその理由が分かった。東条英機内閣で満州政策に深く関わり戦争犯罪にも問われた岸信介は、首相として復権すると1957年5月には国会で「『自衛』のためなら核兵器を否定し得ない」と答弁していた。そして、1960年1月19日にはアメリカで新安全保障条約に調印したのである。この条約を承認するために国会が開かれた5月は、まさに激しい「政治の季節」だったのである。
この時期の重要性については黒澤明監督の盟友・本多猪四郎監督が、大ヒットした映画《ゴジラ》に次いで原水爆実験の危険性を描き出した1961年公開の映画《モスラ》で描いているので、本論からは少し離れるが確認しておきたい、(『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』(のべる出版企画、2016年、45頁)。
すなわち、1960年の4月には全学連が警官隊と衝突するという事件がすでに起きていたが、5月19日に衆議院の特別委員会で新条約案が強行採決され、5月20日に衆議院本会議を通過すると一般市民の間にも反対の運動が高まり、国会議事堂の周囲をデモ隊が連日取り囲むようになった。そして、6月15日には暴力団と右翼団体がデモ隊を襲撃して多くの重傷者を出す一方で、国会議事堂正門前では機動隊がデモ隊と衝突してデモに参加していた東京大学学生の樺美智子が圧死するという悲劇に至っていた。
また、1958年には三笠宮が神武天皇の即位は神話であり史実ではないとして強く批判し、「国が二月十一日を紀元節と決めたら、せっかく考古学者や歴史学者が命がけで積上げてきた日本古代の年代大系はどうなることでしょう。本当に恐ろしいことだと思います」との書簡を寄せたが、「これに反発した右翼が三笠宮に面会を強要する事件」も発生していた(上丸洋一『「諸君!」「正論」の研究 保守言論はどう変容してきたか』岩波書店、10頁)。なぜならば、戦前の価値の復活を求める右翼や論客は「紀元節奉祝建国祭大会」などの活動を強めていたのである。
三笠宮は編著『日本のあけぼの 建国と紀元をめぐって』(光文社、1959年)の「序文」で「偽りを述べる者が愛国者とたたえられ、真実を語る者が売国奴と罵られた世の中を、私は経験してきた。……過去のことだと安心してはおれない。……紀元節復活論のごときは、その氷山の一角にすぎぬのではあるまいか」と書いていた。
書評『我が闘争』の『全集』への収録の際には省いていたヒトラーの「決して誤たぬ本能とも言ふべき直覚」や「感傷性の全くない政治の技術」をより詳しく紹介した「ヒットラーと悪魔」は、まさにこのような時期に書かれていたのである。
三、「感傷性の全くない政治の技術」と「強者への服従の必然性」
映画についての感想を記したあとで、20年前に書いた書評の概要を記した小林は、「ヒットラーのような男に関しては、一見彼に親しい革命とか暴力とかいう言葉は、注意して使わないと間違う」とし、「彼は暴力の価値をはっきり認めていた。平和愛好や暴力否定の思想ほど、彼が信用しなかったものはない。ナチの運動が、「突撃隊」という暴力団に掩護されて成功した事は誰も知っている」ことを確認している。
しかし、その箇所で小林はヒトラーの「感傷性の全くない政治の技術」についても以下のように指摘していたが、それは現在の安倍政権の運営方法と極めて似ているのである。
「バリケードを築いて行うような陳腐な革命は、彼が一番侮蔑していたものだ。革命の真意は、非合法を一挙に合法となすにある。それなら、革命などは国家権力を合法的に掌握してから行えば沢山だ。これが、早くから一貫して揺がなかった彼の政治闘争の綱領である。」
そして、「暴力沙汰ほど一般人に印象の強いものはない。暴力団と警察との悶着ほど、政治運動の宣伝として効果的なものはない。ヒットラーの狙いは其処にあった」とした小林は、「だが、彼はその本心を誰にも明かさなかった。「突撃隊」が次第に成長し、軍部との関係に危険を感ずるや、細心な計画により、陰謀者の処刑を口実とし、長年の同志等を一挙に合法的に謀殺し去った」と続けている。
さらに、ヒトラーの人生観を「人性の根本は獣性にあり、人生の根本は闘争にある。これは議論ではない。事実である」とした小林は、「獣物達にとって、他に勝とうとする邪念ほど強いものはない。それなら、勝つ見込みがない者が、勝つ見込みのある者にどうして屈従し味方しない筈があるか」と書いて、ヒトラーの「弱肉強食の理論」を効果的に紹介している。
さらに小林はヒトラーの言葉として「大衆は理論を好まぬ。自由はもっと嫌いだ。何も彼も君自身の自由な判断、自由な選択にまかすと言われれば、そんな厄介な重荷に誰が堪えられよう」と書き、「ヒットラーは、この根本問題で、ドストエフスキイが「カラマーゾフの兄弟」で描いた、あの有名な「大審問官」という悪魔と全く見解を同じくする。言葉まで同じなのである。同じように孤独で、合理的で、狂信的で、不屈不撓であった」と続けている。
この表現はナチズムの危険性を鋭く指摘したフロムが『自由からの逃走』(日高六郎訳、東京創元社)で指摘していた記述を思い起こさせる。この本がすでに1951年には邦訳されていたことを考慮するならば、小林がこの本を強く意識していた可能性は大きいと思える。
しかしその結論は正反対で、小林秀雄はヒトラーの独裁とナチズムが招いた悲劇にはまったく言及していないのである。
関連記事一覧
「ヒットラーと悪魔」をめぐって(1)――書評『我が闘争』と「ヒットラーと悪魔」
「ヒットラーと悪魔」をめぐって(3)――PKO日報破棄隠蔽問題と「大きな嘘」をつく才能
「ヒットラーと悪魔」をめぐって(4)――大衆の軽蔑と「プロパガンダ」の効用
(2017年9月17日、改訂し関連記事のリンク先を追加。2019年9月11日、改訂と改題)