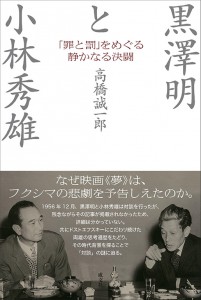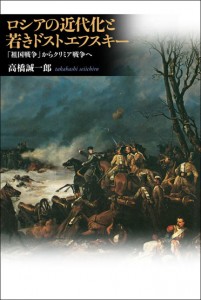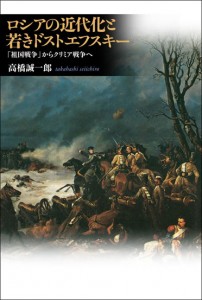(書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)
前回は『若き日の詩人たちの肖像』の全体像を確認するために、アリョーシャと呼ばれるドストエフスキーの愛読者の変貌と『罪と罰』を中心に戦争と文学との関わりを考察していた『英雄と祭典』の著者の思想との関連に焦点をあてて、この長編小説の最後までの流れを考察した。
今回はこの長編小説を初めからゆっくりと読み直すことで、第一章の題辞として『白夜』の冒頭の文章を引用していた堀田善衛が小説において『罪と罰』についてどのように言及しているかを確認したい。
* *
「扼殺者の序章」と題された序章では、序章の冒頭で、「機を見て僕はお前を扼殺したらしい」というフレーズを含む「潟の記憶」と題する詩を載せた著者は、それが、引き揚げ船で上海から帰って来たばかりの一九四七年に書かれたことを明かしたあとで、「記憶を扼殺」した感覚をこう記している。
「自身の指と手のひらに、扼殺者としてのうずくような感覚が、…中略…いまもなお指と手のひらの皮膚になまなましく生きて残っている。男がしめ殺したものが何と何と何であったか」。
その後でこの長編小説でも「冬の皇帝」という呼び名で登場する詩人・田村隆一の「おれはまだ生きている/死んだのはおれの経験なのだ」という句を含む「一九四〇年代夏」という詩が紹介されている。これらの文章からは作家の司馬遼太郎が「鬼胎」と呼んだ昭和初期の異常な時代が、ひしひしと観じられる。
ただ、第一章の題辞に「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた。」という言葉で始まる『白夜』のロマンチックな文章が置かれることによって、暗闇が少しやわらぎ小説空間が広がる。
そして、その冒頭では「文学少年」というよりは「音楽少年といったものであった」少年が上京した晩に聞いた「ボレロ」の強烈な印象で身体が反応してしまったという、音楽の力や生命の不思議さが観じられるエピソードが記されている。
しかも、堀田は暗く重苦しい時代をしぶとく生き、「少年」から「若者」を経て「男」となる主人公を時にユーモアを交えて描いており、読者は彼とともに暗い時代を追体験することになるが、それは陰惨なリンチの問題をテーマとした長編小説『悪霊』を、「時に爆笑を誘うほどのユーモアをともなって」描いていたドストエフスキーの手法とも通じているだろう(下巻、102頁)。
少年の生家は「北国の小さな港町に、二百ほどのあいだ、北海道と大阪をむすぶ、いわゆる北前船の廻船問屋をいとなんで来た家」で、少年が生まれた1918年に、「港の対岸にある滑川の女房連が発起」した米騒動が起きていた。しかし、その騒動が少年の生まれた港にも「波及してきた際には、かつて「明治の民権自由運動の壮士たちの後援者でもあった」曾祖母は、「直ちに家の者、店の者の先頭に立っててきぱきと指示をして」、民衆に粥を配って騒ぎを収めていた。
こうして、父が「古い家柄というものと名とをつかって県会議員をやったりして」おり、選挙の際には「政府与党でない者の選挙違反をつくり上げる義務があった」刑事たちが、「電話その他の盗聴に来ていた」のを見ていた少年は法学部政治学科の予科に入っていた。
このような主人公の設定は『罪と罰』や『白痴』を理解する上でも重要だろう。『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』で分析したように、これらの長編小説を主観的に分析した小林秀雄の解釈では、ドストエフスキーの作品の骨格をなしている「憲法」や法律、裁判の問題などや強者による弱者の蔑視などの問題は読者の視野には入ってこない。
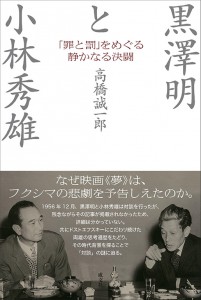 (←画像をクリックで拡大できます)
(←画像をクリックで拡大できます)
1954年のエッセー「二つの衝撃」で「裁判を扱う偉大な作品」として『ベニスの商人』『赤と黒』『復活』などとともに『罪と罰』を上げていた堀田善衛は、「キリストもまた、裁判について痛烈なことばをのこし、また自ら十字架に罹っている」と記していた(『堀田善衛全集』第15巻、78頁)。
『罪と罰』では裁判のシーンはエピローグで簡単に描かれているのみなので、むしろ『カラマーゾフの兄弟』が挙げられるべきだと思うが、主人公を法学部の元学生だったとした『罪と罰』でも、弁護士や「司法取調官」などの登場人物をとおして法律の問題点が鋭く描き出されている。
法学部政治学科の学生を主人公とした『若き日の詩人たちの肖像』でも、主人公の『罪と罰』観が記されているばかりでなく、特高警察や検事などが重要な役割を担っており、法律だけでなく拷問などの問題が考察の対象となっている。
たとえば、第一部の冒頭近くでは、大学の保証人になってもらうために従兄のもとを訪ねて行き、「幼いときからなじんでいたこの従兄の表情の険しさに、ほとんど声を出さんばかりに愕いた」と描かれている。
このエピソードを読む現代の読者も拷問の陰惨さに激しく驚かされると思うが、日本の山県有朋などの政治家はロシア帝国の宗教政策や教育政策をモデルの一つとしていた。それゆえ、その強大なロシア帝国が革命によって打倒されたあとでは、大日本帝国の崩壊を怖れて共産党を根絶やしにしようとしていたのである。
「日本共産党の関西関係の、かなりに重要なポストにいたらしかった」従兄は、「思想犯ということで、長く警察にとめおかれ、」「怖ろしい拷問」を三週間も連日受け、「少年の母が司法省の高官の紹介をもって面会に行ったとき、従兄の顔は腫れあがり、手には真新しい軍手をはめさせられていた」が、それは「指、爪、指のつけ根をいためつけられていたからであった」。
そして著者は、母が少年にそのことを詳しく語ったのは、「母にしても、あまりにむごい、警察の非道に就いて、誰かに何かを訴えたかったのかもしれない」と続けた。
それは1918年の米騒動の際には「騒ぎのつづいたあいだじゅう、ずうと人民に粥を配って騒ぎをおさめた」曾祖母が、貧民を助けずに騒動を拡げた問屋たちを「滑川の者(もん)はダラやがいね。心得のないことをしてしもて」と批判し、「問屋というものには問屋としての心得があることをさとした」ことにも通じているだろう。
著者は従兄の面変わりについて、「人はたとえ肉体的には死ななかったとしても、彼のなかで何かが死ぬ、殺される、あるいは殺す、ということがあるものなのであるらしい。/それがそういうふうにしてわかったことは、少年の心の底に、暗く彩られた、ある深い部分をのこした」と記している(27頁)
そして、2・26事件後の6月号に掲載された河合栄治郎の論文が「バッテンばかりで、さっぱり見当もつかなかった」と記されていたように(53頁)、政府を批判する論文への検閲が徐々に厳しさを増していた。
ヒトラーが独裁的な権力を獲得した1933年の2月に『蟹工船』を書いて政府の方針を真っ向から批判していた小林多喜二は拷問で死亡していたが、ドイツではユダヤ人の虐殺のことが一般の民衆には知られていなかったように、日本でも一般大衆は警察による拷問は共産党員に対してのみ行われていたように考え、自分とは関わりの無いかのように処していたように思われる。
このような時期に『罪と罰』を読んで「殺人の場面が、殺人者のラスコリニコフも、また殺される高利貸の婆さんの顔も、またその現場の全体もが黄色一色に塗りつぶされていることに、小説作家というものの心配りの仕方を読みとっていたのである」と書いた主人公もまだこうも記していた。
「『罪と罰』を読んでラスコルニコフは言うまでもなく、あのスヴィドリガイロフなどという怪異な人物は、東京で言えば必ずや大川の向う住んでいる筈」と考えて、「川向うでしばらくを暮した」が、彼らに似た人物とは会えなかったために「あれはやっぱりドストエフスキーという作者の頭のなかの闇でだけ生きている」のかと考えていた。
その彼が『罪と罰』の登場人物に似た人物と会うことになるのは、「理由の説明も何もなく、物品のように若者はどさりと淀橋署の留置場へ放り込まれた」後のことであった。
* *
2・26事件の余波はなかなか収まらなかったが、主人公がたびたび引っ越しした部屋の一つは、夫が死刑になったあとで軍首脳部の弾劾を続けていた2・26事件の首謀者の未亡人の隣室であった。
そのために右翼係りの刑事がこの「夫人を監視するために隣室の住民である若者の部屋」に、「ご迷惑さんです……」といいながら入り込んで、隣室の模様に耳をこらして」いたが、本人の不在中に家捜しされて部屋に隠していたマルクスやレーニンの本のことを知られたのである。
朝早くに乱暴にアパートの部屋をノックされて、戸を開けると「服を着ろ、警察の者だ」とせき立てられた主人公は、そのまま「ズボンのベルトに腰縄をつけられ」て下北沢の下宿から淀橋署まで連行されたのである。
そのことを記した著者はすでに同級生の二人が授業中に呼び出されて一人が留置場で亡くなっていたことなども記した後で、小林秀雄が訳したランボオ詩集中の「おお城よ/季節よ」というフレーズについて、「張り詰めた呼びかけの、その氷の様に澄み渡った美しさも、これもまたランボオの、詩人として死を賭けていたればこそのものではなかったか」と続けていた。
そして、自分の「氷の様に澄み渡った」という言葉を思い出したことで、「不意に、芥川龍之介の遺書である「或旧友へ送る手記」のことを思い出して勃然たる怒りを感じた」と書き、「所謂生活力と云ふものは実は動物力の異名に過ぎない」で始まる文章を引用している。
「僕の今住んでゐるのは氷のやうに透(す)み渡つた、病的な神経の世界である。僕はゆうべ或売笑婦と一しよに彼女の賃金(!)の話をし、しみじみ「生きる為に生きてゐる」我々人間の哀れさを感じた。…中略…君は自然の美しいのを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう。けれども自然の美しいのは僕の末期(まつご)の目に映るからである。」(159頁)
この文章の後で著者は「何を言ってやがんだ!…中略…いかにお前さんが、たしかに敢然と自殺したからと言って、こんなことを言う権利があるのか!」というこの文章に対する主人公の激しい反発を記している。
小林秀雄が訳したランボオの詩の紹介に続いて芥川龍之介の遺書に対する怒りが記されているこの箇所からは、堀田もまた小林ととともに芥川龍之介を批判しているようにも読める。しかし、「詩と死」についての考察はこの小説に一貫して流れており、小説では「澄江君」と呼ばれる芥川龍之介の遺児・芥川比呂志との出会い以降は遺書に対する思いが少しずつ変化する一方で、なぜここでランボオが引用されていたかも後に明らかになる。
本稿の視点から興味深いのは、この留置所に13日間拘留された主人公を釈放する前に「我が国は皇国であって、国体というものは」などと説教した中年の男が「自分の言っていることを、自身でほとんど信じていないということは、明らかに見てとれた」と記したあとで、「『罪と罰』に出て来る素晴らしく頭がよくて、読んでいる当方までが頭がよくなるように思われるあの検事のことがちらと頭をかすめた」と続けていることである(170頁)。
この文章は昭和初期の日本の政治状況が、憲法のなかった帝政ロシアでも「暗黒の30年」と呼ばれたニコライ一世の治世下と急速に似てきたことをよく物語っているように思われる。すでにこの頃には大学でも「少年が入る前年に、予科生は髪の毛を切れ、坊主頭になれ、つまりは兵隊頭になれという命令」が出ていた。
さらに、「ヨーロッパで戦争」が始まると「東京の街々では、喫茶店や映画館で、また直接の街頭でさえ、官憲によって“学生狩り”というものが行われていた。ぶらぶらしている学生を、遠慮会釈なくひっとらえて一晩か二晩留置所に放り込み、脅かしておいて放り出す。そういう無法が法の名をおいて」行われるようになったのである。
その理由について著者は、「それが何の用意であるかといえば、答は今の日支事変よりももっと大きな戦争という、そのこと以外にありそうもなかった」と記していた(219頁)。
実際、太平洋戦争の戦況が厳しくなる学生たちも戦場へと駆り出されて230万ほどの戦死者を出し、しかも「どの戦場でも戦死者の6~8割が『餓死』という世界でも例がない惨状」で亡くなることになったのである。

出陣学徒壮行会(1943年10月21日、出典は「ウィキペディア」)
アメリカ軍機による空襲が行われるようになると、「文化系学生の徴兵猶予がとり消されるのは、もう目前なのだ」と語られるようになったことを記していた著者は〔下、208〕、学徒出陣の壮行会に主人公が遭遇した際のことを詳しく描いている〔下、374~376〕。
「競技場からは、吹奏楽をともなった男女の大合唱による、荘厳な『海行かば』が聞こえて来た。…中略…男は傘をさして樹陰のベンチにいたのであったが、競技場の入口あたりから行進が町に出はじめたらしかったので立って道のところまで出て行くと、行進は学生たちのものであった。」
「男は何度か突きとばされて、はじめて、これが出陣学徒壮行大会であったことに納得が行った。行進して行く学生たちは、いずれもみな唇を噛み、顔面蒼白に、緊張をしている、と見えた。法文系は一切廃止されてしまい、全部が全部、丙種不合格までが一斉に十二月一日に入営することになったのである。男の眼に泪が溢れてくる。」
そして、「こういう学生たちまでをお召しだのなんだのという美辞麗句を弄して駆り出して、いったい日本をどうしようというのだ、という、どこへもぶっつけようのない怒りがこみあげて来る」と主人公の思いを記した堀田は、鎌倉初期に思いを馳せながら「鴨長明がルポルタージュをしていたような事態が刻々に近づきつつあるように予感される。『方丈記』は実にリアリズムの極を行く、壮烈なルポルタージュであった。」と続けていた。
 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)
(2017年12月24日、加筆)