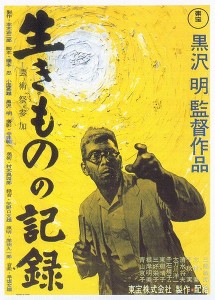前回の記事〈「共謀罪」法案の強行採決と東京オリンピック開催消滅の可能性(1)――1940年との類似性(加筆版)〉では、安倍首相が「共謀罪 成立なしで五輪開けない」と語ったことの問題点を考察するとともに、国際連盟が派遣したリットン調査団の報告の後で日本が国際連盟から脱退していたことについてもふれた。
* * *
今日の「こちら特報部」(「東京新聞」)は、ベルリン五輪(1936年)を徹底して「政治利用」し、「景気浮揚、治安の強化、再軍備」など「国威発揚」の場としたナチスドイツと、「改憲」や「共謀罪」法案でオリンピックを政治利用し、「復興を演出」している安倍政権の手法との「際立つ類似点」を見事に示している。
すなわち、「平和愛好家を自称していた」ヒトラーは「五輪の期間中だけ国内でユダヤ人排斥の看板」を取り外すなどの対策をとることで、「ユダヤ人迫害などはうそだ」と「世界に向けて宣伝」していた。
ベルリンオリンピックの開会式でオリンピック旗に敬礼するアドルフ・ヒトラー。1936年8月1日、ドイツ。出典はサイト「ホロコースト百科事典」より)
そのために「五輪憲章は大会の政治利用を禁じている」が「その原則に触れかねない事態」がおきたのが、「昨年八月、リオ五輪の閉会式で安倍政権が人気キャラクター「マリオ」にふんして登場した一幕」だったのである。
この件については「日刊ゲンダイ」が昨年年8月22日の記事ですでに次のように批判していた。
「ちょうど80年前、ナチス政権下のドイツで開かれたベルリン大会で、ヒトラーは国威発揚のため自ら開会宣言を行った。オリンピックの政治利用の最悪のケースとして歴史に刻まれています。安倍首相もセレモニーに登場することで“東京五輪まで首相を続けるぞ”とアピールしたのです。再来年9月までの自民党総裁任期を延ばそうという動きと連動した姑息な延命PRです」(自民党事情通)/ ヒトラーといい安倍首相といい、独裁者がやることはソックリだ。」
「五輪憲章は大会の政治利用を禁じている」が、リオ五輪の閉会式で安倍前首相は、人気キャラクター「マリオ」にふんして登場していた。https://t.co/bUwsAAj7Gzフクシマの現実から国民の眼を逸らしている。→ 東京新聞:「安倍マリオ」などリオ演出費 総額12億円:東京新聞 https://t.co/tVbTaqJ8II https://t.co/L1ax78TXlf pic.twitter.com/fPwBaWzFxb
— 高橋誠一郎 (@stakaha5) November 9, 2022
* * *
安倍首相の政治利用の「代表格が改憲だ」とし、首相が三日に「夏季のオリンピックが開催される二〇二〇年を日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけ」とすると語ったことを指摘した今日の「こちら特報部」はさらに、こう続けている。
「そもそも五輪招致段階のIOC総会で『汚染水は完全にコントロールされている』と事実に反するアピールをし、現在も続く被災者たちの苦悩も「復興五輪」の名目によって、打ち消そうとしている」安倍首相は、「自らの責任も問われている福島原発事故も、五輪を機に『過去』のものにしたいようだ」。
* * *
開催地の新聞であるにもかかわらず「東京新聞」がこのような記事を載せるのは勇気のある決断であり、五輪に向けたこれまでの努力を無駄にしないためには、「五輪憲章」に違反して開催権を取り上げられる危険性のある安倍政権に代わる次の政権を一刻も早くに打ち立てることが必要だろう。
「コロナ禍の中で行われたオリンピックを振り返る」
https://t.co/ntjrrowFoF
ナショナリズムを高揚して国家観の対立を煽っている国旗の掲揚や国歌の斉唱をやめることが出来ないならば、オリンピックは平和なスポーツの大会とはいえないだろう。 pic.twitter.com/cfFbbEaEcD— 高橋誠一郎 (@stakaha5) December 31, 2021
(2023/01/17、ツイートを追加)