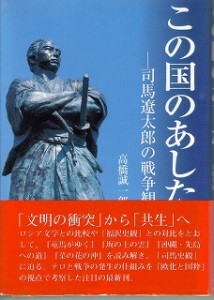はじめに 堀田善衞と三島由紀夫のチェコ事件観
ロシア軍のウクライナ侵攻というニュースを聞いて、最初に思ったことはソ連軍がワルシャワ条約五カ国軍とともに民主化運動を展開していたチェコスロヴァキアに侵攻した1968年のチェコ事件のことでした。
むろん、ソ連の政権下で起きたチェコ事件とソ連崩壊後の今回の侵攻とでは性格も大きく異なります。しかし、前回考察したように、西欧列強に滅ぼされないためにはナポレオンに勝利したロシア帝国を盟主とする「全スラヴ同盟」を結成して対抗すべきだと主張したダニレフスキーの考えは、露土戦争以降、ロシア正教を国教としていたロシアで広まりました。また、革命政権が誕生した後の1918年に行われた日本やアメリカなどの連合国によるシベリア出兵で多くの死傷者を出し、この戦争以降も常に外国からの圧力を感じていたソ連や、ソ連時代の情報将校だったプーチン大統領にもその「恐怖」は受け継がれているように思われます。
他方で、ゼレンスキー大統領が今回のロシアの侵略を「真珠湾攻撃」にたとえたことが日本の右派の怒りを買っているようですが、ダニレフスキーの歴史理論は昭和初期の「大東亜共栄圏」の思想にも影響を与えており、今回のドネツク・ルガンスクの建国を図ったロシアのように満州国の建国をしたことなどから経済制裁を受けた日本は戦争を開始する理由として、A・B・C・D包囲網を挙げていたのです。
ところで、ワルシャワ条約5カ国軍が武力で8月21日にはチェコスロバキア全土を占領下においたことを知った堀田善衞は、1956年のハンガリー事件を連想して、「単純な怒りとともに、呆れてしまい、また同時に、彼らのやりそうなことをやったものだ、という感をもったものであった」と記しています。
しかし、堀田は丸山眞男や久野収らが提唱したチェコ事件をめぐる抗議声明に署名しませんでした。それは、9月20日から25日までタシケントで開催されたアジア・アフリカ作家会議の一〇周年記念集会に出席して、「長年の友人である」ソ連の作家たちが「どんな顔をして何を言うか、このことだけをでもたしかめてみようと思い立った」からでした。
つまり、この時の事件に堀田はまず現場に行って観察しようという鴨長明と同じような精神で対応していたのです。こうして、9月19日に日本を出発した堀田は記念集会に参加した後で、ヘルシンキ、ストックホルム、ロンドン、パリ、プラハ、ウィーン、ベルリン、ブラティスラバなどヨーロッパ各地を訪問して、ことに不幸なチェコスロヴァキアには前後二回、約1カ月滞在して、さまざまな人々と話し合い、約3カ月後の12月24日に日本に帰国しました。その間に見聞きしたことや考えたことを詳しく記したのが堀田善衞の『小国の運命・大国の運命』です。
一方、『文化防衛論』に収められた「自由と権力の状況」という論考でチェコ事件について考察した三島由紀夫は、「学生とのティーチ・イン」でもこの問題に言及しており、この事件が「三島事件」を起こすきっかけの一つになっていたことが感じられます。
それゆえ、本稿ではまずチェコ事件をとおして「政治と文学」の問題について考察した三島の「自由と権力の状況」を簡単に見た後で、昭和初期に流行った小林秀雄の『罪と罰』論にも注意を払いながら、三島の革命観とテロリズム観を考察します。
そして、最後に堀田の『小国の運命・大国の運命』を詳しく分析することにより堀田の視野の広さと考察の深さを示すことにします。
そのことによってウクライナ危機に際しての維新や自民党安倍派の対応と、チェコ事件に対する三島の反応との類似性を明らかにし、報道や言論への圧力を徐々に強めながら昭和初期と同じように戦争へと急速に傾斜している現代日本の危険性を示すことができるでしょう。
1,「政治と文学」の考察――「自由と権力の状況」
三島は「自由と権力の状況」という論考の冒頭でチェコの問題への強い関心の理由をこう記しています。
「チェコの問題は、自由に関するさまざまな省察を促した。それは、ただ自由の問題のみではなく、小国の持ちうる、政治的なオプションの問題でもある。それは、力と力の世界の出来事であると同時に、イデオロギーの対立の中に、いかに身を処しうるかという微妙な戦術の心理的出来事でもある。事、表現の自由に触れるかぎり、「政治と文学」の問題も、ここにドラマティックなモデル・ケースを作り出した。それに比べると、日本で語られている政治と文学の対立状況などは児戯に類する。極端に言えば、あそこでは文学と戦車との対立が劇的に演じられたのである。」(『文化防衛論』、ちくま文庫、119頁、以下頁数のみをかっこ内に記す)。
そして、「安保条約下の日本もアメリカの大国主義に対して警戒し、これを排除し、あるいはこれに抵抗しなければならないと教えるであろう」(123)という意見も紹介した三島は「大国の強大な武力の前には、多少の自衛上の武力など持っても何にもならない。だから非武装中立こそは、国を護る最上の良策である、という考えの論理的矛盾は明らかである」(125)としています。
そして、三島はかろうじて核戦争を回避したキューバ危機後の世界のあり方をも批判して、「われわれにけじめを失わせ、弁別を失わせたものが、冷戦と平和共存の論理」(129)であると結論していました。
2,「みやび」とテロリズム――「文化防衛論」
「文化防衛論」で「『みやび』は、宮廷の文化的精華であり、それへのあこがれであったが、非常の時には、『みやび』はテロリズムの形態をさえとった」とした三島は、「天皇のための廠起は」「一筋のみやび」を実行した桜田門の変の義士たちのように、「容認されるべきであった」と主張したのです(74)。
ここからは幕末に頻発した「天誅」という名前のテロを称賛する姿勢が感じられますが、このような三島の主張とは正反対の主張をしたのが、『竜馬がゆく』で主人公の坂本竜馬を、殺すことを嫌う武士として描いたにもかかわらず、「新しい歴史教科書をつくる会」から高く評価されたことで誤解されることになった司馬遼太郎でした。
ベトナム戦争や学生紛争の時期にこの長編小説を読んだ私は、「天誅」を「正義の殺人」とする思想に『罪と罰』に描かれている「非凡人の理論」と同じような傲慢さを感じて、司馬作品にも熱中しました。あまり知られていないようですが、幕末の「神国思想」が「国定国史教科書の史観」となったと指摘した司馬は、「その狂信的な流れは昭和になって、昭和維新を信ずる妄想グループにひきつがれ、ついに大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」と明確に記していたのです(『竜馬がゆく』文春文庫)。
一方、桜田門外の変を「一筋のみやび」と解釈した三島は、そのような視点から「西欧的立憲君主政体に固執した昭和の天皇制は、二・二六事件の『みやび』を理解する力を喪っていた」(75)と厳しく批判していました。
たしかに、二・二六事件で処刑された磯部一等主計の視点から描いた『英霊の聲』などにおける三島由紀夫の主張は、亡くなった者たちの無念の思いも伝えて迫力がありますが、しかし、情報将校だったプーチンと同様の「国粋主義」的な視野の狭さを感じます。
一方、堀田善衞は誕生したばかりの革命政権を打倒も意図して日本がアメリカなどの連合国と共に行ったシベリア出兵を描いた『夜の森』で、1919年には日本が併合した韓国で三・一独立運動が起きていたことや、この出兵ではすでに満州国に先立って傀儡国家の樹立もはかられていたことなどを記しています。
一方、三島の視野には、併合された韓国や「五族協和」というスローガンで樹立されながら、土地を奪われた満洲の人々などの苦悩や不満は入ってきていないのです。
3,「決闘」と「暗殺」をめぐる議論 と『罪と罰』の解釈
「学生とのティーチ・イン」でも三島はチェコの民主化運動についてこう批判しています。「いよいよ世間は米ソ二大強国の共存時代に入ってきた、これなら大抵のことをやったって片一方が手を出すわけはない、キューバ事件もそうだからあれでもそうだろう。これはいまがやり時だ、ここで両方のいいところをちょっと取ってやれば、共産主義体制に属しながらしかも自由というものをアメリカ並みに味わえるのじゃないか、こうしたら世界中に一番いいお手本を示してやれる、という山気があったに違いない。こんな山気に私は同情しない」(288)
しかし、私が「学生とのティーチ・イン」で一番興味を持ったのは、学生Dの「三島先生はさきほど、暗殺的行為は一つの思想が一つの思想を殺すことで、これは決闘である、決闘という行為は非常に美しいものであると、賛美なさいましたけれども、(……)暗殺というのは非常に卑怯な行為だと思うのです」(202)という核心を突いた質問に対して、三島が少したじろぎながら、こう答えていたことです。
「決闘との比較は多少当を得ていなかったと思いますけれども」としながらも、警備がきわめて厳重なことを考慮するならば、「だからプラクティカルな問題として、暗殺が卑怯に見えても、暗殺という形をとらざるを得ないと思うのです」(203)。
こうして三島は学生の批判を受け入れて、「暗殺が卑怯」であることは認めつつも「暗殺という形」の殺人を認めているのです。
このような主張は一見、不合理で説得力を欠いていると思えます。しかし、なぜ三島がそのような主張をしたのかを考えると、二・二六事件が起きる2年前の1934年に小林秀雄が書いた「『罪と罰』についてⅠ」の構造が浮かんできます。ここで「超人主義の破滅とかキリスト教的愛への復帰とかいふ人口に膾炙したラスコオリニコフ解釈では到底明瞭にとき難い謎がある」とした小林は、「悪人」と見なした「高利貸しの老婆」とその義理の妹を殺した主人公のラスコーリニコフには、「罪の意識も罰の意識も」ついに現れなかったと断言していたのです(全集、6・45)。
つまり、「悪人」と見なした「高利貸しの老婆」を殺害しても「罪の意識」が現れなかったと解釈するならば、「政府要人」を「悪人」と見なして殺した青年将校たちにも「罪の意識も罰の意識も」現れるはずはなかったのです。
このような解釈は、我田引水のように思える人もいるかも知れませんが、「文化防衛論」で「社会主義が厳重に管理し、厳格に見張るのは、現に創造されつつある文化についてであるのは言うまでもない。これについては決して容赦しないことは、歴史が証明している」と記した三島が、「ソヴィエト革命政権がドストエフスキーを容認するには五十年かかってなお未だしの観があるが」と続けています。
この記述からはドストエフスキーへの三島の深い関心がうかがえ、当時、流行していた小林秀雄の『罪と罰』論からも影響を受けたことが感じられるのです。
→「耽美的パトリオティズム」の批判――「美神との刺違へ」という表現と林房雄の「玉砕」の美化
4,復讐と絶望の分析と人類滅亡の危険性――『罪と罰』から『白痴』へ
神西清は三島由紀夫論「ナルシシスムの運命」で、「戦争は確かに、彼の美学の急速な確率を促した。(略)美の信徒は、今やはっきりと美の行動者になったからである」と記していました(『神西清全集』第6巻、484頁)。
実際、三島由紀夫はデビュー作といえる『仮面の告白』のエピグラフで、「美の中では両方の岸が一つに出合つて、すべての矛盾が一緒に住んでゐるのだ」という『カラマーゾフの兄弟』のセリフを引用していたのです。
これらのことを紹介した宮嶋繁明氏は、三島にとって「美」が如何に重要な理念として確立したかに注意を促した神西が、さらに「美の殉教者が一変して、美による殺戮者になったのだ。彼は美という兇器をふりかざして、あらゆる敵へ躍りかかって行った」と続けて、「三島事件」を予見するような考察も行っていたことに注意を促しています(『三島由紀夫と橋本文三』弦書房、2011年、46~47頁)。
ドストエフスキーにおける美の問題は『白痴』の理解にも深く関わりますが、先にみたように、「学生とのティーチ・イン」では「暗殺」の正当性を主張するために「決闘」にも言及することで「暗殺」を「美化」しようとした三島がかえって学生から卑怯だと指摘されていました。
実は、この前段階で三島は「私はアウシュビッツを認めるわけじゃない。私はナチスのああいうやり方を認めるわけじゃない。/私があくまでそこを分けたいと思うのは、人間が全身的行為、全身的思想で、人と人とぶつかり合うという決闘の思想というものが私は好きなんです」と語っていました(196)。
さらにスターリンが行った「粛清」とも比較することで、「あれだけ警備の多勢いるところで、死刑を覚悟でやるというのは大変だと思う。私は人間の行動というのは、行動のボルテージの高さで評価する」と語った三島は、一対一で行う「勇気」にも言及して「暗殺」を正当化していました。
そのような人物の一人がドストエフスキーが『罪と罰』で描いたラスコーリニコフであり、 「非凡人の理論」を考え出して、「悪人」と見なした「高利貸しの老婆」を殺害したのです。こうして、ドストエフスキーは「小説という方法を生かして「非凡人」の理論を、「他者」の殺人という極限的な事態の中で、主人公の身体や感情の動きをもきわめて具体的に分析しながら考察することにより、フロイトなどに先だって絶望の諸相や人間心理の無意識的な深みにまで迫り得た」のです(『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』刀水書房、9頁)。
『罪と罰』では老婆とその義理の妹を殺害したラスコーリニコフの更生が、エピローグでの「人類滅亡の悪夢」を見た後で示唆されていました。
一方、『白痴』ではスイスでの治療から戻ったムィシキンは出会った絶世の美女ナスターシヤの内に深い「絶望」を見抜いて、なんとか癒そうとしたのですが果たせずに終わります。「決闘」の問題を「復讐」のテーマともからめて考察しているこの長編小説では(拙著『黒澤明で「白痴」を読み解く』成文社、176~180頁)、さらにより深い「絶望者」が描かれています。
それが自分の余命が長くないことを知らされたイッポリートです。自殺をしようとして失敗していた彼は、自暴自棄となり「もしもいまこのぼくが急に思いたって、好き勝手に十人ばかりも人を殺したり」、あるいは「世の中で一番ひどいと思われることをしでかしたりした」らどうだろうかと問いかけていました。
「つまり、ラスコーリニコフの「非凡人の理論」では、他者は軽蔑すべき対象としてでも存在したのにたいし、「自己」の可能性を見失って「絶望」したイッポリートにとっては、「他者の生命」も意味をなさなくなってしまって」いたのです(前掲書、217頁)。
この意味で興味深いのは、三島との討論の際に学生Eが、次のような鋭い質問を投げかけていました。 「たった一人でこの世の中を全(すべ)て破壊できると考える人間が、自分の考えを貫こうとして、この全世界を破壊するしかない」と考えて、「合理的に、自分の自殺と他の全世界の人々を滅ぼすということを同時にやったとして、それで全世界を滅ぼすことになっても、ボルテージの高まったその個人に意義はあるのですか。それを伺いたいのです」(206)。
この質問は私が『白痴』のイッポリート から受けた印象とも重なっていました。 彼が考えたのは「無差別殺人」のことでしたが、核の時代の現代においてそれは核兵器の使用になると思えるからです。
こうして、「憲法」を変えるために三島由紀夫が東部方面総監を人質にして自衛隊のクーデターを呼びかけ、その後、割腹自殺をした事件から私は激しい衝撃を受けたのですが、その一因は 椎名麟三が自殺した芥川龍之介が遺書の『或旧友へ送る手記』で、「僕の手記は意識している限り、みずから神としないものである」と記していることに注意を促していたことにもありました。
つまり、「三島事件」を知った時には、三島が芥川とは反対に「みずから神」となるために自刃をしたことに強い反発を覚えたのです。
その後、この衝撃的な事件の印象は薄れましたが、その関心は「昭和維新」を掲げた2・26事件に遭遇した若者を主人公とした堀田善衞の自伝的な長編小説『若き日の詩人たちの肖像』の考察 や、原爆パイロットをモデルにして原水爆の危険性を考察した『審判』の考察へと向かうことになりました。
次回の「チェコ事件でウクライナ危機を考えるⅡ」では、ドストエフスキーについての言及もある堀田善衞の『小国の運命・大国の運命』を詳しく考察することにより、彼の社会主義観や文明観に迫りたいと思います。
(2022年3月21日、加筆、改訂)


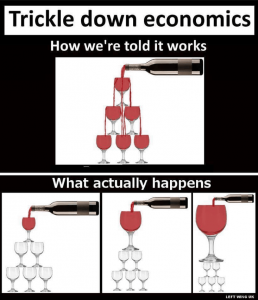


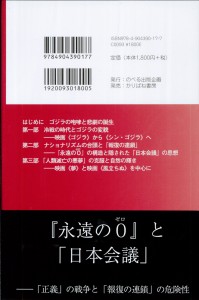

![天空の城ラピュタ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/618ZeQcWG7L._AC_UY327_QL65_.jpg) (「アマゾン」より)
(「アマゾン」より)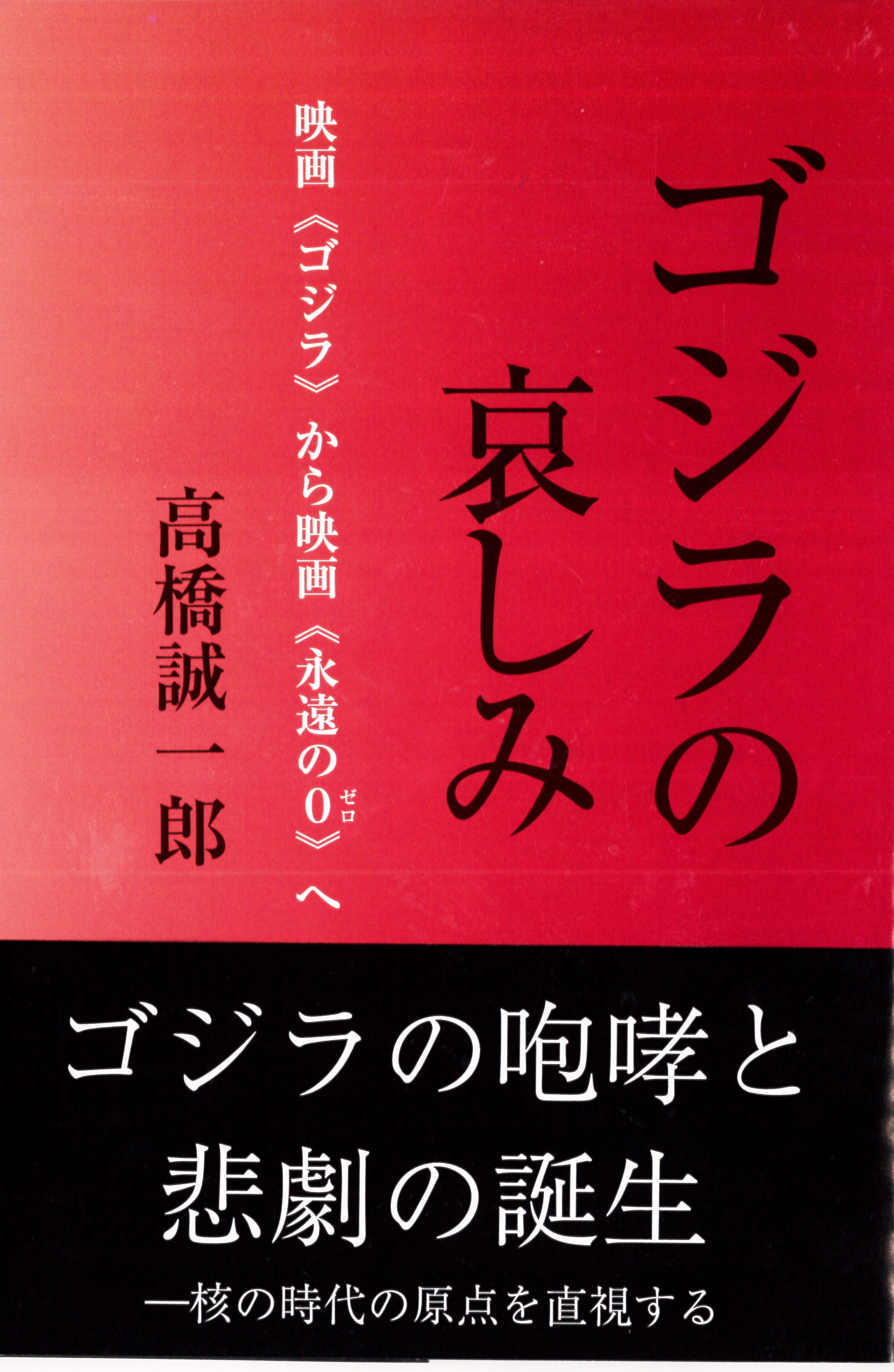


 (ナチス・ドイツの焚書)
(ナチス・ドイツの焚書)