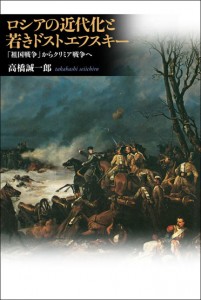1,若き主人公と『白夜』冒頭の文章
第一章の題辞には「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた」という文章で始まる『白夜』の冒頭の言葉に続いて、祈りにも似た次のような言葉も引用されていた。
「空は一面星に飾られ非常に輝かしかつたので、それを見ると、こんな空の下に種々の不機嫌な、片意地な人間が果して生存し得られるものだらうかと、思はず自問せざるをえなかつたほどである。これもしかし、やはり若々しい質問である。親愛なる読者よ、甚だ若々しいものだが、読者の魂へ、神がより一層しばしばこれを御送り下さるやうに……。」(米川正夫訳)
しかし、泥沼の日中戦争に続いて英米とも開戦に踏み切った日本は、初戦の真珠湾攻撃で華々しい戦果を挙げたが、「特殊潜航艇による特別攻撃」に参加した二十歳前後の若者全員が、後の「神風特攻隊」を予告するかのように戻らなかったという事態も起きていたことを知った時に、若者は「腹にこたえる鈍痛を感じ」る(下巻、92頁)。
そして、長編小説の終わり近くで召集令状が来たことを知らせる実家からの電報が届き、「警察で殺されるよりも、軍隊の方がまだまし」と感じた男は、「新橋サロンの詩人たちにも、なにも言わないことにした」とし、『白夜』の文章にについてこう記すことになる。
「郵便局からの帰りに空を仰いでみると、冬近い空にはお星様ががらがらに輝いていたが、そういう星空を見るといつも思い出す、二十七歳のときのドストエフスキーの文章のことも、別段に感動を誘うということもなかった。なにもかもが、むしろひどく事務的なことに思われる。要するにおれは、あの夢のなかへ、二羽の鶴と牡丹の花と母の舞と銀襖の夢のなかへ死んで行けばいいというわけだ、と思う。」
2,「謎」のような言葉――主人公の『白痴』観
注目したいのは、12月9日の夕方に若者の家を訪れて、真珠湾攻撃の成果を「どうだ、やったろう」と誇った特高刑事をそのまま返すのが業腹で彼らを尾行していた若者は、「成宗の先生」(堀辰雄)と出会って立ち話をしていた際に、長編小説『白痴』に言及していることである。
すなわち、堀田善衛は特高警察の目つきから「殺意に燃えたラゴージンの眼」を思い出し「ほとんどうわの空」で、「ランボオとドストエフスキーは同じですね。ランボオは出て行き、ドストエフスキーは入って来る。同じですね」(下巻、83頁)と主人公の若者に「謎」のような言葉を語らせていた。
その後で堀田は、「鈍痛」を抱えながら閉じこもって『白痴』を読んだ若者にこの言葉の意味を説明させているのである(文庫本・下巻93頁~101頁)。ここでは長編小説『白痴』に対する作者の強い愛着が示されているので、少し長くなるが引用しておきたい。
「学校へも行かず、外出もせず、課された鈍痛は我慢をすることにし、若者はとじこもって本を読みつづけた。ドストエフスキーの『白痴』は、何度読んでも、大きな渦巻きのなかへ頭から巻き込むようにして若者を巻き込み、ときには、その大渦巻きの、回転する水の壁が見えるように思い、エドガー・ポオの大渦巻き(メイルストローム)さえが垣間見えるかと思うことさえあった。とりわけて、その冒頭が若者の思考や感情の全体を占めていた。
――なるほど! 絶対の不可能を可能にするには、こうすればいいのか!
と、その冒頭の三頁ほどを、毎日毎日読みかえした。古本屋で買った英訳と、白柳君に借りた仏訳の双方があったので、米川正夫訳と三冊の本を対照しながら読み返してみていた。」
この後で長編小説『白痴』の冒頭の文章を書き写した著者は、「あのロシアの平べったい平原の、ところどころに森や林や広大な水たまりなどのあるところを、汽車がひた走りに走って行く、その走り方のリズムのようなものが、この文章に乗って来ていることが、じかに肌に感じられる」と記している。
そして、二人の旅客に注意を向けてロゴージンを描いた文章を引用した後で「向ひの席の相客は、思ひもかけなかつたらしい湿つぽい露西亜の十一月の夜のきびしさを、顫へる背に押しこたへねばならなかつたのである」とムィシキンを描写していることに注意を促してこう続けている。
「天使のような人物を、ロシアという現実のなかへ、人間の劇のなかへつれ込むのに、汽車という、当時としての新奇なものに乗せた、あるいは乗せなければなかった、そこに、ある痛切な、人間の悲惨と滑稽がすでに読みとられるのである」(下巻、96頁)。
3,「シベリヤから還つたムィシキン」という小林秀雄の解釈
一方、小林秀雄は二・二六事件が起きる2年前の1934年に書かれた「『罪と罰』についてⅠ」で、「罪の意識も罰の意識も遂に彼(引用者注──ラスコーリニコフ)には現れぬ」とし、エピローグは「半分は読者の為に書かれた」と解釈していた(『小林秀雄全集』第六巻、四五頁、五三頁)。
そして、エピローグにおけるラスコーリニコフの「復活」を否定した小林は、「ドストエフスキイは遂にラスコオリニコフ的憂愁を逃れ得ただらうか」と問いかけ、「来るべき『白痴』はこの憂愁の一段と兇暴な純化であつた。ムイシュキンはスイスから還つたのではない、シベリヤから還つたのである」というテキストを修正するような大胆な解釈を示して『白痴』論の方向性を示していた(『小林秀雄全集』第六巻、六三頁)。
続く「『白痴』についてⅠ」で小林は、貴族のトーツキーの妾となっていた美女のナスターシヤを、「この作者が好んで描く言はば自意識上のサディストでありマゾヒストである」と規定していたが、それは厳しい格差社会であった帝政ロシアの現実を無視した解釈だろう。両親が火災で亡くなって孤児となったナスターシヤは、貴族のトーツキーに養育されたものの少女趣味のあった彼によって無理矢理に妾にさせられた被害者だったのである(『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』、31頁)。
しかし、「ムイシュキンの正体といふものは読むに従つていよいよ無気味に思はれて来る」と続けた小林は、『白痴』の結末の異常性を強調して「悪魔に魂を売り渡して了つたこれらの人間」によって「繰り広げられるものはたゞ三つの生命が滅んで行く無気味な光景だ」と記していた(拙著、47頁)。
4,「外界」から「入って」来るムィシキン
一方、『若き日の詩人たちの肖像』で堀田は、ムィシキンのような「天使」はやはり「外国、すなわち外界から汽車にでも乗せて入って来ざるをえないのだ」(下線の箇所は原文では傍点)と記していた。
この文章は『白痴』を映画化した黒澤明監督と同じように、作家・堀田善衛がこの長編小説を正確に読み解いていることを物語っているだろう。なぜならば、スイスでの治療をほぼ終えたムィシキン公爵が混沌としている祖国に帰国する決意をしたのは、母方の親戚の莫大な遺産を相続したとの知らせに接したためだったからである。
そして、ドストエフスキーは小説の冒頭で思いがけず莫大な遺産を相続したムィシキンとロゴージンの共通点を描くとともに、その財産をロシアの困窮した人々の救済のために用いようとした主人公と、その大金で愛する女性を所有しようとしたロゴージンとの友情と対立をとおして、彼らの悲劇にいたるロシア社会の問題を浮き彫りにしていた。
『若き日の詩人たちの肖像』については、2007年に上梓した拙著 『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』でも言及していたが、ムィシキンが「外界」から「入って」来たことに注意を促しているこの文章が、「ムイシュキンはスイスから還つたのではない、シベリヤから還つたのである」という解釈を行っていた小林秀雄の『白痴』論を強く念頭に置いて書かれていた可能性にようやく気付いたのは、『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』を上梓したあとのことであった。
ここでムィシキンが「外界」から「入って」来ることを強調した堀田は、「小説を読み通して行って、その終末にいたって、天使はやはり人間の世界には住みつけないで、ふたたび外国の、外界であるスイスの癲狂院へもどらざるをえないのである」と小林とは正反対の解釈を記していたのである(下巻、100頁)。
そして、「白痴、というと何やら聞えはいいかもしれないが、天使は、人間としてはやはりバカであり阿呆でなければ、不可能、なのであった」と続けた著者は、若者が「成宗の先生」(堀辰雄)に語った「謎」のような言葉の意味をこう説明していることである。
「左様――ムイシュキン公爵は汽車に乗って入って来たが、ランボオは、詩から、その自由のある筈の詩の世界を捨てて出て行って」しまったというのが、「若者が成宗の先生に言ったことの、その真意であった」(下線は原文では傍点)。
そして、「しかしなんにしてもド氏の小説は面白い、面白くてやり切れなかった。とりわけて、ド氏が小説というものの枠やルールを無視して勝手至極なことをやらかしてくれるところが面白かった」と書いた堀田は、結末の異常性を強調した小林とは反対に「『白痴』はその終末で若者に泪を流させた」と続けていた。


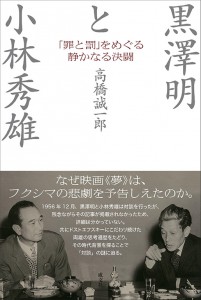









 (書影は「アマゾン」より)
(書影は「アマゾン」より)