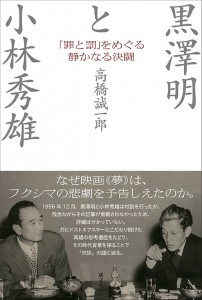『「罪と罰」をどう読むか〈ドストエフスキー読書会〉』(川崎浹・小野民樹・中村邦生著 水声社 二〇一六年)
本書はウォルィンスキイの『ドストエフスキイ』やレイゾフ編『ドストエフスキイと西欧文学』など多くの訳書があるロシア文学者の川崎浹氏と、『新藤兼人伝──未完の日本映画史』などの著作がある研究者の小野民樹氏と、ドストエフスキーの作中人物をも取り込んだ小説『転落譚』がある中村邦生氏の鼎談を纏めたものである。
『罪と罰』の発表から一五〇年にあたる二〇一六年には、それを記念した国際ドストエフスキー学会が六月にスペインのグラナダで開かれたが、冒頭で『罪と罰』を翻訳し「恰も広野に落雷に会って目眩き耳聾ひたるがごとき、今までに会って覚えない甚深な感動を与えられた」という内田魯庵の言葉が紹介されている本書もそのことを反映しているだろう。
さらに本書の「あとがき」では学術書ではないので、「お世話になった方々の氏名をあげるにとどめる」として本会の木下豊房代表をはじめ、芦川氏や井桁氏など主なドストエフスキー研究者の名前が挙げられており、それらの研究書や最新の研究動向も踏まえた上で議論が進められていることが感じられる。
以下、本稿では『罪と罰』という長編小説を解釈する上できわめて重要だと思われる「エピローグ」の問題を中心に六つの章からなる本書の特徴に迫りたい。
「『罪と罰』への道」と題された第一章では、若きドストエフスキーが巻き込まれたペトラシェフスキー事件など四〇年代末期の思想動向やシベリアへの流刑の後で書かれた『死の家の記録』などの流れが簡潔に紹介されている。
ことに、農奴解放などの「大改革」が中途半端に終わったことで、過激化していく学生運動などロシアの時代風潮がチェルヌイシェフスキーとの相克や『何をなすべきか』との関わりだけでなく、一八六五年には「モスクワでグルジア人の青年が高利貸しの老婆二人を殺害、裁判が八月に行われ、その速記録が九月上旬の『声』紙に連載」されていたことや、「大学紛争で除籍されたモスクワ大学の学生が郵便局を襲って局員を殺そうとした話」など当時の社会状況が具体的に記されており、そのことは主人公・ラスコーリニコフの心理を理解する上で大いに役立っていると思われる。
当初は一人称で書かれていたこの小説が三人称で書かれることによって、長編小説へと発展したことなど小説の形式についても丁寧に説明されている。
本書の特徴の一つには重要な箇所のテキストの引用が適切になされていることが挙げられると思うが、第二章「老婆殺害」でも『罪と罰』の冒頭の文章が長めに引用され、この文章について小野氏が「なんだか映画のはじまりみたいですね。ドストエフスキーの描写はひじょうに映像的で、描写どおりにイメージしていくと、理想的な舞台装置ができあがる」と語っている。
この言葉にも表れているように、三人の異なった個性と関心がちょうどよいバランスをなしており、モノローグ的にならない<読書会>の雰囲気が醸し出されている。
また、『罪と罰』を内田魯庵の訳で読んだ北村透谷が、お手伝いのナスターシャから「あんた何をしているの?」と尋ねられて、「考えることをしている」と主人公が答える場面に注目していることに注意を促して、「北村透谷のラスコーリニコフ解釈は、あの早い時期としては格段のもの」であり、この頃に「日本で透谷がドストエフスキーをすでに理解していたというのは誇らしい」とも評価されている。
さらに、「ドストエフスキーの小説はたいてい演劇的な構成だと思います。舞台に入ってくる人間というのは問題をかかえてくる」など、「ドストエフスキーの小説は、ほとんどが何幕何場という構成に近い」ことが指摘されているばかりでなく、具体的に「ラスコーリニコフとマルメラードフの酒場での運命的な出遭いというのは、この小説のなかでも心に残る場面ですね」とも語られている。
たしかに、明治の『文学界』の精神的なリーダーであった北村透谷から強い影響を受けた島崎藤村の長編小説『破戒』でも、主人公と酔っ払いとの出遭いが重要な働きをなしており、ここからも近代日本文学に対する『罪と罰』の影響力の強さが感じられる。
また、『罪と罰』とヨーロッパ文学との関連にも多く言及されている本書では、ナポレオン軍の騎兵将校として勤務していた『赤と黒』の作家スタンダールが、「モスクワで零下三〇度の冬将軍」に襲われていたことなど興味深いエピソードが紹介されており、若い読者の関心もそそるだろう。
テキストの解釈の面では、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』など書簡体小説の影響を受けていると思われる母親からの長い手紙の意味がさまざまな視点から詳しく考察されているところや、なぜ高利貸しの義理の妹リザベータをも殺すことになったかをめぐって交わされる「六時過ぎか七時か」の議論、さらに「ふいに」という副詞の使用法についての会話もロシア語を知らない読者にとっては興味深いだろう。
犯罪の核心に迫る第三章「殺人の思想」では、「先ほどネヴァ川の光景が出てきましたけど、夕陽のシーンが小説全体のように現れることが、実に面白いですね」、「重要な場面で必ず夕陽が出てくるし、『夕焼け小説』とでもいいたいほどです」と語られているが、映画や演劇の知識の豊富さに支えられたこの鼎談をとおして、視覚的な映像が浮かんでくるのも本書の魅力だろう。
さらに、井桁貞義氏はドストエフスキーにおける「ナポレオンのイデア」の重要性を指摘していたが、本書でも「ナポレオンとニーチェ」のテーマも視野に入れた形で「良心の問題」がこの小説の中心的なテーマとして、「非凡人の理論」や「新しいエルサレム」にも言及しながらきちんと議論されている。
本書の冒頭では『罪と罰』から強い感動を与えられたと記した内田魯庵の言葉をひいて、「読んだ人には皆覚えがある筈だ」と指摘し、「残念な事には誰も真面目に読み返そうとしないのである」と続けていた文芸評論家の小林秀雄の文章も引用されていた。本章における「良心の問題」の分析は、一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で、ラスコーリニコフには「罪の意識も罰の意識も遂に彼には現れぬ」と解釈していた小林秀雄の良心観を再考察する機会にもなると思える。
第四章「スヴィドリガイロフ、ソーニャ、ドゥーニャ」や、「センナヤ広場へ」と題された第五章でも多くの研究書や研究動向も踏まえた上で、主な登場人物とその人間関係が考察されており興味深い。
ことに私がつよい関心を持ったのは、ソーニャが「ラザロの復活」を読むシーンに関連して一八七三年の『作家の日記』(昔の人々)でも、ドストエフスキーがルナンの『イエスの生涯』について、「この本はなんといってもキリストが人間的な美しさの理想であって、未来においてすらくり返されることのない、到達しがたい一つの典型であるとルナンは宣言していた」ことに注意が促されていたことである。
そして、このようなドストエフスキーのキリスト理解をも踏まえて第六章「『エピローグ』」の問題」では、『死の家の記録』に記されていたドストエフスキー自身がシベリアのイルティシ川から受けた深い感銘もきちんと引用されており、そのことが『罪と罰』の読みに深みを与えている。
たとえば、ドストエフスキーは「首都から千キロも離れたオムスクの監獄と流刑地のセミパラチンスクで過ごしたことにより、ロシアの懐の深さを知って帰ってきた」と語った川崎氏は、「その背景があって作家は『エピローグ』を書いた」と説明している。
そして、「『ラズミーヒンはシベリア移住を固く決意した』と『エピローグ』に書かれていますが、彼のシベリア行きはちょっと不自然に思いました」との感想に対しては、「ラズミーヒンがドゥーニャといっしょにシベリアに行って根付こうというときに、あそこは『土壌が豊かだから』と彼自身はっきりと言って」いると語っているのである。
さらに私は囚人たちが大切に思っている「ただ一条の太陽の光、鬱蒼(うっそう)たる森、どこともしれぬ奥まった場所に、湧きでる冷たい泉」が、ラスコーリニコフが病院で見た「人類滅亡の悪夢」に深く関わっていると考えてきたが、この鼎談でもこの文章に言及した後で悪夢が詳しく分析されている。
すなわち、この悪夢には「ヨハネの黙示録」が下敷きになっていることを確認するとともに、ドストエフスキーがすでに一八四七年に書いた『ペテルブルグ年代記』で「インフルエンザと熱病はペテルブルグの焦点である」と書いていることや、その頃に熱中したマクス・シュティルネルの『唯一者とその所有』では、個人主義の行き過ぎが指摘されていることも確認されている。
そして、「この熱に浮かされた悪夢の印象がながい間消え去らないのに悩まされた」とドストエフスキーが書いていることにふれて、それは「悪夢の役割の大きさを作家が強調したかったのでしょう」と記されている。
ただ、『罪と罰』が連載中の一八六六年五月に起こった普墺戦争では、先のデンマークとの戦争では連合して戦ったプロイセン王国とオーストリア帝国とが戦ってプロイセンが圧勝したことで、今度はフランス帝国との戦争が懸念されるようになっていた。そのことをも留意するならば、この悪夢は将来の世界大戦ばかりでなく、最新兵器を擁する大国に対するテロリズムが広がる現代へのドストエフスキーの洞察力をも物語っているように思える。
鼎談では「ドストエフスキーの文学」と現代との関わりも強く意識されていたが、川崎氏にはシクロフスキイの『トルストイ伝』やロープシンの『蒼ざめた馬』などの翻訳があるので、そこまで踏み込んで解釈してもよかったのではないかと私には思われた。
なぜならば、『地下室の手記』でドストエフスキーは、バックルによれば人間は「文明によって穏和になり、したがって残虐さを減じて戦争もしなくなる」などと説かれているが、実際にはナポレオン(一世、および三世)たちの戦争や南北戦争では「血は川をなして流れている」ではないかと主人公に鋭く問い質させていたからである。
『罪と罰』の最後をドストエフスキーが、「『これまで知ることのなかった新しい現実を知る人間の物語』が新しい作品の主題になると予告している」と書いていることに注意を促して、「そこにはどうしても『白痴』という実験小説が結びつかざるを得ません」と続けた川崎氏の言葉を受けて、「そこに私たちの新たな関心の方位があるということですね」と語った中村氏の言葉で本書は締めくくられている。
冒頭に掲げられている一八六五年の「ペテルブルグ市 街図」や、ロシア人独特の正式名称や愛称を併記した「登場人物一覧」、さらに「邦訳一覧」が収録されており、この著書は格好の『罪と罰』入門書となっているだろう。
川崎氏は「あとがき」で〈ドストエフスキー読書会〉という副題のある本書が、一三年間かけてドストエフスキーの全作品を二度にわたって読み込んだ上で、『罪と罰』についての鼎談を纏めたと発行に至る経緯を記している。
本書でもふれられていたルナンの『イエスの生涯』についてのドストエフスキーの関心は長編小説『白痴』とも深く関わっているので、次作『白痴』論の発行も待たれる。
(『ドストエーフスキイ広場』第26号、2017年、132~136頁より転載)