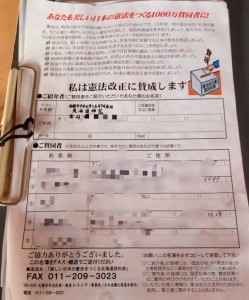「自主憲法を日本人の手で作り上げなければいけない」」として、「改憲」を目指す安倍自民党が昨年提出した「戦争法」が、日本政府に軍国化を迫った「第3次アーミテージ・リポート」の内容ときわめて近いものであったことが国会の質疑応答で明らかになりました。
同じように安倍政権はアベノミクスの一環として、それまでの自民党の「公約」に反してTPP秘密交渉への参加も決めていましたが、これも「日本の原発再稼働やTPP参加、特定秘密保護法の制定、武器輸出三原則の撤廃」を求めた「第3次アーミテージ・リポート」の要求に沿うものであったことも明らかになっています。
アメリカの要求に従って、一部の大企業と軍需産業の利益にはなるが、大多数の「日本国民」には犠牲を強いる安倍政治は、ドイツの作家シラーなどが戯曲『ウィリアム・テル』(ヴィルヘルム・テル)で描いた14世紀の悪代官ヘルマン・ゲスラーの暴政に似ていると思われます。
(アルトドルフのマルクト広場にあるウィリアム・テル記念碑。写真は「ウィキペディア」より)
経済学に関しては素人ですが、素人でも分かるような「TPP」の危険な点を以下に記した後で、最後に正岡子規が編集主任をしていた新聞『小日本』における「秘密主義」批判の記事を再掲しておきます。
明治に書かれたこの記事は、「秘密主義」を貫く一方で、報道機関への圧力を強めている安倍政権と「薩長藩閥政府」との類似性を示唆していると思えるからです。
* * *
TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の秘密交渉の結果が一部、明らかになりましたが、やはり農業や牧畜などに限っただけでも大幅な譲歩を強いられていたことが明らかになりました。
「東京新聞」の記事によれば、この結果を受けてようやく民主党が中間報告案で「国益守れず」と明記し、TPPへの政府承認案に反対する方向を示したとのことです。
これに対して与党からは「選挙目当てで方針を変えるのか」などの批判が出ているようですが、原発の危険性に気づいた小泉元首相が脱原発に転換したように、その政策の間違いに気づいた時にはすばやく対応することが重要でしょう。
ことに、これから世界的な食糧危機が予想される中で、国民の生命や健康に深くかかわる「食料自給率」の低下は、「国家の安全保障」をも脅かすと思えるからです。
* * *
これまでは外国からの圧力により「規制緩和」が、あたかも絶対的な正義のように見られていましたが。最近起きた痛ましいバス事故の遠因は、バス事業への参加への「規制緩和」にあったことが指摘されています。
現状でのTPPへの政府承認案は農業の衰退をまねくばかりでなく、「食品添加物・遺伝子組み換え食品・残留農薬などの規制緩和」により、食の安全を脅かし、「医療保険の自由化・混合診療の解禁により、国保制度の圧迫や医療格差が広がりかねない」危険性があるのです。
TPP(環太平洋パートナーシップ協定)では、自由貿易が謳われていますが、その反面、著作権の大幅な延長に見られるように、「規制強化」の側面も強く持っているようです。
ことに「ISDS条項(ISD条項)」は、「当該企業・投資家が損失・不利益を被った場合、国内法を無視して世界銀行傘下の国際投資紛争解決センターに提訴することが可能」としています。この条項は、グロ-バル産業には有利でも、国内産業には不利益であり、日本の独自性をも損なう危険性があるように思われます。
また、「一度自由化・規制緩和された条件は当該国の不都合・不利益に関わらず取り消すことができない」という21世紀の規定とは思えない不思議なラチェット規定を、安倍政権が一方的に認めてしまったことにも問題があるでしょう。
* * *
明治27年4月29日に子規が編集主任を務めていた新聞『小日本』は第一面に掲載された「政府党の常語」という題名の記事で、「感情」、「譲歩」、「文明」、「秘密」などの用語を取り上げていました。
ことに「藩閥政府」の問題点を鋭く衝いた「秘密」は、原発事故のその後の状況や、国民の健康や生命に深く関わるTPPの問題など多くが隠されている現代の「政府党の常語」を批判していると思えるほどの新鮮さと大胆さを持っているように思えます。以前のブログ記事でも引用しましたが、再び全文を引用しておきます。
「秘密秘密何でも秘密、殊には『外交秘密』とやらが当局無二の好物なり、如何にも外交政策に於ては時に秘密を要せざるに非ず、去れどそは攻守同盟とか、和戦談判とかいふ場合に於て必要のみ、普通一般の通商条約、其条約の改正などに何の秘密かこれあらん、斯かる条項は成るべく予め国民一般に知らしめて世論の在る所を傾聴し、国家に民人に及ぼす利害得喪を深察するこそ当然なれ、去るに是れをも外交秘密てふ言葉の裏に推込(おしこ)めて国民の耳目に触れしめず、斯かる手段こそ当局の尊崇する文明の本国欧米にては専制的野蛮政策とは申すなれ、去れど此一事だけは終始(しじう)一貫して中々厳重に把持せらるゝ当局の心中きたなし卑し」(青字は引用者)。
TPP関連の記事一覧