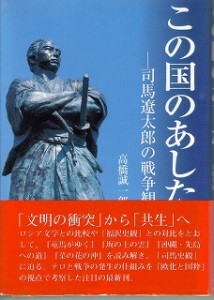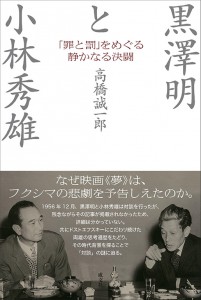リンク→「主な研究」のページ構成
(芥川龍之介の肖像、Yokohama045、図版は「ウィキペディア」より)
はじめに
本稿では言論統制の強化が進み始めたころに書かれた芥川龍之介の『将軍』などに対する小林と司馬の考察を比較することで、イデオロギーから自由であった司馬遼太郎の歴史認識の広さと深さを明らかにできるだろう。
一、司馬遼太郎の『殉死』と芥川龍之介の『将軍』
『坂の上の雲』を書く一年前に乃木大将を主題とした『殉死』(文春文庫)を発表した司馬遼太郎は、この小説の冒頭近くで直接名前は出さないものの芥川龍之介の『将軍』に言及して、「筆者はいわゆる乃木ファンではない」が、自分には「大正期の文士がひどく毛嫌いしたような、あのような積極的な嫌悪もない」と断り、この作品を「小説以前の、いわば自分自身の思考をたしかめる」つもりで書くと続けていた。
それゆえ、この記述では芥川と自分の乃木観の違いが強調されていると考えた私は、旅順の激戦にも言及しつつ乃木大将を批判的に描いていた芥川龍之介の小説が気になりながらも、この短編と『殉死』とを具体的に比較することは行ってこなかった。
しかし、司馬遼太郎の『殉死』や『坂の上の雲』にも影響を及ぼしたと思われる夏目漱石の短編「趣味の遺伝」における旅順の戦いの描写や乃木将軍への言及に注目しながら、改めて芥川の『将軍』を読んだ際には先の言葉は司馬氏独特の韜晦的な表現であり、実際は芥川龍之介のこの小説の影響を強く受けているだろうと感じるようになった。
芥川龍之介の短編小説『将軍』は現在あまり読まれていないので、まずその内容を詳しく紹介し、その後で司馬の『殉死』との関係を考察することにしたい。
芥川龍之介の『将軍』は、司馬が「旅順総攻撃」の章でもふれていた「白襷(しろだすき)隊」について書いている第一章の「白襷隊」から始まり、「間諜」、「陣中の芝居」と続いて、乃木大将の殉死をめぐる父と息子との会話を描いた第四章「父と子と」から成立っている(引用は『芥川龍之介全集』岩波書店による)。
第一章の「白襷隊」は次のような文章で始まっている。「明治三十七年十一月二十六日の未明だった。第×師団第×聯隊(れんたい)の白襷隊(しろだすきたい)は、松樹山(しょうじゅさん)の補備砲台(ほびほうだい)を奪取するために、九十三高地(くじゅうさんこうち)の北麓(ほくろく)を出発した」。
その後で芥川龍之介はこう記している。少し長くなるが、司馬遼太郎の「軍神」観にも関わるので引用しておく。
「路(みち)は山陰(やまかげ)に沿うていたから、隊形も今日は特別に、四列側面の行進だった。その草もない薄闇(うすやみ)の路に、銃身を並べた一隊の兵が、白襷(しろだすき)ばかり仄(ほのめ)かせながら、静かに靴(くつ)を鳴らして行くのは、悲壮な光景に違いなかった。現に指揮官のM大尉なぞは、この隊の先頭に立った時から、別人のように口数(くちかず)の少い、沈んだ顔色(かおいろ)をしているのだった。が、兵は皆思いのほか、平生の元気を失わなかった。それは一つには日本魂(やまとだましい)の力、二つには酒の力だった。」(太字は引用者)
そして、「聯隊長はじめ何人かの将校」が「最後の敬礼を送っていた」のを見た田中一等卒が「どうだい? たいしたものじゃないか? 白襷隊になるのも名誉だな」と語るのを聞いて、「苦々しそうに、肩の上に銃をゆすり上げた」堀尾一等卒が、「何が名誉だ?」と聞き返し、「こちとらはみんな死にに行くのだぜ。してみればあれは××××××××××××××そうっていうのだ。こんな安上がりなことはなかろうじゃねえか?」と反論した。すると田中一等卒が、「それはいけない。そんなことを言っては×××すまない」と語ったと芥川は記している。
ここで注目したいのは、『澄江堂雑記』に「官憲」によって「何行も抹殺を施された」と芥川は記しているが、将校たちから「最後の敬礼」に送られて突撃をする兵士たちの苦悩が具体的に描き出されていたこの会話の部分も、検閲で伏せ字になっていることである。原稿が遺されていないために確定できないが、注の記述は最初の個所では「名誉の敬礼で生命を買い上げて殺(そう)」という文章が、次の個所では「陛下に」という文字が入っていただろうと想定している。
そして、第二章の「間諜」では、ロシア側のスパイを見つけた「将軍の眼には一瞬間、モノメニアの光が輝」き、「斬れ! 斬れ!」と命じた場面などが描かれている。「午前に招魂祭を行なったのち」に催された「余興の演芸会」での出来事が記されている第三章「陣中の芝居」では、将軍が「男女の相撲」や「濡れ場」のある余興の上演を二度にわたって直ちに取りやめさせるのを見た「口の悪いアメリカの武官」が隣にすわったフランスの武官に、「将軍Nも楽じゃない。軍司令官兼検閲官だから」と話しかける場面が描かれ、ピストル強盗を捉えつつも傷ついた巡査が亡くなるという芝居ではN将軍が、「偉い奴じゃ。それでこそ日本男児じゃ」と深い感激の声をあげたと記されている(下線引用者)。
最後の「父と子と」の章では、日露戦争当時は軍参謀の少佐だった中村少将とその息子との大正七年の夜の会話が淡々と描かれている。壁にあった「N閣下の額画」が別の絵に懸け換えられているのに気づいた少将から、肖像画が壁に掛かっているレンブラントについて尋ねられた息子は「ええ、偉い画かきです」と答え、さらに「まあN将軍などよりも、僕らに近い気もちのある人です」と続けている。
一方、彼が追悼会に出ていた友人が「やはり自殺している」ことを告げた青年は、自殺する前に「写真をとる余裕はなかったようです」と続けて暗にN将軍を批判したことを咎められると、「僕は将軍の自殺した気もちは、幾分かわかるような気がします」としながらも、「しかし写真をとったのはわかりません。まさか死後その写真が、どこの店頭にも飾られることを、――」と続けようとした。
すると、「それは酷だ。閣下はそんな俗人じゃない、徹頭徹尾至誠の人だ」と父から憤然とさえぎられるが、息子は「至誠の人だったことも想像できます。ただその至誠が僕等には、どうもはっきりとのみこめないのです。僕等よりのちの人間には、なおさら通じるとは思われません。……」と語り、雨が降ってきたことに気づく場面で終わる。
大正一〇年に書かれたこの小説で芥川は青年に「ただその至誠が僕等には、どうもはっきりとのみこめないのです」と語らせていたが、この小説が発表された二年後には戦死者でなかったために靖国神社に入ることのできなかった乃木を祭る神社が創建され、「活躍した偉人を祭神とする神社の先例」となった(山室建徳『軍神――近代日本が生んだ「英雄」たちの軌跡』中公新書、二〇〇七年)。
さらに、昭和に入ると「偉大なる明治を思い返すべきという動き」が強まり、満州事変勃発の直後に廣瀬武夫を祀る神社創設の許可が内務省からおりて、日露戦争戦勝三〇周年にあたる昭和一〇年に廣瀬神社が鎮座した。芥川が自殺した翌年の昭和一五年には「本人の意志など問題ではなく」なり、東郷平八郎が神になることを「もってのほかでごわす」と拒否したにもかかわらず東郷神社が創建された。
一方、明治二〇年から一年間ドイツに留学していた乃木希典が帰国後に書いた意見具申書で、「我邦(わがくに)仏教の如キハ、目下殆(ほと)ンド何ノ用ヲ為ストコロナク」と書いている文章に注目した司馬は、『殉死』において乃木が「軍人の徳義の根元は天皇と軍人勅諭と武門武士の伝統的忠誠心にもとめるほかない」と報告していたばかりでなく、「日本は神国なるがゆえに尊し」という感動をもって書かれた山鹿素行の『中朝事実』を、師の玉木文之進から「聖典」のごとくに習っていた乃木希典が、ドイツ留学から戻った後でこれを読みなおすことで、「ついにはその教徒のごとくになった」と書いていたのである。
司馬と同じころに青春を過ごした哲学者の梅原猛は『殉死』や『坂の上の雲』において、「乃木希典は純真きわまりない人間」としてだけでなく、「戦争は大変下手で、無謀な突撃によっていたずらに多くの兵隊の血を流した将軍」として描かれていると指摘し、「乃木大将は東郷元帥とともに戦前の日本ではもっとも尊敬された軍神であった」ので、「戦前ならば、死刑にならないまでも、軍神を冒涜するものと作者は社会的に葬られたにちがいない」として、この作品を書いた司馬の勇気を高く評価している(「なぜ日本人は司馬文学を愛したか」『幕末~近代の歴史観』)。
芥川龍之介は治安維持法が強化されて特別高等警察が設置される前年の昭和二年に自殺したが、大正時代の青年たちを主人公とした『ひとびとの跫音』(中公文庫)で司馬は、大正十四年には治安維持法が公布されて国家そのものが「投網」や「かすみ網」のようになったと記し、「人間が、鳥かけもののように人間に仕掛けられてとらえられるというのは、未開の闇のようなぶきみさとおかしみがある」と続けている。
芥川が遺書ともいえる「或旧友へ送る手記」で、「みずから神にしない」と書き、自己の英雄化を拒否していることに注目するならば、「軍神を冒涜するもの」は「社会的に葬られた」時代に青春を過ごした司馬の芥川龍之介に対する思いはきわめて深く重かったと思える。
二、小林秀雄の『将軍』観と司馬遼太郎の「軍神」批判
一九四一年に書いた「歴史と文学」という題名の評論の第二章で、「先日、スタンレイ・ウォッシュバアンといふ人が乃木将軍に就いて書いた本を読みました。大正十三年に翻訳された極く古ぼけた本です。僕は偶然の事から、知人に薦められて読んだのですが、非常に面白かつた」とした小林秀雄は、「思い出話で纏(まと)まつた伝記ではないのですが、乃木将軍といふ人間の面目は躍如と描かれてゐるといふ風に僕は感じました」と書いていた(『小林秀雄全集』第七巻二一二頁)。
小林の読んだ本は、日露戦争の際にシカゴ・ニュースの記者として従軍したウォシュバンが書いた『NOGI』という原題の伝記で、『乃木大将と日本人』という邦題で、徳冨蘇峰による訳書推薦の序文とともに目黒真澄の訳で出版されていたものである(講談社学術文庫、一九八〇年)。
その直後に芥川の『将軍』に言及した小林は「これも、やはり大正十年頃発表され、当時なかなか評判を呼んだ作で、僕は、学生時代に読んで、大変面白かつた記憶があります。今度、序でにそれを読み返してみたのだが、何んの興味も起こらなかつた。どうして、こんなものが出来上つて了つたのか、又どうして二十年前の自分には、かういふものが面白く思はれたのか、僕は、そんな事を、あれこれと考へました」と続けている(下線引用者))。
そして、「『将軍』の作者が、この作を書いた気持ちは、まあ簡単でないと察せられますが、世人の考えてゐる英雄乃木といふものに対し、人間乃木を描いて抗議したいといふ気持ちは、明らかで、この考へは、作中、露骨に顔を出してゐる」とした小林は「敵の間諜を処刑する時の、乃木将軍のモノマニア染みた残忍な眼とか、陣中の余興芝居で、ピストル強盗の愚劇に感動して、涙を流す場面だとかを描いてゐる」が、「作者の意に反して乃木将軍のポンチ絵の様なものが出来上る」と解釈している(下線引用者)。
さらに、「最後に、これもポンチ絵染みた文学青年が登場していまして」と続けて、乃木将軍を批判した青年の言葉を紹介し、「作者にしてみれば、これはまあ辛辣な皮肉とでもいふ積りなのでありませう」と書いた小林は、ウォッシュバンの書いた伝記が「芥川龍之介の作品とまるで違つているのは、乃木将軍といふ異常な精神力を持つた人間が演じねばならなかつた異常な悲劇といふものを洞察し、この洞察の上にたつて凡ての事柄を見てゐるといふ点です。この事を忘れて、乃木将軍の人間性などといふものを弄くり廻してはゐないのであります」と賛美していた。
ここで小林は、「学生時代に読んで、大変面白かつた」記憶がある『将軍』を、ついでに読み返してみたのだが、何んの興味も起こらなかつた」と書いていたが、その理由は現在の読者には明らかだろう。つまり、学生時代には自分にも戦場で戦うことになる可能性があったので、芥川が青年に語らせた言葉は小林にとっても切実なものだった。しかし、この評論を書いた翌年には大東亜文学者会議評議員に選出され、青年たちを戦場へと送り出す役割をいっそう強く担うことになる小林にはすでにそのような危険性は無くなっていたのである。
司馬遼太郎の歴史観との関連で興味深いのは、小林が「疑惑 Ⅱ」というエッセーで、日中戦争の時に二五歳で戦死し、「軍神」とされた戦車隊の下士官・陸軍中尉西住小次郎を扱った「菊池寛氏の『西住戦車長伝』を僕は近頃愛読してゐる。純粋な真実ないゝ作品である」と書いていることである(『小林秀雄全集』第七巻、六八頁)。そして、「友人に聞いても誰も読んでゐる人がない。恐らくインテリゲンチャの大部分のものは、あれを読んではゐないであらう。当然な事なのだ」と書いた小林は、「インテリゲンチャには西住戦車長の思想の古さが堪へられないのである。思想の古さに堪へられないとは、何といふ弱い精神だろう」と続けて、日本の近代的な知識人を批判していた。
さらに、「今日わが国を見舞っている危機の為に、実際に国民の為に戦っている人々の思想は、西住戦車長の抱いてゐる様な単純率直な、インテリゲンチャがその古さに堪へぬ様な、一と口に言へば大和魂といふ、インテリゲンチャがその曖昧さに堪へぬ様な思想にほかならないのではないか」と記して、夏目漱石が『吾輩は猫である』でスローガンとして使われていることへの危機感を表明していた「大和魂」にも言及した小林は、「伝統は生きてゐる。そして戦車といふ最新の科学の粋を集めた武器に乗つてゐる」と続けていたのである(太字は引用者)。
一方、『竜馬がゆく』を執筆中の一九六四年に軍神・西住戦車長」というエッセーを書いた司馬遼太郎は、そこで「明治このかた、大戦がおこるたびに、軍部は軍神をつくって、その像を陣頭にかかげ、国民の戦意をあおるのが例になった。最初はだれの知恵から出たものかはわからないが、もっとも安あがりの軍需資源といっていい」と厳しく批判していた(『歴史と小説』、集英社文庫)。
そして、「日露戦争では、海軍は旅順閉塞隊の広瀬武夫中佐、陸軍では遼陽で戦死した橘周太中佐が軍神」になっていたことを紹介した司馬は、菊池寛の『西住戦車長伝』から「剛胆不撓(ごうたんふとう)、常に陣頭に立ちつつ奮戦又奮戦真に鬼神を泣かしむる行動を敢行して、よく難局を打開し」という記述を引用して、「事実、そのとおりであろう。西住小次郎が篤実で有能な下級将校であったことはまちがいない」と記している。(なお、司馬はここで菊池寛の伝記を『昭和の軍神・西住戦車長伝』と、「昭和の軍神」を付け加えて誤記しているが、それは軍神に対する司馬の強い関心をも示しているだろう)。
ただ、その後で司馬は比較文学者の島田謹二が描いた『ロシヤにおける広瀬武夫』(弘文堂刊)に描かれている「この個性的な明治の軍人がすぐれた文化人の一面をもっていたことを知ったが、昭和の軍神はそうではなかった。学校と父親からつくった鋳型から一歩もはみ出ていなかった」と続けているのである。
すなわち司馬によれば、西住戦車長が「軍神」になりえたのは彼が戦車に乗っていたからであり、「軍神を作って壮大な機甲兵団があるかのごとき宣伝をする必要があった」のであり、当時の日本陸軍は「世界第二流の軍隊だった」が、「国家が国民をいつわって世界一と信じこませていたのである」(太字は引用者)。
西住戦車長が戦死した翌年にノモンハン事件が起きると、その「いつわり」のつけはすぐに払わねばならなくなった。冷静な事実の記述でありながら、内に激しい怒りがこもっている司馬の文章を少し長くなるが引用しておきたい。
「ソ連のBT戦車というのもたいした戦車ではなかったが、ただ八九式の日本戦車よりも装甲が厚く、砲身が長かった。戦車戦は精神力はなんの役にも立たない。戦車同士の戦闘は、装甲の厚さと砲の大きさで勝負のつくものだ。ノモンハンでの日本戦車の射撃はじつに正確だったそうだが、(中略)タマは敵戦車にあたってはコロコロところがった。ところがBT戦車を操縦するモンゴル人の大砲は、命中するごとにブリキのような八九式戦車を串刺しにして、ほとんど全滅させた。」
つまり、司馬遼太郎は『坂の上の雲』で日露戦争の際に、乃木大将の指揮した軍隊が崩壊したことなどが隠蔽されたことを指摘していたが、そのような軍事上の事実の「隠蔽」はノモンハン事件での大敗北の際にも行われて、国民には知らされていなかったのである。
この意味で重要と思われるのは、『昭和という国家』の「誰が魔法をかけたのか」と題された第一章で、「ノモンハンには実際には行ったことはありません。その後に入った戦車連隊が、ノモンハン事件に参加していました」と語り、「いったい、こういうばかなことをやる国は何なのだろうということが、日本とは何か、ということの最初の疑問となりました」とし、「私は長年、この魔法の森の謎を解く鍵をつくりたいと考えてきました」と続けた司馬が、「参謀本部という異様なもの」について言及して、「そういう仕組みがいつでき始めたかというと、大正時代ぐらいから始まっています。もうちょっとさかのぼれば、日露戦争のときが始まりでした」と書いていることである。
このように見てくるとき、『坂の上の雲』を書いたときの司馬の関心が、「軍神」を作り出して、本来ならばその生命を守るべき「国民」を戦争に駆り立てた「参謀本部」というシステムにあったことは確実だといえるだろう。
事実、「ノモンハンで生きのこった日本軍の戦車小隊長、中隊長の数人が、発狂して廃人になったというはなしを、私は戦車学校のときにきいて戦慄したことがある。命中しても貫徹しないような兵器をもたされて戦場に出されれば、マジメな将校であればあるほど発狂するのが当然であろう」とも記していた司馬は、「昭和に入って、軍部はシナ事変をおこし、さらにそれを拡大しようとしたために、国民の陣頭にかざす軍神が必要になった」と説明し、「つづいて大東亜戦争の象徴的戦士として真珠湾攻撃のいわゆる『九軍神』がえらばれ」たが、「日本の軍部がほろびるとともに、その神の座もほろんだ」と結んでいたのである(『歴史と小説』)
それゆえ司馬は、『坂の上の雲』を書き終わった年に発表した「戦車・この憂鬱な乗り物」と題した一九七二年のエッセーでは、「戦車であればいいじゃないか。防御鋼板の薄さは大和魂でおぎなう」とした「参謀本部の思想」を厳しく批判している(太字は引用者)。このとき司馬の批判が「大和魂」を強調しつつ、「伝統は生きてゐる。そして戦車といふ最新の科学の粋を集めた武器に乗つてゐる」と書いて、国民の戦意を煽っていた小林秀雄の歴史認識にも向けられていた可能性は高かったと思える。
(〈司馬遼太郎と小林秀雄――「軍神」の問題をめぐって〉『全作家』第90号、2013年より、芥川龍之介観の考察を独立させ、それに伴って改題した。2月6日、青い字の箇所とリンク先を追加)
リンク→司馬遼太郎と小林秀雄(1)――歴史認識とイデオロギーの問題をめぐって
リンク→小林秀雄と「一億玉砕」の思想