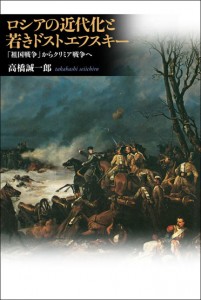(←画像をクリックで拡大できます)
(←画像をクリックで拡大できます)
序章 「ねずみ」たちについて
『未成年』の主人公アルカージイは、『吝嗇の騎士』について「これこそ、思想的に見て、プーシキンの創造した最高のものだ」(工藤精一郎訳)と述べている。これは自分が蓄えた多量の金貨を見ながら、「わしは悪魔さながらに、ここから世界を支配できるのだ」(栗原成郎訳)とつぶやくけちな男爵とその父のせいで騎士としての対面も保てないような生活を強いられる息子アルベールとの激しい対立から、ついには、決闘ざたから息子が父親を殺すに至る物語詩である。
この作品のテーマは、やはり「父親殺し」のテーマを扱った『カラマーゾフの兄弟』を強く思い起こさせるが、ソヴィエトの研究者ブラゴーイは、親子の対立を裁いてもらおうとした長老の前で父フョードルと息子ドミートリイが激しく言い争う『カラマーゾフの兄弟』の冒頭の場面と、やはり、親子のどちらが正しいかを裁いて貰おうとして大公の前で親子が激しく争う『吝嗇の騎士』の最後の場面との類似をも指摘している。
ところで、この『吝嗇の騎士』には「親父が俺を、地下の穴倉で生まれた二十日ねずみのようにではなく、れっきとした貴族の息子として扱ってくれるようにしてみせるぞ」(傍点筆者)という息子アルベールの台詞がある。ブラゴーイは、これら傍線をひいた単語は、やはり自分のことを「ねずみ」にたとえた『地下室の手記』の主人公を連想させると指摘している。確かにここで「地下の穴倉」と訳されているのは「地下室」とも同じ単語なのである。
だが、「ねずみ」という単語が呼び起こす連想は「地下室の男」にとどまらない。たとえば、『未成年』の創作ノートにはアルカージイの父親の前身となる人物について「彼にとって人間はねずみである」という表現が記されている。また、桶谷氏は「地下室の男」が自分のことを「ねずみ」と呼んでいることに注意をうながしながら、ムイシュキンという名前が、「小ねずみ」(ムイシュカ)に由来することを指摘して、「地下室の男の強烈な自意識の原因である苦痛は、ムイシュキンを病気にした苦しみとおそらく同じものなのである」(桶谷秀昭、『ドストエフスキイ』)と述べている。そして、精神錯乱に陥った男について「私の考えでは、精神病患者というよりも、むしろおそろしく苦しみぬいた男のような気がします。これこそが彼の病気のすべてだったのです」とムイシュキンが語っているのを引用しながら、「ムイシュキンはたくまずして自分のことを語っている。彼が白痴になったのは、『おそろしく苦しみぬいた』からである」と説明している。確かに、ムイシュキンは苦しむイポリートに対して「人より余計に苦しむことのできた人は、当然、ひとより余計に苦しむ値打ちのある人なんですよ」と慰めているが、他者と共に「苦しむ能力」とはムイシュキンの能力を恐らく端的に表すものであり、桶谷秀昭氏の指摘はムイシュキンの本質を突いているように思える。
ところで、「ねずみ」というこの言葉は、自ら「古鼠」と名乗っていたもう一人の主人公『貧しき人々』のジェーヴシキンを思い起こさせる。ドストエーフスキイは、ドン・キホーテについて「彼が美しいのは、それと同時に彼が滑稽であるためにほかなりません」と説明しているが、「ムイシュキン(小鼠)」という名字が滑稽感を読者に与えているように、「ジェーヴシカ(娘)」という名詞から作られたジェーヴシキンの名字も滑稽な感じを読者に与えている。さらに、ドストエーフスキイは一八六八年一月一日の手紙で「他人から嘲笑されながら、自分の価値を知らない美しきものに対する憐憫が表現されているので、読者の内部にも同情が生れるのです。この同情を喚起させる術のなかにユーモアの秘密があるのです」と述べているが、ジェーヴシキンを特徴付けるのもこの同情という言葉なのである。すなわち、ワルワーラはジェーヴシキンについて「あなたはほんとに変なご性分ですこと!…中略…どなたでもあなたは善良なお心を持っていらっしゃるというでしょうけれども、あたくしにいわせるなら、あなたのお心はあまりに善すぎるのです。…中略…もし人のことを何から何までそんなふうに気にかけていたら、いちいちそんなに同情していたら、もうだれよりも不幸な人になるに決っていますわ。」(木村浩訳、傍点筆者)と語っているがこの言葉は、そのままムイシュキンについて当てはまる。ことに最後の傍線の箇所はムイシュキンの悲劇をも予告しているだろう。周知のようにナスターシャ・フィリポヴナやロゴージンへの同情から彼はついには病を再発し、再び白痴に戻ってしまうのである。
この「同情」という単語は日本語で書くと非常に甘ったるい感じになるが、ロシア語では字義どおり訳せば「共ー苦」の意味を持つ単語であり、やはり同情とも訳される単語「共ー感」と共にドストエーフスキイにおいてはしばしば用いられている。後に詳しく見るように、ドストエーフスキイは「良心」(字義どおり訳せば「共ー知」)について深く考察し、人間の行動を善い方向に導くはずの「良心」が、誤った理論に導かれて非人道的な行為に走る危険性を鋭く指摘した。ドストエーフスキイはこのような誤った理論に導かれて「良心」が間違った決定を出すことを防ぐ機能を、「共ー苦」や「共ー感」といった感情の内に見い出したといえるかも知れない。
ムイシュキンは哲学の点で体系だった論述をしていないが、それでも、この「同情」という言葉は後にムイシュキンの「思想」の根幹をなすものとして語られているのである。すなわち、ムイシュキンは殺人を犯しかねないロゴージンについて「彼は苦悩することも同情をよせることもできる大きな心を持っているのだ」と考え、さらに「その同情はロゴージン自身の眼を開かせ、彼を教えさとすであろう。同情こそ全人類の生活にとって最も重要な、ひょっとすると唯一の法則だからである」と結論しているのである。
そして、このような同情(「共ー苦」)の概念はプーシキンと密接に結びついていた。すなわち、「ロゴージンが本を読んでいるーーいったいこれが《憐れみ》じゃないというのか」とムイシュキンが思う箇所があるが、後に彼が「二人でプーシキンを読みました。いや、すっかり読んだのです」(木村浩訳)と述べていることから、それがプーシキンの本であることが分かる。
ドストエーフスキイは亡くなる前年の演説でプーシキンの「特殊な芸術的天才の一面、ーーすなわち全世界的共鳴の才能、他国の天才に同化する才能」に大きな注意を喚起しているが、おそらく、この時もムイシュキンに、プーシキンの作品を読むロゴージンの内に「他者と共に苦しむ」才能や「他者と共に感じられる」才能が目覚めることを期待させていたのだと断言してもよいだろう。
そしてこの点に留意する時、ムイシュキンが持つほとんど唯一の事務的能力」である能筆も、新たな意味を持って来るように思える。「浄書係り」をしていたジェーヴシキンは同僚の者から馬鹿にされていたが、ムイシュキンにおいて「浄書」は、単に一つの事務的能力を表すばかりでなく、人間としての彼の能力をも現しているように思える。たとえば、司馬遼太郎氏は『空海の風景』の中で、どんなタイプの字もかける空海の能力に、どんなものとも心を通わせることのできた「共感できる」能力をみているが、他人の筆跡を驚くほど上手に真似できるムイシュキンの才能にも、他人と「共感できる」能力を見ることができるかもしれない。
小林秀雄は「地下室の男」について論じながら「作者はやっとここまで歩いて来た。『二重人格』のゴリアドキンが、この作の主人公まで育って来たのである」(『ドストエフスキイ』)と書いているが、私たちも同じように、「『貧しき人々』の主人公ジェーヴシキンもようやく『白痴』の主人公まで育ってきたのである」と言えるだろう。
プーシキンがドストエーフスキイに及ぼした影響は、ほとんど彼の一生に及ぶほど長く、また深かった。この稿では、主に『貧しき人々』から『白痴』に至るまでの作品を取り上げながら、「社会正義」と「良心」という二つの側面に光を当てて、ドストエーフスキイの作品に及ぼしたプーシキンの影響についてエッセー風に論じてみたい。
第一章 社会正義を求めてーーペトラシェーフスキイ事件まで
第一節 『貧しき人々』と『駅長』
よく知られているように、『貧しき人々』は貧しい中年の官吏と彼の遠い親戚でみなし子の娘ワルワーラとの往復書簡とワルワーラの手記から成り立ち、二人の精神的な成長が描かれているが、その過程でプーシキンの作品は共に重要な位置を占めている。すなわち、手記の中ではワルワーラがポクローフスキイから借りた本で次第に新しい世界に目覚めて、さらに彼の誕生日に彼女がポクローフスキイの父と共に贈ったプーシキンの全集は彼らの幸福のシンボルともなっていたのである。そして、貧しい官吏の心の成長と人間としての尊厳の目覚めが描かれている手紙では、小説『ベールキン物語』の中の『駅長』が中心的な役割を果たしているのである。
ところで、プーシキンは『エヴゲーニイ・オネーギン』の中で「一年一年、私は荒っぽい散文に心を引かれ、一年一年腕白なリズムから引きはなされて、ーーため息とともに打ち明けるのだが、ーーリズムを追いまわすのが億劫になって来た」(池田健太郎訳)と打ち明けているが、ブラゴーイは当時の批評界はプーシキンの詩から散文への移行を彼の詩才の明らかな衰退と捉えていたと記している。プーシキンのよき理解者であったベリーンスキイですら『ベールキン物語』を「この中にはまったくすぐれた点がないとは言えないにしても、この小説はプーシキンの才能にも彼の名前にも値しない」と論じ、プーシキンに多くを負っていたゴーゴリでさえ「今ではプーシキンを繰り返してはならない。現在我々の規範となるべきなのはプーシキンではない」と断言したのだった。
では、ドストエーフスキイはジェーヴシキンの筆を通してプーシキンの散文をどのように評価したのだろうか。
「今度きみのご本で『駅長』を読みました。これだけはいっておきますが、長年生きているくせに、自分の生活をそっくりまるで掌をさすように書いたが、身近にあることを知らずにいることもあるものなんですね。それに、今まナ自分でも気づかないでいたことが、こんな本を読んでいるうちに、少しずつ思いだしたり、気づいたり、なるほどと納得してくるのです。それから最後に、もうひとつきみの本が好きになった理由があるのです。それはほかでもありません。そこらにある本は、読んでも読んでも、どうにもむずかしくて、わからないような時がよくあるんです。たとえば、わたしなんか愚鈍なたちで、生まれながらの鈍才ですから、あまりむずかしい本は読まないのですが、この本を読んでいると、まるで自分で書いたような気がするんです」
ドストエーフスキイは後にペトラシェーフスキイ事件裁判で、文学は「民衆の生活の表現の一つであり、社会を写す鏡である」と述べ、さらに「誰が新しい考えを、民衆が理解できるようなかたちに作り直すのかーー文学でなくて誰がそれをなすでしょうか」と主張したが、このような文学観はヂェーヴシュキンの筆を通して既に『貧しき人々』において簡単な言葉で記されていたのである。つまり、ドストエーフスキイはこの時点で既にプーシキンの作品に文学のあるべき姿を見ていたと言えるだろう。
だが、ドストエーフスキイはここで『駅長』を高く評価しているだけではない。『駅長』は宿屋に何度か立ち寄ったことのある語り手を通して、一人娘に去られた駅長の悲しみを描いた物語であるが、その登場人物や筋自体も『貧しき人々』の内容と深くかかわっているのである。この作品を読んだヂェーヴシュキンは「わたしはあの男が罪ぶかい話ながら気を失うほどやけ酒をのみ、一日じゅう羊皮の外套をかぶって寝すごし、悲しみをまぎらすためにポンスをあおり、迷子になった仔羊のようなドゥニャーシャのことを思いだしては、汚い外套の裾で目をこすりながら、哀れっぽく泣き声をあげるというところを読んだとき、思わず涙がこぼれそうになりました!」と書くが、『貧しき人々』の結末でもやはり、ワルワーラもやはりジェーヴシキンの元から去っていってしまうのである。ジェーヴシキンは最後の手紙で「生みの娘のように愛していました」と告白し、さらにワルワーラの馬車を追って、「力のかぎり、息の根が絶えるまで、駆けていきます」と書いている。この文を読んだ時、読者の記憶にはドゥーニャを失ったヴィリンの悲しみが重なるだろう。
さらに、別れが避けられないことを知ったジェーヴシキンは手もとに残された『ベールキン物語』を「わたしへのプレゼントにしてください」と悲しみの中で書いているが、恐らくだがこの言葉はプーシキンのテーマと重なることで、ポクローフスキイ葬儀の日に彼の父親が、プーシキンの全集など息子の本をポケットに詰め込めるだけ詰め込んで、息子の棺をつんだ馬車の後を走って追ったというエピソードをも呼び起こすのである。
ところで、ジェーヴシキンは『駅長』を絶賛し、実際この本は彼が人間としての尊厳に目覚めさせる契機を果たした。だが、ネチャーエワはジェーヴシキンのこのような高い評価が実は、娘に出て行かれたヴイリンの孤独と悲しみにワルワーラの注意を向け、今まさに、家庭教師の職を探して自立しようとしていた彼女を自分の元に引き留めておこうとするジェーヴシキンの意図と深く結びついていたことに注意を向けている(『若きドストエーフスキイ』、露文)。
この指摘を受けてヴェトローフスカヤは、秩序の問題という観点から見る時、ドストエーフスキイがジェーヴシキンに述べさせた『外套』についての感想は、プーシキンの『駅長』の中の秩序のテーマを受け継いでいると述べている(「ドストエーフスキイの長編小説『貧しき人々』」、露文)。興味深い指摘なので、少し見ておこう。
『駅長』には「官位はこれ、一四等官。宿場にあっては独裁官」という題辞が掲げられており、プーシキンは本文でこれを受けて「そもそも駅長とは何者だろうか? 一四等官の官等をもつ紛れもない受難者で、この官位のおかげでわずかに殴打を免れているに過ぎず、それとても常に免れるものとは限っていないのである」(神西清訳)と書いている。この一四等官とはピョートル大帝によって新たに布かれた制度の一番下の官位であるが、プーシキンは語り手の口を借りて「……私は、上下の詮議だてのやかましい給仕が、県知事の昼餐で私の皿をあと回しにするのにも、長い間慣れっこになれなかったものである」と記し、主人公の官位に言及することで社会的地位の問題をさりげなく小説の中に持ち込んでいたのだ。さらに、彼は「今になってみれば、それもこれも、まことに理の当然という気がする。まったく、もし『物ごとは位順』というすこぶる通りのいい規則の代わりに、何か別の規則、たとえば『物ごとは知恵の順』が用いられだしたとしたら、いったいどんなことになるだろうか? …中略…給仕はだれから先に料理を配ったらいいだろうか?」(傍点筆者)と皮肉とユーモアを込めて書いている。
ところが、『貧しき人々』の主人公ジェーヴシキンはこの皮肉を全く感じとれず、字句通りにこの言葉を受け取り、勤めに出て働こうとするワルワーラに「お願いですから、そんな自由思想は頭の中からたたきだして、わたしをいたずらに苦しめないでください。…中略…もう一度注意ぶかくきみの本をよく読みかえしてください。きっとなにかためになりますから」と説得するのだ。
『駅長』に対する評価の基準を当てはめるとすれば、主人公の服装の貧しさ、浄書をする主人公にたいする同僚たちの侮蔑と嘲りといった状況が、目の前に生き生きと浮かんでくるように描き出される『外套』は、前者と同様の賞賛に値すべきはずであった。だが、ジェーヴシキンはそのようには反応せずに、「こんなにわたしを追いつめるなんて、ほんとに、いけませんね。」とたしなめて、ようやく買い求めた外套をその夜のうちに、盗まれてしまった貧しい中年の九等官、アカーキイの物語に対しては激しい反発を示した。
それはまさにこの小説が自分の貧困さなど、彼がワルワーラに知られたくなかったことが描かれていたからに他ならなず、また、アカーキイの死後、彼の幽霊が出没し、ついにはかの閣下の橇を止めて彼の外套をはぎ取ったなどという後日譚は、ワルワーラにも当時の秩序に対する反抗心を植え付けるように思えたからである。それゆえジェーヴシキンは『外套』の感想を述べながら「人間の境遇というものは、だれでも至高の神様から決められているのですよ。…中略…ある人は他人に命令をくだし、ある人は不平もいわずに戦々兢々としながら、その命令に服従するようになっています」と『駅長』の語り手が用いた「物事は位順」という規則を持ち出して当時の秩序のあり方を全面的に認めながら、今の「境遇」に満足せず職を求めて自立しようとしているワルワーラを非難するのである。さらに彼は、アカーキイが外套探しに奔走してとうとう閣下に直訴するがかえって叱り飛ばされ、ショックのあまり死んでしまうという結末にふれて、「われわれ下っぱの役人は、叱るべきときには叱りとばすのが当り前です」とし、その理由を「官等にはいろいろあって、それぞれの官等がちゃんとその分に相応した譴責を必要とするので、懲戒にもいろい
ろなニュアンスがでてくるのも自然と言うものでしょう、これは当然の話ですよ! …中
略…(それでーー筆者)、世の中ももっていくのです。この予防法がなかったなら、世の中もたっていきませんし、秩序も何もあったものではありませんよ」(傍点筆者)と書き、ここでも『駅長』の語り手が用いた「理の当然」という言葉(訳語では、当然の話)を使いながら、自分が誤読した『駅長』の語り手の論理を用いて『外套』を批判しているのである。
ところで、ドストエーフスキイはこのようなジェーヴシキンに皮肉な結果を用意している。つまり、ジェーヴシキンは、『外套』の終わり方を批判して「いちばんいいのは、この気の毒な男を死なさずに」、彼の美徳を知った閣下が彼の「官等を上げてやり、俸給もたんまり上げてやる、というふうにしたらどうでしょう」と提案している。そして『貧しき人々』では、閣下の前で失態を犯したジェーヴシキンが、その身なりのあまりの貧弱さに同情した閣下から服代として大金を貰うという、まさに彼が望んだように事態が発生する。こうして、閣下の恩恵によって、自分の借金も返済しワルワーラにお金を送ることもできたジェーヴシキンは窮状から脱することができたかに見えた。だが、そうはならず、既に見たようにワルワーラは彼の元から去っていくのである。つまり、ドストエーフスキイは、閣下の恩恵を得るというエピソードによって、ジェーヴシキンが夢みたような解決策が、実際には気休め的なものに過ぎないことを強く読者に訴えているのである。
こうして、ドストエーフスキイはジェーヴシキンに、『駅長』の語り手が「物事は位順」という規則を主張していると誤読させることにより、「ちっぽけな人間」を扱った『駅長』と『外套』を「社会秩序」という面でも強く結び付け、ジェーヴシキンの悲劇を通して当時の社会の不平等さを鋭く浮き彫りにしていると言えるだろう。
キルポーチンもドスエーフスキイが『貧しき人々』において『駅長』と『外套』とを取りあげたことによって、当時の文学者の内で一番早く両作品に見られるプーシキンとゴーゴリとの関係を示したと述べている。さらに、彼は「いや、これは作りごとじゃない! 読んでごらんなさい、まったく自然そのままです!」というジェーヴシキンの言葉に注目して、ドストエーフスキイはゴーゴリと共にプーシキンをも「自然派」の創始者の一人に入れたのであると述べ、ベリーンスキイがプーシキン論の中で「自然派」が「カラムジーンやドミートリエフからではなくプーシキンとゴーゴリから始まった」と記しているのは『貧しき人々』を読んでドストエーフスキイの見解の正しさを認めたからだろうと推測している(『ドストエーフスキイ』、露文)。
これらの指摘はドストエーフスキイのプーシキン理解が当時のロシアの文壇においてもラジカルなものであったことを裏付けているだろう。
第二節 「ネワ河の幻影」と『青銅の騎士』
こうして、ドストエーフスキイは『貧しき人々』において、当時の社会の不正義を痛烈に描いた。それと同時にこの小説においてドストエーフスキイは既に、都市ペテルブルクについての深い考察も行っており、その考察も深くプーシキン、ことに彼の後期の作品『青銅の騎士』と関わっているように見える。
すなわち、プーシキンはこの詩の序詩でまず、「汝を愛す、ピョートルの創れるものよ、汝のおごそかにも姿よい眺めを、ネワの威力ある流れを、その岸のみかげ石を、汝の柵の鋳鉄の唐草模様を…」(谷耕平訳)とその美しさを讃える。だが、それに続く二つの長詩ではペテルブルグを襲った大洪水で最愛の婚約者を失い、茫然として街をさまよい、ついにはペテルブルグの建設者ピョートル大帝を形どった「青銅の騎士」に追いかけられているという脅迫観念に駆られて狂気に陥った若い官吏エヴゲーニイの悲劇を歌いあげた。こうしてプーシキンは「ペテルブルグの史詩」という副題を持つこの作品で、ペテルブルグの持っている二面性を明らかにしたのである。さらに彼は主人公のエヴゲーニイが「自分が貧しいということ、働いて、自ら暮らしもたて、体面も、たもたねばならない」ことを痛切に自覚する一方で、「何もしない、しあわせな人間もあるではないか、思慮深からぬなまけ者、そのくせ生活のふしぎにも楽な」者たちがいることをも鋭く認識していたことをも指摘していた。
ドストエーフスキイもまた『貧しき人々』の中で夕暮れ時のフォンタンカの通りを歩く貧しい人々を克明に描写した後で、華やかなゴローホワヤ街やそこを馬車で通る金持ちの人々を描き出して、このような二面性を強調している。そして、このような描写の後で、ジェーヴシキンは「こんなことを考えてはいけない、これは自由思想だってことはわかっていますよ」と断りながらも「立派な人が荒野におきざりになっているのに、別の人には向うから幸福がとびこんでくるというのは、いったいどういうわけでしょう」と問いかけて社会的な不公平さを訴えていたのである。
そして、ペテルブルクの二重性は第二作『分身』においていっそう深く追求されており、グロスマンが指摘しているように、『分身』の主人公もプーシキンの『青銅の騎士』の主人公エヴゲーニイと同様に、「ペテルブルクにおびえきっており、その結果彼は発狂する」(『ドストエフスキイ』、北垣信行訳)のである。さらに、中編小説『弱い心』には、その内容だけでなく、表現のレヴェルでも『青銅の騎士』からの強い影響を見ることが出来るのである。
周知のように、『弱い心』の主人公ワーシャもまたエヴゲーニイと同じようにペテルブルグのコロムナという地区に住む若い官吏であり、プロポーズが受け入れられ許婚者との甘い結婚生活を夢みていた。しかし、幸せに有頂天になった彼は仕事が手に付かず、頼まれていた清書の仕事を期限までに仕上げられられなくなり、発狂に至るのである。ここには『青銅の騎士』のような半ば人災による洪水はなく、主人公の発狂も自分の気持ちを制することの出来なかった「弱い心」によるもののように見える。だが、ドストエーフスキイは最後に親友を失ったアルカージイがネワ河の辺で体験した次のようなエピソードをつけ加えている。
「ネワの河面は、針のような霜に名ごりの夕陽を反射して、幾千万とも知れぬ細かい火花を散らしていた。零下二十度からの凍が襲いかかっていた。…中略…両側の河岸通りに並ぶ家々の屋根からは、巨人のような煙の柱が立ちのぼって、互いに縺れたり、解けたりしながら、上へ上へと昇っていった。…中略…それどころか、この黄昏どきには全世界が、強弱すべての人間も、その住居もーー貧者のあばら家も富者の喜びである金殿玉楼も、何もかもひっくるめて、何かの夢のように」(米川正夫訳)思われた。
そして、この幻影を見たアルカージイの心に「奇妙な想念」が訪れる。「彼はぴくりとした。彼の心はこの瞬間、いままで経験したことのない、力強い感覚の刺激で、とつぜん沸き立った血の泉に浸ってしまった。彼はいまやっと初めて、この不安の感じがすっかりわかったように思われた。そして、なぜあの不幸なワーシャが、自分の幸福に堪えきれないで、発狂したかということを悟った」。この後、アルカージイは彼がワーシャと共に住んでいたコロムナの家から離れるのである。
ブラゴーイは、このアルカージイの気持ちの描写(傍線の箇所)とペテルブルグの建設者ピョートル大帝を形どった「青銅の騎士」の像の前に立ち、「よし、驚くべき建設者よ、今にみろ!」と憎しみにふるえてつぶやいたエヴゲーニイの気持ちの描写の間に重なるものが多いことを指摘し、状況の類似なども考え合わせればこれらの一致は全くの偶然とは言えないだろうと述べている。さらに、「何もかもひっくるめて、何かの夢のように」思われたという最後の箇所も『青銅の騎士』の中の「それとも、われらが人生などというものは、すべてむなしい夢に似て、天上のなす、地上への嘲笑である、というのか」(傍点筆者)というエヴゲーニイの感慨とも重なっているように思える。
ところで、アカデミー版全集の註は面白い事実を伝えている。それはこの小説がドストエーフスキイの友人のブートコフの生活のエピソードに基づいて書かれたものであり、ブートコフはワーシャという主人公の原型であると考えられ、小説の中ではアルカージイが骨身を惜しまず世話しているが、ドストエーフスキイ自身もブートコフに対して様々な形で面倒を見ていたという指摘である。
このように見る時アルカージイの形象とドストエーフスキイ自身との間にかなり深い係わりを見ても、それほど不自然ではないだろう。事実、アルカージイが見るこの「ネワ河の幻影」というモチーフは「ペテルブルグの夢」、『罪と罰』などで重要な意味を持ちながら度々用いられており、ことにフェリエトン「ペテルブルグの夢」の中では作者自身の感想として記されているばかりでなく、この幻影の後で『貧しき人々』の構想が浮かんできたことも記されているのである。そして、やはりアルカージイと名付けられた『未成年』の主人公もまた「ネワ河の幻影」について語っている。むろん、作者と作中人物をそのまま同一視することはできないにしても、ドストエーフスキイがアルカージイと名付けた登場人物の口を通してかなり率直に自分の心情を託しているとは言えそうである。
さらに、この小説の終わり近くには、この出来事にショックを受け、これは「かなり重大な出来事だから、このままうっちゃてはおけない」と告げて回るワーシャの同僚の男が出てくる。ドストエーフスキイはこの男が「熱狂的な自由思想家」として知られていたという初版にあった説明を一八六五年以降の版では削っているのである。(なお、ベリチコフは『分身』の改作の際にも、ドストエーフスキイが自由思想をめぐる議論を削除していることに注意を促している。『ドストエフスキイ裁判記録』、中村健之介訳)。このことは、『弱い心』を書いた時、ドストエーフスキイがこの「熱狂的な自由思想家」に託してこの出来事を鋭く批判していたことを物語っているように思える。すると、幻影を見た後のアルカージイの変化についてドストエーフスキイが書いている「この瞬間、何かある新しいものを洞察したような具合だった。……彼はそれから気難しい退屈な男になって、今までの快活さをすっかり失くしてしまった」(傍点筆者)という文章は、意味深である。この中編小説が発表された一八四八年がドストエーフスキイがペトラシェーフスキイのサークルとの関わりが深まった時期であり、この翌年に逮捕されることを考え合わせれば、「ある新しいものを洞察した」という表現は、ドストエーフスキイの決意表明とも受けとめられなくはないかもしれない。
第三節 「警告する」ものとしての「良心」
ところで、私達の興味をひくのは、この時期、すなわちドストエーフスキイがペトラシェーフスキイのサークルに近づいていた一八四八年に書かれた作品には比較的この単語が多く用いられ、しかも重要な意味を持っていることである。たとえば、賄賂の問題を扱った短編『ポルズンコフ』の中で主人公は、賄賂を取ったことを認めながら「たくさんよこしたかね?」という問いに対して、「まあ、現代人のあるものが自分の良心を、ありったけのヴァリエーションで売る、それくらいの額ですがね……ただし、良心に金を出すものがあれば、の話なんで。しかし、わたしは金をポケットへ入れた時、煮え湯を浴びせられたような気がしましたよ」と答えている(米川正夫訳)。あるいは、『正直な泥棒』ではその泥棒が「悲しみと良心」の痛みのせいで亡くなったと書かれていた(一八四八年版、後の版では省略された)。
そして、ドストエーフスキイは既に『貧しき人々』の中でジェーヴシキンに、いけないのは金持ちの耳元に口を寄せて「自分ひとりのことばかり考えるのは、自分ひとりのために生きていくのはたくさんだ」とささやく者がいないことだと書き記していた。『弱い心』では幸せのまっただ中にいる主人公が「良心がぼくを苦しめる」と語っており、その理由を親友のアルカージイは「自分一人だけが幸せになることがつらいのだ」と説明している。
ここで注目したいのは、プーシキンが『エヴゲーニイ・オネーギン』の中で「大胆な風刺の王であり自由の友」と呼び、ドストエーフスキイも後の裁判において、プーシキンと共に名前を挙げているフォンヴィージン(一七四五ー一七九二)における「良心」の用法である。すなわち、『旅団長』は登場人物の一人の「良心を持って暮らすことは辛いことだと言われているが、今度という今度は良心なしに生きるということが一番悪いということを身にしみて理解したよ」という言葉で終わる。一方、「自分一人だけが幸せだというようなことはありえない」という言葉も見つかる喜劇『親がかり』では、「誰もが美徳の人になれるのでしょうか?」という姪の問いに対して、スタロドゥームが「良心に責められることをしないこと」だよと答え、さらに「いいかい、良心は、いつでも友人のように、裁判官が罰するより一足さきに、警告するのだよ」と説明しているのである。
これらの作品で「良心」(共ー知)は、「心の裁判官」とでも言えるような働きをし、当時の法律では問われないがしかし自分の罪をとがめ、多少自分にとて不利な場合でも社会的な不公正には異議を唱え、さらには、不幸な人々を見捨てて自分一人だけが幸せになることに異議を唱える内面の声としてあらわれているといえるだろう。ドストエーフスキイのペトラシェーフスキイ・サークルへの積極的な参加は、こうしたドストエーフスキイの良心理解とも無縁ではなかった筈である。
一八四九年四月二三日未明、ドストエーフスキイは寝入りばなを起こされ逮捕された。その容疑はペトラシェーフスキイ・サークルの「集会に出席」し「出版の自由、農民解放、裁判制度の変更の三問題に関する討論に加わりゴロヴィンスキイの意見に賛成」したこと及び「ベリンスキイのゴーゴリへの手紙を朗読」したことであった。
このサークルの性格について、メンバーの一人アフシャルーモフはその回想記に次のように書いている。「週に一度ペトラシェーフスキイの所で集まりがあった。それはその時代の様々な事件、政府の施策、様々な学問分野の最新の著作などに関する多彩きわまりない意見の興味深い万華鏡のようなものだった。あらゆることがなんの気兼もなく大きな声で話題にされた。時々だれかが講義のような形でレポートをやった。ヤストルジェムプスキイが経済学について論じ、ダニレフスキイがフーリエの思想体系について語り、ある集まりではゴーゴリに宛てたベリンスキイの手紙がドストエーフスキイによって朗読された」(中村健之介訳)。
だが、ドストエーフスキイがここで読み上げたのは、ベリーンスキイの手紙だけではない。ドストエーフスキイの詩の朗読には定評があり、晩年にも「予言者」を始めとする多くのプーシキンの詩を朗読したが、この事件に連座して捕まえられたミリュコーフはドストエーフスキイが「おお、友よ、私は見るだろうか! 迫害されない人民を/ツァーリの命で 農奴身分の廃止されるのを/そして啓蒙された自由の祖国に/ついに美しい朝やけがおとずれるのを?」というプーシキンの政治詩『農村』をこのサークルでも朗読したと語っている。一八一九年に書かれたこの詩の構成は、前節で見た『青銅の騎士』の構成をも思い起こさせる。すなわち、ここでもプーシキンはまず、農村の風景の美しさを歌いあげる。だが、詩人の目は単に美しいものだけに留まらず、「おそろしい思いが心を暗くかげらせる」と続けて「ここでは 心になんの希望も好意もはぐくめずに、/だれもが 墓場まで重いくびきをひきずっていく」(草鹿外吉訳)と同じこの村の持つ二面性を厳しく指摘し、農奴制を厳しく批判しているのである。
ここには美の歌い手であると共に圧制に苦しむ人々に温かい眼差しを注いだプーシキンの詩才が既に現れているが、プーシキンはこの詩を含む一連の政治詩が原因で、シベリアに流刑になりかけ、友人たちの尽力で罪一等を減じられて南方のコーカサスへ左遷された。むろん、ドストエーフスキイがこのことを知らない筈はなく、ペトラシェーフスキイのサークルでこの詩を朗読した時、自分もまた危険を犯しながらもプーシキンと同じ理念を広めようとしているのだという、心の高まりを覚えたことであろう。
ところで、アフシャルーモフが挙げているベリンスキイの手紙とは、彼がそれまで高く評価していたゴーゴリが『友人達との行復書簡抄』を出版して、専制政治や教会そして農奴制や体刑までも擁護し、民衆にとって読み書きの知識は有害であるとすら説いたのを厳しく批判したもので、ベリンスキイはこの手紙で、「現在のロシアで最も焦眉の国家的課題は農奴制と体罰の廃止」であると述べ、「文学のみが、タタール的な検閲に苦しみながらも、いまだ活力と前途」を示していると主張した。
ドストエーフスキイは後に何故ベリンスキイの手紙を読んだのかという問いに対して「文学上の記念的作品」であるからと釈明するが、一読して分るように、ベリンスキイの遺言ともみられるこの手紙にはロシアの政治制度の苛酷さに対する激しいいきどおりがあふれている。そして、ドストエーフスキイも検閲制度に対するベリンスキイの見解や怒りをそのまま受け継ぐかのように、この検閲制度に対する批判を述べるのである。「検閲官は作家を、彼が何かを書きあげる以前に、既に何か政府に対する生まれながら敵のように見て、明らかに偏見をもって原稿を調べにかかること、ーーそれは私にとって気の迷入ることでした…中略…そのような状況では、実に多くの芸術分野が消滅せざるをえません。諷刺文学や悲劇はもはや存在しえません。現在のような酷しい検閲のもとでは、グリボエードフやフォンヴィージンのような作家、いやプーシキンでさえ存在できません」。
ここで、プーシキンの名前が出てきていることに注意を払いたい。第一節で『駅長』との関連でみたドストエーフスキイの文学観はこのすぐ後に書かれているからである。さらに、『貧しき人々』のジェーヴシキンは自分が自由思想家と見られることを極度に恐れていたが、ドストエーフスキイは監獄の中での尋問という状況の中で「自分は祖国に対して善いことを希う権利があるのだと感じている人、そういう人が全て自由思想家と呼ばれるのなら、それと同じ意味で私は自由思想家です」とはっきり言明しているのである。
そして、裁判において「如何なる事で私は罪ありとされているでしょうか? …中略…もし私に自分の個人的意見を述べる権利、あるいは強圧的な意見には同意しない権利が無いというのなら、何のために私は学んだのでしょうか」と鋭く問い返したドストエーフスキイは、後に刑場で死刑の判決を聞いた時にも「私達が裁かれた事柄、私達の精神をとらえた考えは、後悔を要しないものと思われたばかりか、何か私達を浄めるもののように、私達の多くのことを許してくれる殉教の対象のように」考えていたのだ。
この時、ドストエーフスキイの脳裏で、理想に燃えながら決闘で倒れたプーシキンの姿が自分の姿に重なりはしなかっただろうか。むろん、プーシキンだけに対象を絞ってしまうのは間違えだろう。しかし、プーシキンの死亡を知って喪に服したいと考えもしたドストエーフスキイは、ある意味でそれ以降ずっとプーシキンの理念を求めて歩んで来たとも言えそうだ。そして、理想のために死ねるのなら後悔するはずもなかったのである。

(セミョーノフスキー練兵場における死刑の場面、ポクロフスキー画。図版はロシア版「ウィキペディア」より)
第二章 「殺すこと」についての考察 ーー「良心」の問題をめぐって
第一節 「良心」の「自己流の解釈」
ドストエーフスキイたちの死刑は執行されず、シベリアへの流刑が決まる。長いシベリアでの監獄生活の後、ドストエーフスキイの考えは彼自身も認めているように大きく変わった。
その理由はいくつか考えられるが、ここでは、この論考のテーマとかかわると思われるものを三つあげておきたい。その第一の理由としては農奴の解放があげられるだろう。先に引用した『農村』という詩でプーシキンが望んだように、農奴はまさに皇帝の命令で解放されたのだった。そして、第二には、理想としていたヨーロッパの国々を旅行したことにより、ドストエーフスキイはあまりにも理想とはかけ離れたその現実をじかに己の目で観察したのであった。そして、第三にはドストエーフスキイがシベリアに流刑になる前に身をもって死の恐怖を体験させられたことがあげられるだろう。恐らくそのことによって彼は「殺すこと」について深く考えさせられ、さらに、『罪と罰』において「良心に従って血を流す事は可能か」という形で問われるように、「良心」について根本的な反省を強いられたのではないだろうか。
この章では「殺すこと」に対するドストエーフスキイの考察の深まりをプーシキンの作品とのつながりを検証しながら調べてみたいが、まず最初に、何故「殺す事」と「良心」の問題が係わってくるのかを、ドブロリューボフとの係わりを通して見ておきたい。
シベリア流刑後にドストエーフスキイが関心を示した劇作家にオストローフスキイがいるが、彼はその処女作『身内のものは後勘定』で、金儲けの為には手段を選ばぬ主人の策謀を利用して一儲けしようとする手代に「良心をわきまえなきゃならぬと人がいう、そうだ、もちろんのこと良心はわきまえなければならない、でもこれをどんな意味にとったらいいか。立派な主人に対してはどんな人間でも良心をもっている、だが主人自身が他人をだましているのでは、この場合どんな良心がありうるだろう」と語らせていた。ドブロリューボフはその評論において、この言葉を引用しながら、この手代について「(彼は)人非人ではなく、彼でも良心は知っている、ただしそれを自己流に理解しているだけである」(石山正三訳、傍点筆者)と述べた。こうして、ドブロリューボフはこの評論の中で、はっきりと良心の重要性ばかりでなく、悪人にも「良心」を「自己流に理解」する可能性があることも指摘しえていたのである。
この評論集が出た一八五九年は、ドストエーフスキイが流刑から戻って再び文学活動に力を注ぎ出した頃であるが、「良心」を「自己流に理解」する可能性があるというドブロリューボフの指摘はドストエーフスキイに強い関心を抱かせたはずである。なぜならば、ドストエーフスキイは、彼がシベリアに流刑される前に書いた手紙で「私は自らの正しさを信じておりました。私は何もかも自供するということはしませんでした。そしてそのために刑は重くなったのでした」と書き、さらにそれ程長くない文書での釈明の中で「もし私が誤りを犯していたらどうなるのでしょう? 誤りは良心の問題なわけです」と述べ、さらに「これが私が与えられた質問に対し、良心にかけて答えることができることであります」と自分の証言の正しさを良心にかけて誓っていたのである。
この点で私達の興味をひくのはペトラシェーフスキイ事件における若きドストエーフスキイの言葉とラスコーリニコフの言葉との類似である。たとえば、ラスコーリニコフは「だが、いったい何のために自首しに行くのか、自分でもわからない。罪? いったいどんな罪だい。……あんな貧乏人の汁を吸っていたばばあを殺すのはかえって四〇の罪が許される位だ」(米川正夫訳)とドーニャに語るが、ドストエーフスキイもまた裁判の場において「私が罪ありとされる背徳・有害・反逆性の程度を誰が量ったのでしょう。その計量はどんな尺度でなされるのでしょう」と、却って「罪」とは何かを鋭く問い返していたのである。
むろん、ドストエーフスキイとラスコーリニコフの両者が罪に問われた状況は全く異なる。前者が罪に問われたのは農奴の解放、言論の自由、裁判制度の改革など今日から見ればきわめて穏当な要求であるのに対し、後者は殺人を犯しているのだ。だが、『罪と罰』の中でポルフィーリイは「あなたが、ただばあさんを殺しただけなのは、まだしもだったんですよ。もしあなたがもっとほかの理論を考え出したら、それこそ百億倍も見苦しいことをしでかしたかもしれませんよ」とラスコーリニコフに語っているが、両者に共通するのは、自分の思想は正しいという確信であり、良心に照らして見れば、裁き手よりも自分の方が正しいという思いなのである。
そして、彼の言葉は殺人を犯さなかった若きドストエーフスキイにも当てはまるように思える。つまり、幸い露見せずに容疑の中には入らなかったが、秘密印刷所の開設の必要性を説いた時ドストエーフスキイは「この事業の神聖さについて大いに雄弁をふるいました」と述べたとマイコフは伝えており、またペトラシェーフスキイ・グループの一員だったパーリムは「ある時、議論が『もしも農奴解放は暴動による以外は不可能であるとわかったら?』ということになった。その時、ドストエーフスキイは、例の激しい反応の仕方で、『それならば、暴動によってでも!』と叫んだ」と伝えているが、この時期ドストエーフスキイは自分たちの思想を実現するためには、もしそれ以外に方法がなければデカブリストたちのようにほう起によって、言葉を代えれば、血を流してでも農奴制を覆そうと考えていたように思える。
そしてドストエーフスキイ自身も深くこの事を意識していた。たとえば彼は後に『作家の日記』の中で、自分達のサークルと秘密結社「五人組」を組織し「政府に密告する恐れがある」という理由で会員の一人を殺したネチェーエフのサークルとを比較しながら、自分達がネシャーエフのグループの人間に成れるかと自問してこう答えているのである。「自分一人のことを言わしてもらえば、恐らく、私はネチャーエフの徒の一人には、断言はできないが、成ったかもしれない。青年時代の私なら、成ったであろう」。
このように見てくる時、ドストエーフスキイが、「良心」とは何かについて深い反省を行なうのはきわめて必然的だったと言えるだろう。『罪と罰』の中で問題にされる「良心に従って血を流すことは可能か」という命題は単に抽象的なものではなく、ドストエーフスキイ自身の体験と密接に結びついたドストエーフスキイの身を焦がすような問いだったのである。
ドストエーフスキイはドブロリューボフの論文に対する直接の論評を書いてはいないが、彼について触れながら「目的と手段」の問題を論じた一八六二年の論文からはその影響が見て取れるように思える。これは『時代』の編集者には明らかに良心が欠けていると指摘した質問者に対する反論の形で書かれているのだが、ドストエーフスキイはまず「真理のための闘士」も、「誤りを犯して、でたらめをいうこともある」のだと言い、「その生活からいえば、ほとんど義人といっていいほどで、深く神聖に真理を確信している」りっぱな人物が、「ただただ自分の高潔無比な目的を達せんがために」「壁に頭をぶっつけはじめる」ことだってあると主張する。そして、「この人物の誤り」は「彼が目的到達のために用いた手段に存する」ことは明瞭であると述べ、彼は「手段の点でのみ誤ったのである」と説明している(米川正夫訳)。
さらに、ドストエーフスキイは「天才的な人間でも、自分の思想を実現する際、しばしば誤るものである。しかも、天才的であればあるほど、その誤りも大きくなる」と続け、その例をドブロリューボフにも求めて彼の民衆観を批判しながら、「彼の誤りそのものさえ時とすると、彼の精神的欲求があまりにも熱烈であったためかもしれない」と述べ、質問者は「このように重大な非難を他人に向けるには、もっと注意ぶかく、良心的であるべきである」と結んでいる。
ドストエーフスキイ自身も認めているように「壁に頭をぶっつけはじめる」という比喩は「乱暴」である。だが、この言葉を一層「乱暴」な「人を殺しはじめる」という表現言い換えれば、ドストエーフスキイがここで述べていることは、『罪と罰』のテーマとほとんど重なるようにみえる。「真理への愛に貫かれた聡明な人間」が、ポトハリュージンのように「良心」を「自己流に理解」したなら、ラスコーリニコフの悲劇が発生するであろう。極限すれば、この文脈のなかでドブロリューボフの代わりにラスコーリニコフを入れれば長編小説『罪と罰』はその思想的な骨格を既に得ることになるとも言いえるように思える。
第二節 『地下生活者の手記』と『その一発』
ところで、ドストエーフスキイが『分身』を「徹底的に書き改めようとした」一八六一年にドブロリューボフの『打ちひしがれた人々』が出版された。彼は『虐げられた人々』までのドストエーフスキイの作品を論じたこの評論で『分身』をも取り上げ、この作品のテーマが「行動における小心な正直さと、陰謀に対する理論的な欲求との分裂」であると指摘して、このテーマの重要性と現代性に注意をうながした。さらに、ドブロリューボフは、この作品を高く評価し、よく手を入れられるならば、ゴリャートキンは単なる奇妙な人物ではなく、現代人のよくあるタイプの一つが生まれるだろうと書いた。ドブロリューボフはこの評論を書いた一八六一年に二五歳の若さで亡くなるのだが、ドストエーフスキイは彼の予言を裏付けるように、創作ノートの中でゴリャートキンは「地下室の男」の原形になったと書く。そして、『地下生活者の手記』(一八六四)において、その主人公「地下室の男」を「最近の時代に特徴的であったタイプの一つ」と言い、「いまなおその余命を保っている一世代の代表者なのである」とドブロリューボフの表現をほぼ踏襲して主人公を性格付けているのである。
その意味で、『分身』の改作のためのノートに「新ゴリャートキンは、まるで旧ゴリャートキンの良心の権化であるかのように、旧ゴリャートキンのすべての秘密を知っている」という文章が書かれているのは、ドブロリューボフをめぐるドストエーフスキイの考察と無縁ではないように思える。
なお、『分身』の創作ノートには将軍を決闘に呼び出すが、撃ち合う寸前に「閣下、私は満足です」とゴリャートキンが述べるというエピソードも記されている。この構想は実現されなかったが、『地下生活者の手記』において自尊心を傷付けられた主人公が、様々な復讐の方法を思いめぐらし、「空に向けて発砲」した後に行方も知れずに去って行こうと考える場面でいかされている。そして、ドストエーフスキイはその発想がプーシキンの『その一発』にも負っているということを、主人公が「正確に知り抜いていた」と書き記している。
ところで、ウージンは『ベールキン物語』の中の『その一発』とドストエーフスキイの作品との内的な深い関わりに注目している。すなわち、この作品の主人公シリヴィオはかって平手うちにされた伯爵と決闘ざたになったが、相手が射ち損じ、いざ自分が射つ番になっても相手が桜んぼうを食べているのに腹を立て、自分の射つ権利を後に延ばして機会を窺う。数年後、伯爵が結婚するという知らせを受けるや、彼は勇躍相手の元へと出かけて行くのだ。そして、幸せに暮らしている相手を見つけると、自分の残されていた権利を要求し、じっくりを狙いを定める。彼の腕前をすれば相手には確実な死が待っているはずであった。だが、彼はすぐには撃たずに二度も中断して、伯爵をさんざん待たせ、死の恐怖を味あわせた後に「僕は満足した。僕は君の取り乱したところも怖気付いたところも、とっくり拝見した…中略…君の身柄は君の良心に預けておくとしよう」(神西清訳)と言い残して去って行くのである(傍点筆者)。
ウージンはこの「良心」という単語の用法に注意を払って「ここにいるのはもはや復讐者ではなく、公平で厳しい裁判官である。彼は伯爵に「良心」を返して、生命の尊厳とその意味を悟った以上、伯爵は生き続けることができるという、判決を告げるのである」と指摘し、さらに「この有名な場面」の「ゆっくりしたテンポ」に注目して、それはシリヴィオが実験者のように、人間の生命の秘密を解こうとして、実験の結果を確実に計測しようとして注意深く、冷静に観察しているためだと主張している。ポドドーブナヤは「ウージンの解釈がプーシキンの『その一発』のテキストにどれ程近いかは別にしても」と断定を避けながらも、「シリヴィオの行為をこのように解釈すれば、この決闘の場面自体がまさしくドストエーフスキイ的であるとは言える」(『ドストエーフスキイ、資料と研究』、第八巻、露文)と述べている。
だが、私たちはウージンの読みがプーシキンの意図にも重なるのと断言してもよいように思える。たとえば、この作品『その一発』には「余は決闘の認むる当然の権利によって彼を射ち殺さんと心に誓った…後略」というエピグラフがあり、この作品でもプーシキンがかなり復讐のテーマを意識していたことが分かるが、浅岡氏は「復讐の権利を主張する」主人公の考えが、当時のジプシーの社会ばかりでなく「少なくとも西欧文明社会では歴史的に広く、根強く支持されてきた思想である」ことを確認して、次のように結論している。プーシキンは「当然の権利として認められた《血の復讐》」の問題を取り上げることによって、「《良心の呵責》を受けることなく」それが可能か否かを問いかけ「《血の復讐》の不当性を追求」したのではないか(浅岡宣彦、「『ジプシー』に於ける復讐のテーマ」)。
すなわち、プーシキンは一八二四年の時点で既に「血の復讐」を厳しく批判していたのだ。その意味で「殺される瞬間」を冷静な観察者の眼で描いた『その一発』(一八二八年)は、「血の復讐」についてのプーシキンの考察の一つの到達点であるとも言い得るのではないだろうか。なお、この作品の冒頭近くでは「決闘したことがあるか」という問いに対して、シルヴィオが不快そうに「ある」と答えたことから「どうやらその良心には、何者か彼の戦慄すべき腕前の不幸な犠牲者が横たわっているらしい」(傍点筆者)という記録者の感想が記されている。ここでは「良心」という言葉もまだそれほどの重みを持ってはいない。だが、結末近くでこの言葉は「その一発」を発射することを止めたシルヴィオ自身によって「きみの身柄はきみの良心に預けておくとしよう」という形で繰り返されることにより、殺したことに対する反省が暗示されているのだ。
『地下生活者の手記』の中で『その一発』に言及したドストエーフスキイは、『罪と罰』において殺人者ラスコーリニコフの心理を詳しく描き出し、『白痴』では「ところが、死刑では、それがあれば十倍も楽に死ねるこの最後の希望を、確実に奪い去っているんですからね。…中略…いや、この世にこの苦しみよりひどい苦しみはありませんよ」とムイシュキンは殺される者にほとんどなりきり、彼の意識を通して殺される瞬間の苦しみを述べているのである。これらの描写はウージンの読み方の正確さを裏付けているだろう。このように見てくる時、哲学的な小説『地下生活者の手記』の中にシルヴィオの名前が出てきたのは、単なる偶然とは言えないだろう。そして、ドストエーフスキイは地下室の男に、「現代の人間」は奴隷を虐待したクレオパトラの行為を野蛮だと言うが、ナポレオン戦争や南北戦争では、理念や理想の名のもとに「血は川をなして流れている」ではないかと批判させている。ドストエーフスキイは『その一発』の場面に単に復讐の深い心理を読みとっただけではなく、「殺すこと」に対するプーシキンの深い考察を見ていたと断言してもよいと思われる。
第三節 『罪と罰』と『スペードの女王』
ところで、プーシキンが「殺すこと」の問題を良心との関わりの中で考えたのは作品『ジプシー』や『その一発』のみにとどまらない。
序章で見た『吝嗇の騎士』には、男爵が金櫃を開けながら「世の中には/殺人にも快感を覚える手合いがいる、という。/わしも、こうして、錠前に鍵をさしこむとき、/人殺しどもが生け贄にナイフを突き立てるときに、感じるのと/同じ感覚を味わうのだ」と不遜にも呟くばかりでなく、「良心、それはこころをかきむしる、鋭い爪をもった獣、/良心、それは招かざる客、こうるさい話あいて、/…中略…その良心の呵責を知らぬというのか?……」と独白している箇所がある。また、初期の物語詩『盗賊の兄弟』でも、「短剣と暗い夜」を友として多くの悪事を働いていた弟が病に侵された時、「良心の呵責」に襲われ「眼の前に幻がむらがり」、なかでも、かつて「切り殺した老人の姿が、ことしげく 彼の心にやってきた」と書かれている。あるいは、『ボリス・ゴドゥノフ』でも皇位に就くために幼い皇太子を殺したボリスの「耳のなかでは、鉄槌でたたくように、非難の声がひびく。…中略…血まみれ少年たちの姿がまぶたに浮かぶ…中略…まこと、良心の汚れた人間はあわれなものだ」という苦しみの独白が書かれている。
だが、ことに私達の興味をひくのは、『未成年』の主人公アルカージイが「これは稀に見る偉大な創造で、完全にペテルブルグ人の一典型」であると規定した、『スペードの女王』の主人公ゲルマンの形象と彼の良心理解である。後に見るようにゲルマンの良心理解は、ラスコーリニコフの良心理解と深いところで結びついているように思える。
よく知られているように、ゲルマンは堅実な生活を送っていたが、たまたま友人の祖母がカルタで絶対に勝てる方法を知っているという話を聞いた彼は、何とかその秘密を知り大金を得ようとする。彼は老婆の養い子リーザを利用して老婆の屋敷に忍び込み秘密を聞き出そうとして、心ならずも彼女を死に至らせ、自分も後に狂気に陥るのである。
良心理解の問題を別にしても、彼とラスコーリニコフとの間には、幾つかの類似点がある。たとえば、前者の横顔がナポレオンに似ていると描かれているのに対し、ラスコーリニコフの理想もナポレオンになることと記されている。あるいは、両者がともに「確実に」大金を得ることができると知った時に行動に踏み切ること、また、老婆に誠心誠意仕えながら主人公の犠牲になる若い女性は共にリザヴェータという名前である。そして、『スペードの女王』の中には殺された老婆が笑うシーンがあるが、ラスコーリニコフの多くの夢の中でも「殺された老婆が笑う夢」はきわめて印象深いのである。
このように見て来るとき『罪と罰』が『スペードの女王』から多くの啓示を受けて書かれたのは明らかであり、ドストエーフスキイもまた小説の中でそれを認めているように思える。そして、このことは『罪と罰』における「良心」の考察についてもあてはまるように見える。ドストエーフスキイはペテルブルクを舞台とした長編小説『罪と罰』において、「殺すこと」と「良心」の問題を「良心に従って殺す事は可能か」という形で深く考察しているが、プーシキンもまた「ペテルブルク人の一典型」であるゲルマンの良心理解について、何度か言及しているのである。むろん、短編小説『スペードの女王』に「良心」という単語が頻繁に用いられるということはないが、それでも重要な場面で用いられており、その中には『罪と罰』における「良心」の用法を想起させるようなものもある。以下、最初に『スペードの女王』における良心の用法を分析し、『罪と罰』の中の用法と比較してみたい。
最初に良心という言葉が用いられるのは、リーザとの逢引を約束して忍び込んだゲルマンが自室へと階段を登っていく彼女の足音を聞いたときで「彼の心には、良心の呵責めいたものがちょっと感じられたが、たちまち静まってしまった」(中村白葉訳)と書かれている。
次に用いられるのは、その晩の舞踏会の席でリザヴェータに語ったトームスキイのゲルマン評の中でであり、そこで彼はゲルマンについて「横顔はナポレオン、心はメフィストフェレス」と評した後で、「彼の良心には、すくなくとも三つの罪業があるね」と語る。しかし、それがどのような「罪業」なのかは、話題が変わり語られていない。
だが、その夜リザヴェータの元にゲルマンが現れ、老伯爵夫人を殺してしまったようだと告白する。リザヴェータは先ほど語られた言葉を思い出す。彼女はゲルマンの本音を知って「辛い後悔」に激しく泣きだす。だが、ゲルマンは「死んだ老夫人のことを思っても、良心の呵責は覚えなかった」。
こうして、ゲルマンは嘆き悲しむリザヴェータを残して去っていく。だが、そんな彼でもその三日後に行なわれた故伯爵夫人の葬儀には参加した。なぜならば「後悔は感じなかったものの、それでもやはりーー貴様は老婆殺しだと繰り返す良心の声を、完全におさえてしまう術もなかったからである」。
このように見て来る時、ゲルマンの「良心理解」に三つの段階を見て取ることが出来る。すなわち、最初ゲルマンは自分が行なおうとすることに「良心」の傷みを全く感じていない。そして、老婆を殺してしまった後でも、「良心の呵責は覚えなかった」のである。だが、彼は後悔は感じなかったが、「良心の声」にせき立てられて、葬儀に参列したのだった。
このようなゲルマンの良心理解は、ラスコーリニコフのそれとほとんど重なっていると言っても過言ではあるまい。ラスコーリニコフもまた自分の行なおうとすることに「良心の傷みは感じていなかった」し、かえって高利貸しの老婆を殺すことが正しいと考えていたのだ。そして、シベリアでも「彼は峻厳に自己をさばいてみたけれど、たけり狂った彼の良心は…中略…自分の過去にかくべつ恐るべき罪を見いださなかった」。しかし、それにもかかわらず、「良心の呵責が、にわかに彼を悩ましたような」感触がラスコーリニコフを襲うのである。
プーシキンはゲルマンに彼独自の思想や良心についての見解を述べさせてはいない。しかし、自分の思想や欲望に捉えられたとき、人間が「殺すこと」すらも厭わないことに、鋭い危機感を抱いたドストエーフスキイは、プーシキンが『スペードの女王』の中で展開した一見何気ないような、ゲルマンの良心理解に深い興味と理解を示し、それを『罪と罰』の中で展開し、さらに深めたと言えるのではないだろうか。
この意味で興味深いのは百万長者のロスチャイルドになることを「自分の理想」とした『未成年』の主人公アルカージイの次のような考察である。「なにか頭の中に常に動かぬ強いものをもっていて、それにすっかり熱中していると…中略…まわりに起こるいっさいのことがその本質にふれずにすべりぬけてしまうものである。印象でさえもゆがめられたものになる。しかも、その上、もっとも悪いのは、いつも言い訳ができることである…中略…『なに、おれには『理念』がある、それ以外はみな些細なことさ』ーーこう自分に言い聞かせればすむらしい」。ここで「理想」の箇所に「大金持ちになること」をいれればゲルマンの、「ナポレオンになること」を入れればラスコーリニコフの心理のきわめて的確な描写になると言えるだろう。
ドイツの哲学者H・クーンは、「良心」が誤る可能性を否定したカントやフィヒテの説を引用しながら「誤りえない良心という説は良心を余りにも高揚させるがために、良心が良心たることをとめてしまう」と批判し、さらに「良心の迷誤には多くの形態がある」ことを指摘しながら、その主な原因は「思惟者がその根本原理にもとずいて定式化した良心」に、「あたかもそれが良心そのものであるかのごとくに、頼ることにある」(『存在との出会い』、斎藤博、玉井治訳)と分析している。論理的で説得力に富むクーンのこのような良心論は、恐らくナチズムに対する深い内省に支えられていると思われるが、ドストエーフスキイは既に『罪と罰』においてラスコーリニコフの「良心」理解を通して、誤った思い込みに陥った時の危険性を鋭く指摘していたのである。すなわち、ラスコーリニコフは「自然法則に従って」人類が「凡人」と「非凡人」とに分かれていると述べた後に、「非凡人」は「ある種の障害を踏み越えることを自分の良心に許す権利」を持っており、非凡人は「自分の内部で、良心に照らして、血を踏み越える許可を自分に与える」のだと説明しているのであり、ここでも「自分の内部で」と記されているように、自分の良心の自律性が明白に主張されていたのである。
ベルジャーエフは「何びともドストエーフスキイ以前、彼ほどに良心の呵責と悔恨を研究したものはいなかった」(『ドストエーフスキイの世界観』、宮崎信彦訳)と書いたが、確かにドストエーフスキイは、プーシキンの良心理解を深めながら、『罪と罰』において、「良心」理解が誤った思いこみに陥った際の危険性を鋭く指摘したのである。それは多くの核兵器を有しながら、イデオロギーや宗教、国益の違いなどからなおも争いを続ける「現代」の持つ危険性をも鋭く予言しえていたと言えるであろう。
そして、ムイシュキンが「骨の髄まで悪のしみこんだ者でも、やはり自分が犯罪者であるということを知っているんですね。つまり、まるっきり後悔をしていないにしろ、自分の良心に照らして悪いことをしたと考えているんですよ。…中略…(ところが思想に基づいて殺した者はーー筆者)自分のことを犯罪者と考えようとしないばかりか、そうする権利があったのだ……いや、自分のしたことは善いことだ……と、まあ、そんなふうに考えているんですからねえ」と語っているように、「良心」と「思想」の問題は、『白痴』においてもしっかりと受け継がれているのである。
『未成年』のアルカージイは「もっとも簡単で、もっとも明白な思想ーーこういうものこそ理解が難しいのである」と言っているが、恐らく、ムイシュキンが聖書から引用した「殺すなかれ」という思想もそれにあてはまるだろう。ムイシュキンはこの言葉を引用しながら、「人が人を殺したからといって、その人を殺してもいいものでしょうか? いいえ、絶対にいけません」と続けている。
大規模な戦争の危険性が未だに存在する現在、私達もドストエーフスキイとともに「殺すな」という思想について、もう一度じっくり考えねばならないように思える。
註
ドストエーフスキイの作品からの引用は次の全集に依りました。
一、『ドストエフスキー全集』、新潮社
二、『ドストエーフスキイ全集』、河出書房新社
また、プーシキンの作品からの引用は、河出書房新社版『プーシキン全集』の他に、『スペードの女王』、『ベールキン物語』、『エヴゲーニイ・オネーギン』は岩波文庫版、『青銅の騎士』は筑摩書房版、『世界文学体系』を利用させて頂きました。なお、引用などに際しては、原則として表記を統一しました。

(『ドストエーフスキイ広場』創刊号、1991年)