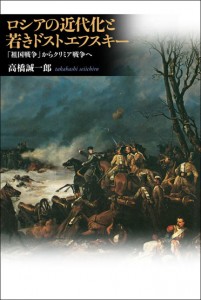リンク→「主な研究(活動)」タイトル一覧Ⅱ
リンク→「主な研究(活動)」タイトル一覧
あとがきに代えて──小林秀雄と私
「告白」の重要性に注意を払うことによって知識人の孤独と自意識の問題に鋭く迫った小林秀雄のドストエフスキー論は、それまで高校の文芸部で小説のまねごとのような作品を書いていた私が評論という分野に移行するきっかけになった。原作の文章を引用することにより作品のテーマに迫るという小林秀雄の評論からは私の文学研究の方法も大きな影響を受けていると思える。
『カラマーゾフの兄弟』には続編はありえないことを明らかにしていただけでなく、「原子力エネルギー」の危険性も「道義心」という視点から批判していた小林の意義はきわめて大きい。
しかし「『罪と罰』についてⅠ」で、「罪の意識も罰の意識も遂に彼(引用者注──ラスコーリニコフ)には現れぬ」と書いた小林秀雄が、「『白痴』についてⅠ」で「ムイシュキンはスイスから帰つたのではない、シベリヤから還つたのだ」と記していたことには強い違和感を覚えた。
さらに、小林秀雄のドストエフスキー論を何度も読み返す中で、原作から多くの引用がされているがそこで記されているのは小林独自の「物語」であり、これは「創作」ではないかという深刻な疑問を持つようになった。
ただ、これまで上梓した著作でほとんど小林秀雄に言及しなかったのは、長編小説『白痴』をきちんと読み解くことが意外と難しく、イッポリートやエヴゲーニーの発言に深く関わるグリボエードフの『知恵の悲しみ』やプーシキンの作品をも視野に入れないとムィシキンの恩人やアグラーヤの名付け親など複雑な人物構成から成り立っているこの長編小説をきちんと分析することができないことに気づいたためである。
『黒澤明で「白痴」を読み解く』(成文社、二〇一一年)でようやく黒澤監督の映画《白痴》を通してこの長編小説を詳しく分析したが、小林秀雄のドストエフスキー論について言及するとあまりに議論が拡散してしまうために省かざるをえなかった。
少年の頃に核戦争の危機を体験した私がベトナム戦争のころには文学書だけでなく宗教書や哲学書なども読みふけり、『罪と罰』や『白痴』を読んで深い感銘を受けたことや、『白痴』に対する私の思いが揺らいだ際に「つっかえ棒」になってくれたのが黒澤映画《白痴》であったことについては前著の「あとがき」で書いた。ここでは簡単に小林秀雄のドストエフスキー論と私の研究史との関わりを振り返っておきたい。
* * *
小林秀雄は、戦後に書いた「『罪と罰』についてⅡ」で、「ドストエフスキイは、バルザックを尊敬し、愛読したらしいが、仕事は、バルザックの終つたところから、全く新に始めたのである」と書いた。そして、「社会的存在としての人間といふ明瞭な徹底した考へは、バルザックによつてはじめて小説の世界に導入されたのである」が、「ドストエフスキイは、この社会環境の網の目のうちに隈なく織り込まれた人間の諸性格の絨毯を、惜し気もなく破り捨てた」と続けていた。〔二四八〕
しかし、知識人の自意識と「孤独」の問題を極限まで掘り下げたドストエフスキーは、バルザックの「社会的存在としての人間」という考えも受け継ぎ深めることで、「非凡人の理論」の危険性などを示唆していた。この文章を読んだときには小林が戦争という悲劇を体験したあとでも、自分が創作した「物語」を守るために、原作を矮小化して解釈していると感じた。
それゆえ、修士論文「方法としての文学──ドストエフスキーの方法をめぐって」(『研究論集 Ⅱ』、一九八〇年)では、感覚を軽視したデカルト哲学の問題点を批判していたスピノザの考察にも注意を払いながら、社会小説の側面も強く持つ『貧しき人々』から『地下室の手記』を経て『白痴』や『未成年』に至る流れには、シェストフが見ようとした断絶はなく、むしろテーマの連続性と問題意識の深まりが見られることを明らかにしようとした。
上梓した時期はかなり後になったが、厳しい検閲制度のもとで戦争の足音が近付く中で、なんとか言論の自由を確立し農奴制を改革しようとしたドストエフスキーの初期作品の意味をプーシキンの諸作品などとの関わりをとおして考察した『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』(成文社、二〇〇七年)には、私の大学院生の頃の問題意識がもっとも強く反映されていると思える。
ラスコーリニコフの「罪の意識と罰の意識」については、「『罪と罰』における「良心」の構造」(『文明研究』、一九八七年)で詳しく分析し、その論文を元に国際ドストエフスキー学会(IDS)で発表を行い、そのことが機縁となってイギリスのブリストル大学に研究留学する機会を得た。イギリスの哲学や経済史の深い知識をふまえて、『地下室の手記』では西欧の歴史観や哲学の鋭い批判が行われていることを明らかにしていたピース教授の著作は、後期のドストエフスキー作品を読み解くために必要な研究書と思える(リチャード・ピース、池田和彦訳、高橋編『ドストエフスキイ「地下室の手記」を読む』のべる出版企画、二〇〇六年)。
この時期に考えていた構想が『「罪と罰」を読む──「正義」の犯罪と文明の危機』(刀水書房、一九九六年、新版〈追記――『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』〉、二〇〇〇年)につながり、そこでラスコーリニコフの「良心」観に注意を払いつつ、「人類滅亡の夢」にいたる彼の夢の深まりを考察していたことが、映画《夢》の構造との類似性に気づくきっかけともなった。
日露の近代化の類似性と問題点を考察した『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』(刀水書房、二〇〇二年)でも、雑誌『時代』に掲載された『虐げられた人々』、『死の家の記録』、『冬に記す夏の印象』などの作品を詳しく分析することで小林秀雄によって軽視されていた「大地主義」の意義を示そうとした。
プーシキンの『ボリス・ゴドゥノフ』については授業では取りあげていたが、僭称者の問題を扱う予定の『悪霊』論で本格的に論じようとしていたためにこれまで言及してこなかった。今回、この作品における「夢」の問題にも言及したことで、『罪と罰』から『悪霊』に至る流れの一端を明らかにできたのではないかと考えている。
「テキスト」という「事実」を自分の主観によって解釈し、大衆受けのする「物語」を「創作」するという小林の方法は、厳しい現実を直視しないで威勢のよい発言をしていた鼎談「英雄を語る」*などにおける歴史認識にも通じていると思える。このような方法の問題がきちんと認識されなければ、国民の生命を軽視した戦争や原発事故の悲劇が再び繰り返されることになるだろう。
「『罪と罰』をめぐる静かなる決闘」という副題が浮かんだ際には、少し大げさではないかとの思いもあった。しかし、本書を書き進めるにつれて、映画《白痴》が小林の『白痴』論に対する映像をとおしての厳しい批判であり、映画《夢》における「夢」の構造も小林の『罪と罰』観を生涯にわたって批判的に考え続けていたことの結果だという思いを強くした。黒澤明は映画界に入る当初から小林秀雄のドストエフスキー観を強く意識しており、小林によって提起された重たい問題を最後まで持続して考え続けた監督だと思えるのである。
時が経つと不満な点も出て来るとは思うが、現時点では本書がほぼ半世紀にもわたる私のドストエフスキー研究の集大成となったのではないかと感じている。
黒澤明監督を文芸評論家・小林秀雄の批判者としてとらえることで、ドストエフスキー作品の意義を明らかにしようとした本書の方法については厳しい批判もあると思うので、忌憚のないご批判やご助言を頂ければ幸いである。
*注 1940年8月に行われた鼎談「英雄を語る」で、「英雄とはなんだらう」という同人の林房雄の問いに「ナポレオンさ」と答えた小林秀雄は、ヒトラーも「小英雄」と呼んで、「歴史というやうなものは英雄の歴史であるといふことは賛成だ」と語っていた。
戦争に対して不安を抱いた林が「時に、米国と戦争をして大丈夫かネ」と問いかけると小林は、「大丈夫さ」と答え、「実に不思議な事だよ。国際情勢も識りもしないで日本は大丈夫だと言つて居るからネ。(後略)」と続けていたのである。この小林の言葉を聴いた林は「負けたら、皆んな一緒にほろべば宣いと思つてゐる」との覚悟を示していた。(「英雄を語る」『文學界』第7巻、11月号、42~58頁((不二出版、復刻版、2008~2011年)。
(2014年5月3日、注の加筆:7月14日)