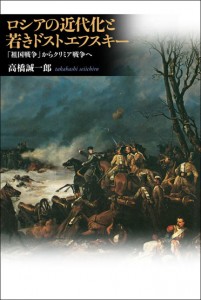徳富蘇峰の「教育改革」論
徳冨蘆花の「謀叛論」の講演から強い影響を受けていた成瀬正一が、芥川龍之介などの『新思潮』の同人をさそって、第一次世界大戦中に反戦論を唱えていたロマン・ロランの『トルストイ』を翻訳して一九一六(大正五)年に出版すると、それは新聞にも紹介記事が載るなどの大きな反響を呼んだ*22。
このような若者たちの動きに立ちふさがったのが、『軍人勅諭』や『教育勅語』の発布によって、「国権」の強化を果たした山県有朋の後ろ盾を得て、軍部とのつながりも強めていた徳富蘇峰だった*23。すなわち、彼は一九一六年に『大正の青年と帝国の前途』を著して、「我が青年及び少年に歓迎せらるる書籍、及び雑誌等は、半ば以上は病的文学也、不完全なる文学也」とし、大正青年に共通する特色は、「彼ら一切の青年を統一す可き、中心信条」がないことであると断定した。そして、相変わらず自分の新聞を『国民新聞』と名づけつつも、「されば帝国臣民の教育は、愛国教育を以て、先務とせざる可らず」として、「国民」を「臣民」と位置づけた蘇峰は、「日本魂」を「忠君愛国の精神」であるとし、青年が「日本帝国に全身を」献げるような「教育改革」の実施を求めたのである*24。
しかもここで西欧列強の「二重性」を批判しつつ、「白閥を打破し、黄種を興起」することが、「我が日本帝国の使命にして、大和民族の天職」であると強調した蘇峰は、大正青年の精神のたるみは「全国皆兵の精神」が、「我が大正の青年に徹底」していないためだとし、「尚武の気象を長養するには、各学校を通して、兵式操練」をするだけでなく、「学校をして兵営の気分を帯ばしめ」ることが必要だと記して「世界的大戦争」への覚悟を求めていた*25。
一方、第一次世界大戦の激戦に巻きこまれることのなかった日本は、「アジアのドイツ領や権益をおさえ」、「海軍はドイツ領南洋諸島を占領」することによって、第一次世界大戦による利益を手中に収めていた*26。それゆえ、国際的な危機を強調することで国民に戦争への意識を普及しようとした徳富蘇峰の主張は、政府の高官や軍人に受け入れられたこともあり、急速に「教育改革」の理念として国策としても取り入れられた。
たとえば、昭和一二年に文部省から発行された『国体の本義』では、大正デモクラシーを想定しながら、その後も「欧米文化輸入の勢いは依然として盛んで」、「今日我等の当面する如き思想上・社会上の混乱を惹起」したとして、これらの混乱を収めるべき原則として『教育勅語』の意義が強調された*27。
さらに文部省教学局は、『国体の本義解説叢書』の一冊として『我が風土・國民性と文學』と題する小冊子を発行して、「日本の国体」においては、「敬神・忠君・愛国の三精神が一になっている」として、「正教・専制・国民性」の「三位一体」を強調したウヴァーロフ的な「教育改革」を断行するようになるのである*28。
一八七九年に書いた『民情一新』で福沢諭吉は、西欧の「良書」や「雑誌新聞紙」
を見るのを禁じただけでなく、「学校の生徒は兵学校の生徒」と見なしたニコライ一世治下の政治を「未曽有(みぞう)の専制」と断じていたが、日露戦争に勝った後の日本は「暗黒の三〇年」と呼ばれるニコライ一世治下のロシア帝国ときわめて似た相貌を示すようになっていたのである*29。
芥川龍之介の『河童』と狂気の問題
しかも、日本やロシアのように西欧とは異なる「伝統」と持つ国家において、「国権」が強調されるとき、国の方針に反対する者を「非愛国的」と見なすような傾向も生まれる。
このような大正から昭和にかけての悲劇を象徴するような出来事が、第一高等学校から東京帝国大学へと進み、第四次『新思潮』の同人として短篇『鼻』で漱石の激賞を受け、華々しく文壇にデビューした芥川龍之介(一八九二~一九二七)の自殺であろう。
評論家の関口安義氏は、芥川が第一高等学校在学中に蘆花の「謀叛論」を聞いたという実証はできないとしながらも、親友井川恭や成瀬正一などが受けた強い印象の記述をとおしてその影響を見ている*30。たしかに成瀬正一によるロマン・ロランの『トルストイ』の翻訳にもかかわっていた龍之介は、その早すぎる晩年には『将軍』一九二二(大正一一)年、『桃太郎』(一九二四)などの短篇で「自国の正義」を主張して、国民を戦争へと駆り立てることを厳しく批判していたのである。
しかし、一九二五(大正一四)年に公布された治安維持法について司馬は、国家そのものが投網やかすみ網のようになっていたとし、「人間が、鳥かけもののように人間に仕掛けられてとらえられるというのは、未開の闇のようなぶきみさとおかしみがある」と鋭く批判した*31。このような状況下で書かれたのが、一九二七年に書かれた『歯車』である。ドストエフスキーにおける「分身」のテーマに注目した井桁貞義氏は、ここで芥川が『カラマーゾフの兄弟』や『罪と罰』に言及しつつ、自己の分裂の危機を描いていると指摘している*32さらに同じ年に書かれた『河童』で芥川は、「ある精神病院の患者」が語った話を記したという形で、「河童の国を借りて取り上げられる諸問題は、文明・風俗習慣・生誕・恋愛・家族制度・芸術・官憲の横暴・資本主義・法律・自殺・宗教」などの問題を取りあげていた。
このことを指摘した評論家の関口安義氏は、河童の国の音楽会で警察により「演奏禁止」が命じられる場面をとおして、芥川が「当時の日本の官憲による言論・表現への諸検閲制度を暗に皮肉っている」とした*33。
実際、語り手の〈僕〉に、「そんな検閲は乱暴じゃありませんか?」と河童の国を批判させた芥川は、河童のトックに「何、どの国の検閲よりもかえって進歩している位ですよ。たとえば日本を御覧なさい。現につい一月ばかり前にも……」と反論させながら、途中で沈黙させていたのである*34。
しかも、芥川は河童の国では、「労働者の見方をする新聞さえも実は資本家ゲエルに(さらにはゲエル夫人に)支配されている」とも書いていた。日露戦争に際してはこれを批判する者たちが「平民新聞」を創刊していたが、すでに昭和の初期には「国家」が行う戦争を批判するような「言論の自由」さえもが失われ始めていた。
事実、芥川が自殺した翌年の一九二八(昭和三)年に出された『統帥参考』という参謀本部の将校か陸軍大学校の学生しか見ることのできない「極秘中の極秘の本」に、「国が戦争になった場合、統帥機関が日本国民を統治する」と記されていた。さらに一九三五(昭和一〇)年には、それまで高等教育機関で使われていた美濃部達吉の著作『憲法講義』が発禁処分となって、「国民」の権利を保障する盾の役目を果たしていた「憲法」は完全に形骸化されるにいたった。こうして、明治時代に「国民」となったはずの日本の若者が、「臣民」として「国家」が遂行する「聖戦」に学徒動員などで戦場に駆り出される可能性が開かれることになったのである*35。
「言論・表現の自由を阻害することは、あってはならないと芥川は考えていた」とした関口氏は、「『将軍』への伏せ字問題その他で、彼自身が体験してきたやりきれない日本の現実であった」と続けている。このことは日本でも若きドストエフスキーが生きた「暗黒の三〇年」と同じように、まともな形で正論を唱えれば「狂人」とされるので、「狂人の手記」という虚構の形でしか正論を語れない時代が、すぐ近くまで来ていたことを明確に物語っているだろう。
『若き日の詩人たちの肖像』と『白夜』
日露両国の近代化の問題を『坂の上の雲』などの長編小説で深く考察した作家の司馬遼太郎は、堀田善衛や宮崎駿と行った鼎談で、芥川龍之介が自殺した後で中野重治など同人雑誌『驢馬』に係わっていた同人たちが「ほぼ、全員、左翼になった」と指摘している*36。そして司馬は、「後世の人たち」は「その理由がよくわからないでしょう」が、「私は年代がさがるので一度もなったことはないけれども」と断りつつも、「昭和初年、多くの知識青年が左翼になった」「そういう時代があったということは、これはみんな記憶しなければいけない」と続けていたのである。
つまり、「国家」への忠誠を求められる一方、自国の欠点に対する批判や軍部の方針を批判することも禁じられていた「昭和初期の日本」では、「出口」が見いだせないなかで、感受性豊かな青年たちが極端な「国粋思想」を批判する左翼的な思想に共感を示すようになったのである。
検閲の厳しかった昭和初期の暗い「別国」の時代に青春を過ごした司馬遼太郎の言葉は、自由思想すらも厳しく規制されていたニコライ一世の「暗黒の三〇年」の時期に、なぜドストエフスキーがペトラシェフスキー事件に関与するようになったのかをも説明し得ているであろう。
国内の劣悪な政治状況を放置したまま「為政者」にではなく「国民」に「道徳」を課し、これを批判する者を厳しく罰したこのような政治体制は、ロシアの場合と同じように「欧化と国粋」の対立の激化をも招くことになったのである。
さらに芥川は「河童」において、「職工屠殺法」によって河童の国では首になった職工を、肉にし、食糧に用いるということが法律で認められていると語る河童のゲエルに、語り手の〈僕〉にその非道さを批判させるが、しかしその後でゲエルに、「あなたの国でも第四階級の娘たちは売笑婦になってゐるではありませんか? 職工の肉を食ふことなどに憤慨したりするのは感傷主義ですよ」と答えさせていた。
すなわち、江戸時代には比較的安定した生活をしてきた農民たちは、明治維新後に地租税などが導入されたことや、さらに度重なる戦争による軍備費増大のための増税や徴兵により貧困化が進んだ。ことに冷害などの被害にあった東北地方などでは、家族のために娘を売らねばならなくなる農家も出てきており、「富国強兵」策により莫大な富を手にした軍需産業や政治家などの一部の特権階級と民衆との間に極端な格差が生まれていた。このような時代の状況が、幕末の日本と同じように二・二六事件などの軍事クーデターやテロを多発させる遠因になったと言っても過言ではないだろう。
大学受験のために上京した日に二・二六事件に遭遇した若者を主人公とした長編小説『若き日の詩人たちの肖像』で、堀田善衛はラジオから聞こえてきたナチスの宣伝相ゲッベルスの演説から受けた衝撃と比較しながら、ニコライ一世治下の厳しい検閲制度と迫り来る戦争の重圧の中で描かれた『白夜』の冒頭の美しい文章に何度も言及している*37。
この作品で堀田は烈しい拷問によって苦しんだいわゆる「左翼」の若者たちや、イデオロギー的には異なりながらも彼らに共感を示して「言論の自由」のために文筆活動を行っていた主人公の若者の姿をとおして、昭和初期の暗い時代を活き活きと描いていたのである。
しかもここで堀田善衛は、厳しい言論弾圧のもとに「右傾化」する時勢の中でドストエフスキーの読み方を変えていった愛読者の姿も描いているが、次節で見るように、太平洋戦争へと突入する時期に『罪と罰』を西欧的な世界への挑戦の書物とする見方が日本で高まったのも、このような政治の流れと無関係ではない*38。
『罪と罰』の解釈と「大東亜共栄圏」
評論家の松本健一氏は真珠湾攻撃の翌年に出版された堀場正夫の『英雄と祭典』にふれて、彼が『罪と罰』を「『ヨーロッパ近代の理知の歴史』とその『受難者』ラスコーリニコフの物語」ととらえ、「大東亜戦争を、西欧的近代の超克への聖戦」と見なしたことを紹介している。
むろん、このような読みは現在のレベルでの研究を踏まえた上での読みから見れば、明らかな「誤読」であると言える。しかし、堀場の「誤読」には、時代的な背景もあった。すなわち、ニーチェによるドストエフスキー理解を踏まえたシェストフは、ドストエフスキーをも「超人思想」の提唱者であり、「悲劇の哲学」の創始者の一人とした*39。
このようなシェストフの解釈が日本でも受け入れられる中で、優れた批評家であった小林秀雄ですら、『罪と罰』のエピローグではラスコーリニコフは影のような存在になっていると指摘して、書かれている彼の更生をも否定したのであった*40。それは「近代人が近代に克つのは近代によってである」として、欧米との戦争を評価した小林の近代観から導かれたものでもあった*41。
(拙著『ロシアの近代化と若きドストエフスキー』成文社、2007年、終章より。転載に際してはわかりやすいように、一部改訂を行った)。